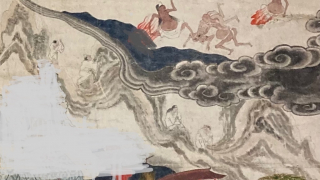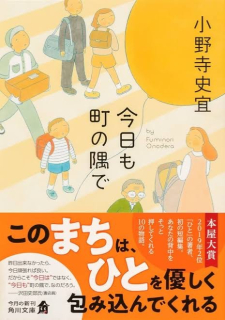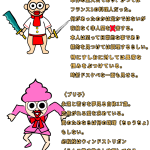神社仏閣珍道中・改
【神社仏閣珍道中】 …御朱印帳を胸に抱きしめ
人生いろいろ、落ち込むことの多い年頃を迎え、自分探しのクエストに旅にでました。
いまの自分、孤独感も強く本当に空っぽな人間だなと、マイナスオーラ全開であります。
自分は生きていて、何か役割があるのだろうか。
やりたいことは何か。
ふと、思いました。
神さまや仏さまにお会いしにいこう!
…そんなところから始めた珍道中、
神社仏閣の礼儀作法も、何一つ知らないところからのスタートでした。
なにせ初詣すら行ったことがなく、どうすればいいものかネットで調べて、ようやく初詣を果たしたような人間でありました。
そして未だ厄除けも方位除けもしたことがなく、
お盆の迎え火も送り火もしたことがない人間です。
そんなやつが、自分なりに神さまのもと、仏さまのもとをお訪ねしております。
もう何年経ったことか…。
相も変わらず、作法もなっていないままかもしれない珍道中を繰り広げております。
神さま仏さま、どうかお導きください。
- 投稿制限
- スレ作成ユーザーのみ投稿可
拙い文章、そして、愚かな人間がおろおろしつつ日々暮らす様子をただただ書き連ねたこのスレをご覧くださっておられる方々に心から感謝を申し上げます。
本当にありがとうございます。
お彼岸という期間に新たなスレをスタートするにあたり、日頃なかなか伝えずにまいりました思いを綴ろうと思っておりましたところ、東北の地で線状降水帯の発生を伝えるニュースを伝え聞き、一刻も早くこの忌わしい帯が解けるよう祈っておりました。
そんな昨日、娘婿に頼まれ孫を預かるべく一日外出しており、帰宅してから初めて能登半島の災害を知りました。
おりしもニュースの少ない時間帯、もどかしさに開いたSNSで投稿される輪島の映像に、大きな衝撃を受けました。
震災の傷跡がまだ色濃く残る能登の地にまた新たな災害が…。
言葉を失うばかりです。
ただただもう祈ることしかできません。
どうか命が守られますように。
どうか一刻もはやく雨がやみますように、水が引きますように。
不安な日々がこれ以上訪れることが
ありませんように。
祈ります。
願います。
お彼岸という期間は、文字通りの彼岸、御仏の住まわれる世界に最も近い期間であるとのことで、願いが届きやすいと聞いております。
どうか日本で起きている自然災害が一刻も早く鎮まり、人々が一日でも早く日常の生活を取り戻せますように。
…能登半島において今回の大雨による被害を受けられた方々は、元旦に起きた地震の被害でまだその日常すら取り戻してありませんでしたのに。
能登、東北、そして茨城で被害をお受けになられておられる全ての方に心よりお見舞い申し上げます。
【お彼岸】
〝暑さ寒さも彼岸まで〟
とはよく言ったもので、ついこの間まで夏日、それも真夏日の騒ぎをしていたというのに、今晩などは少し肌寒いくらいです。
ただこの慣用句で言うところの『彼岸』は一般的に言う【お彼岸】のことで、〝お〟を付けないと仏教的にはむしろ混乱してしまいそうです。
日本の仏教では、【此岸(しがん)】と【彼岸(ひがん)】という概念があり、
彼岸とは向こう岸、仏さまの住まわれるお浄土の世界(悟りの世界、あの世)を指します。
この、〝暑さ寒さも…〟で指すところのいわゆるお彼岸の期間、お中日を中心に一週間を指します。
私はこのお彼岸期間というのが七日間あることについて、これだけの期間があればどこかしらでお墓参りができるであろう、というものなのかと思っておりましたが、さにあらず、たしかにお墓参りをする期間でもありますが、残りの六日。
これは
『ご先祖様への供養を行い、仏教修行をすることで自分自身を見つめ直す時期』ということのようで、そんな仏教修行の一つ【六波羅蜜(ろくはらみつ)】といわれ、これは出家していない者たちに向けに説いた、悟りに至るための修行、といわれます。
【六波羅蜜】とは
・布施(ふせ)…施しをすること
・持戒(じかい)…規律を守ること
・忍辱(にんにく)…よく正しい心をもつこと
・精進(しょうじん)…目的に向かってたゆまず努力すること
・禅定(ぜんじょう)…常に平静な心をもち続けること
・智慧(ちえ)…智慧を磨き、智慧を働かせること
とされます。
…なるほどぉ。
六波羅蜜はちょうど六個六日間あるお彼岸に努めてこの六波羅蜜の教えを実践するということ?
あらあら、これは大変です。
(続き)
世にシルバーウィークと称された秋の三連休後半も終え、お彼岸も終わった気がしてしまいますが、令和六年の秋彼岸は、【9月19日(木)から9月25日(水)】までの七日間ですので、まだお彼岸中であります。
…ちなみにこの三連休という言い方、三連休でない方も多いというのになぁと、私はあまり好きではないのです。
かといってシルバーウィークについては言語道断、今年の秋のそれに至っては敬老の日を含んでいたため、自分では若いつもりの私は、このシルバーをシルバーシートとかと同義のいわゆるお年寄りを指すものと勘違いして、何でも言い換えを考えてしまうのはどうかと密かに心を波立たせておりました。
そもそも三日間しかないのにウィークとかおかしいし。
まぁその点、このお彼岸は〝お中日〟である『秋分の日』の二十二日を中心とした前後三日の計七日間、文字通りウィークでありますが。
閑話休題。
このお彼岸を詠んだ松尾芭蕉の句があります。
>今日彼岸
>菩提の種を蒔く日かな
芭蕉はこの時節、菩提の種を蒔いて、悟りの世界へ渡る心掛け、実践を詠んでいます。
【菩提】とはサンスクリット語のbodhi(ボーディ)の音写であり、世俗の迷いを離れ、煩悩を絶って得られた悟りの智慧のことであり、仏の悟りの境地であります。
bodhiの漢訳は『智』『道』『覚』。
菩提を得た者こそが仏であり、これを目指す者が菩薩であるとされます。
この芭蕉の詠んだ菩提の種を撒く、〝心掛け・実践〟こそが前レスに書いた【六波羅蜜】を心掛けることであり、六波羅蜜の実践となりましょう。
……。
たかが一週間の間であるというのに、なかなか六波羅蜜の実践は難しく感じられ、己がいかに未熟者であるかを感じます。
心掛けるだけでも良しとするのが仏教であり、この芭蕉の句はまさにこの仏教の教えを端的にあらわしていると言えましょう。
芭蕉って凄いなぁ。
俳句って本当に奥が深い。
…あれ?
そこじゃないか。
でも本当に芭蕉の凄さ、俳句の奥深さをあらためて感じました。
そうかぁ…今日も六波羅蜜を、かぁ。
いや明日もだ。
…煩悩おばさんは今日も明日も悩むようです。
【絵解き】
とあるお寺さんで、秋彼岸のお中日に絵解きをしてくださると知り、うかがいました。
そのお寺さんに伝わる、一般に地獄絵図と呼ばれる絵図をもとに法話をくださるので『絵解き』。
それも個別、なかなか得られる機会ではありません。
貴重なお話。
しかしながらここに書くことに抵抗があった私。
ここをお読みくださる方にそのお話を曲げずに、漏らさずに伝えることができる自信がかけらもないこと。
そして。
衆生が地獄に堕ちるようなことがないよう、地獄の恐ろしさを描かれた絵をもとにお話いただいたものですので、できればその絵をここにあげたい。
けれども、衆生の心に焼きつけられることを目的に描かれた地獄絵図は見ようによっては、今傷ついた心をお持ちになって、あるいはつらい思いを抱えて、ここミクルさんを訪れておられる方のお心に変に刺さったりはしないかと、私の中で葛藤がありました。
一回一回、その画像をアップしたのち、全く違う画像をはさむことによって、ここをお読みでない方の目に触れることは最小限に抑えられるのではないか、そんな考えに至りました。
【絵解き】と表題を入れたところはそうした絵がアップされていることをご了承、ご理解いただいた上でお読みください。
あまり時が経つと、こんなありがたい貴重なお話を、私は一つ漏れ二つ抜けと忘れてしまうので。
手のひらに乗せた砂よりも水よりも早く零れ落ちる私の記憶です。
(続き)
この『死出の山』と称される死後四十九日間かけて歩く途中、七名の審判を受けるとされます。
それを仏教的にどう採るかは、宗派、あるいは個人の見解、何よりも地獄絵図を描いた作者によって異なるようであります。
だいぶ前にはなるかと思いますが、この珍道中録でも触れたことがございますが、
【十王】と呼ばれる死後の裁判官的な存在による裁きを受け、それによって死後の世界が決められる、というものと、
やはり七日ごとにお会いする御仏がおられるという説とがあり、
さらには混在するものもあって、なかなか絵解きも大変なようです。
といいますのも、日本に仏教が伝来するのは中国から、であって、この中国において【道教】と習合したからであります。
中国で道教と習合するにあたり、『閻魔王授記四衆逆修生七往生浄土経』が作られたといい、さらには十王信仰も生まれたといいます。
ではお釈迦さまのお生まれになられた地、インドにおいてはこの〝地獄絵図〟と呼ばれるものがないかというと、やはり存在していたと、実際にその地を訪れ学ばれた僧侶である、私に絵解きをしてくださった方がおっしゃっておられました。
では現在日本において伝わっている、いわゆる〝死後の世界〟についての考え方、教えは、というと、冒頭述べましたとおり、いくつかの説が存在しているようです。
それは同じ〝仏教〟であっても、宗派というものがあるということもあり、なによりもその寺に伝わる〝地獄絵図〟によるものが大きく作用してまいります。
なぜなら。
自分のお寺に伝わる〝地獄絵図〟にはっきりと十王の姿が描かれていたら、本来なら語りたい、死後の世界でお会いするとされる御仏、いわゆる【十三佛】さまを語ろうにも、十王が描かれ、しかも大きく役割が示されていたら、…それはなかなか難しいものとなりましょう。
なぜこのようなことになったかといえば、やはり日本においても仏教伝来前にあった教えとも結びつきましょう。
いわゆる大きな意味での神仏習合、であります。
ですが日本においては、どちらかというと平安末期において、仏教由来の末法思想や冥界思想と結びついたと考えられるようです。
そうした中、日本でも『地蔵菩薩発心因縁十王経』なるものが作られています。
このお経の中には『三途の川』や『奪衣婆』が登場しているといいます。
【絵解き】
四十九日間の旅を終えて、たどり着いた川。
三途の川と呼ばれる川です。
ここには橋が描かれていますが、この川の渡り方はその人間の生きてきた生き方によって篩い分けられています。
そう、四十九日間死出の山を歩いてきながら受けてきた裁きによるものであります。
しかしながら。
そう解く説と、死してまもなくこの川に来るという説とに分かれるものもございます。
この先閻魔大王に会うとするならば、十王の裁きを受けるという説を採ると、辻褄が合わなくなるのです。
十王の裁きを受けて閻魔大王の前に来るとするならば、閻魔大王の裁きは三十五日、であるからです。
初七日=一七日、二(ふた)七日、三七日、四七日、五七日=三十五日、三十五日目に閻魔大王にお会いすることになっているからです。
この後六七日があって、七七日=四十九日となりますので、この死出の山を越えてから、という説ですと、このあとに閻魔大王に会うことになるので、十王の裁きを受けるという説ではおかしなこととなってしまうのです。
仏教で説くところの〝初七日忌には不動明王さまにお会いして過去を懺悔する〟、というものと大きなズレが生じてしまいます。
そもそも同じ仏教であっても、宗派によっては、説かれている死後の世界が大きく異なるのです。
浄土真宗においては死と同時にお浄土に生まれ、仏さまに成らせていただくという教えでありますので、こうした死出の山を歩くこともなければ、裁きを受けるということもなく、死後まもなく御仏のお導きでお浄土で仏となるという考えでありますので、当然この地獄絵図とは無縁となります。
まぁ、その辺は宗教的なものとなり、神道におけるもの、キリスト教におけるもの、その他の宗教におけるもの、さまざまな死後が説かれておりましょう。
そういった違いであると、私のような無宗教な者は、なんでも受け入れられ、逆に受け入れたくないものは避けて通れるというお気楽な考えでいられる存在でございます。
と、まぁ、今回そこについて触れだすとこんがらがります。
実際、この地獄絵図と呼ばれる絵をお持ちのお寺さんにおかれましても、きっと描いた作者とのズレのあるお寺さんもありましょう。
この図は、十王の裁きを受けるでなく、死出の山を越えて三途の川にたどり着いた、といったものが描かれているものでございます。
(続き)
この絵では三途の川に立派な橋がかかっているさまが描かれています。
歩いて、あるいは泳いで渡る人物は描かれてはいませんが、細い、おそらくは浅い川が手前に描かれ、橋の向こうはいかにも深そうな川が横たわるように見受けられます。
三途の川は、此岸(しがん=現世)と彼岸(ひがん=あの世)を分ける境目にあるとされる川とされます。
三途は仏典に由来し、餓鬼道・畜生道・地獄道を意味するとも聞きます。
このいわゆる彼岸、あの世への渡川・渡航は、オリエント起源の神話宗教やギリシア神話にまで世界中で見られるものであり、三途川の伝承には民間信仰が多分に混じっているとされます。
もちろんそれは三途の川と呼ばれはいたしませんが。
一説には、俗に三途川の名の由来は、初期には「渡河方法に三種類あったため」であるともいわれるといいます。
これによれば、
善人は金銀七宝で作られた橋を渡り、
軽い罪人は山水瀬と呼ばれる浅瀬を渡り、
重い罪人は『強深瀬』あるいは『江深淵』と呼ばれる深くて広い難所を渡る、とされているといいます。
またこの川には悪龍が住んでいるとも。
そして。
三途の川というと有名な【奪衣婆】が描かれています。
一般に三途の川には十王の配下に位置づけられる『懸衣翁』・『奪衣婆』という老夫婦の係員がおり、六文銭を持たない死者が来た場合に渡し賃のかわりに衣類を剥ぎ取ることになっており、文字通り『奪衣婆』が衣類を剥ぎ取り、その衣を木に掛けるのが『懸衣翁』。
この絵では懸衣翁は描かれていないように思えますが、この衣を木にかけると罪の重い人間は木の枝が大きくしなり、罪の軽い人間はその枝はほとんどしなることがないといいます。
これで三途の川を渡る場所が決められるとされます。
ただ、この絵だと明らかに三途の川を渡った後、奪衣婆に会っているように思われますが…。
このうちの奪衣婆は江戸時代末期に民衆信仰の対象となり、多く像や堂が造られたり、地獄絵の一部などに描かれたりしています。
一説には奪衣婆は閻魔大王の妻とする説もあります。
そして。
三途の川の河原は【賽の河原(さいのかわら) 】と呼ばれます。
(続き)
注)ここでは先に挙げた地獄絵図について触れます。
三途の川の奪衣婆のそばにお地蔵さまが描かれているのにお気づきかと思います。
このお地蔵さまのおられるところは、俗に言われる【賽の河原】であります。
お子さまを亡くされた方は表現によってはお心の傷に触れることもあるかもしれないと思いますので、ここまででお閉じいただければと思います。
三途の川の河原は【賽の河原(さいのかわら) 】と呼ばれ、親に先立って死亡した子供がその親不孝の報いで苦を受ける場とされています。
ちなみにこれは俗信に基づくものであるとされ、本来仏教とは関係のないものと言われます。
しかしながらあまりにも世の中に浸透しておることから、当然この話を知らないお坊さんはおりませんし、
お寺さんにはかなりの数、慈母地蔵さまの像や水子地蔵さまの像がお祀りされています。
これらのお地蔵さまの御像はお子さんを亡くされた親の心に寄り添うべくお寺に祀られたことでありましょう。
賽の河原では亡くなった子供たちが親の供養のために積石塚または石積みの塔を作るべく石を積んでの修行をしており、この塚、あるいは塔を完成させると、現世にいる親の供養になるとされています。
しかし完成する前に鬼が来て塔、あるいは塚を破壊し、何度塔(あるいは塚)を築いてもその繰り返しになってしまうと言われています。
しかしその子供たちは、最終的には地蔵菩薩によって救済されるとされています。
これは仏教の地蔵信仰と民俗的な道祖神である賽(さえ)の神が習合したものであるというのが通説であります。
お地蔵さまはたとえそこが地獄であろうと、どんなところにでも訪れ衆生を救済してくださる御仏とされています。
それゆえこの賽の河原にも子供を救いに来てくださっている、とされます。
以前購入した『関東百八地蔵尊霊場』という本があるのですが、そこの冒頭に『地蔵和讃』なるものが書かれていて、この和讃、賽の河原の様子がしかと描かれたもので、これを目にするたび胸が切なくなっていたたまれなくなり、本を閉じてしまいます。
百八と数が多いから、というのもありますが、この地蔵尊霊場めぐりに行こうと思えないのはこの和讃が載せられていることに起因していると言っても過言ではありません。
【絵解き】
さて。この絵の中央に描かれているのが、地獄といえば、というくらいの閻魔大王さま。
これこそがお坊さんにとってなかなか難しい扱いとなる存在で。
この絵解きをしてくださったお坊さんも何度も口を濁すかのように語っておられました。
日本の仏教においては、人が亡くなられたのちの考えがいくつも枝分かれしておりまして、四十九日という考え方すらしない宗派もあるくらいです。
また同じ四十九日、十王の裁きを受けるパターンと、御仏のお導きを受けるパターンとに大きくは分かれます。
四十九日を仏教に基づいて語るならば、十王さまのお裁きではなく、七日ごとにそれぞれの日に定められている仏さまにお会いすることとなっています。
ゆえに、三途の川も存在しなければ、奪衣婆もおらず、この閻魔大王さますらも存在していないのです。
…困るでしょう?
なにせその存在しない閻魔大王さまが大々的に中央に描かれているのですから。
ちなみに。
初七日では不動明王さま。
二七日では釈迦如来さま。
三七日で文殊菩薩さま、
四七日では普賢菩薩さま。
五七日でお会いするのはお地蔵さま。
…ちなみに十王さまの裁きを受けるパターンですと、まさにここでお会いするのが閻魔大王さま、とされているのです。
六七日は弥勒菩薩さま。
七七日には薬師如来さまとお会いするとされています。
もちろん仏さまとお会いしている間もお裁きを受けていることは代わりはありません。
故人はそれぞれの御仏の前で生前(前世)の行いを懺悔し、御仏によっては智慧や、この死後の修行で得た悟りや徳を授けていただきながら死出の山を登って行くのです。
お坊さんは葬儀の席においてはこの故人の四十九日間の修行についての説法をされます。
もちろん、宗派によっては死後まもなく御仏が迎えに来られると説かれます。
この場合は迎えに来られる御仏の数が異なると聞きます。
それは上品(じょうぼん)の上生〜下品(げぼん)の下生の九通りがあり、楽器を奏でながらたくさんの御仏が迎えに来てくださったり、たった一人の仏さまが蓮座(亡くなられた方が乗る台)だけを持ってこられるという、生前の行いによって迎え方のランクがあるのだといいます。
(続き)
この地獄絵図、三途の川も、奪衣婆さまもおれば、十王の一人、閻魔大王さまも描かれています。
死後故人が四十九日までに歩まれる道や修行のお話を説かれたお坊さん、この絵解きをなさるときは結構ドキドキだと思うのです。
お寺さんによってはこうした地獄絵図のないところもあります。
死後すぐに成仏される宗派ではまさにそうでありましょう。
そうでなくとも地獄絵図を持たないお寺さんは多いかもしれません。
聡いお子さんにその矛盾を問われたらどう答えたら良いか非常に悩まれることでしょう。
しかしながら。
こうした地獄絵図で絵解きをし、あるいは閻魔大王の大きな像を前に、地獄極楽を説いて、子らに生前の善行を説くのもまたお坊さんの大切な説法、お仕事であります。
実際、こちらのお寺さんでは夏にこの地獄絵図をもとに、子どもたちに悪いことをせずに生きることの大切さを話しているとおっしゃっておられましたし、御本堂には大きな大きな(…たぶん…)丈六の閻魔さまの坐像が祀られています。
坐像の丈六、ですので二メートル四十センチ、となります。
これほどに大きな、恐い顔をなされた閻魔さまの御像は子どもたちにとっては本当に恐ろしい存在でありましょう。
地獄絵図を飾らずとも閻魔さまの御像が祀られでおりますので、こちらのお寺さんにとってはどちらも本当、なのです。
なのでお坊さんはこの絵図を前にして死後仏さまのもとで修行されることもちらっと述べつつ、閻魔大王の前で裁きを受ける話もされるのです。
この絵図に描かれた【浄玻璃の鏡】についてもきちんとその役割を語り、嘘をついてもここに生前の行いが映ってしまい、いかなる隠し事もできないこと、嘘をつくと舌を抜かれることも話しておられました。
長い長い仏教の歴史において、インドから中国に渡った時点でこの十王伝説はすでに組み込まれ、日本に伝来しておりますし。
人の正しい生き方、道を説くお坊さんという存在は、多少の矛盾点などよりも何より正しく生きることを説くのであります。
寺子屋などでさらに文字やら算術などをも、子らに教えていたのがお坊さんでありました。
また、かつては市中においてこの地獄絵を手に地獄の恐ろしさを語り、人として正しく生きることの大切さを説いていた尼さんもいたというお話もお聞きしました。
【絵解き】
この閻魔さまの前にうっすらと描かれているものに、お坊さんのお話無くしては気づくことはできませんでした。
こう拡大すると微かに見えますでしょうか。
人が真っ逆さまに落ちていくさまが描かれています。
地獄絵図ではたった一枚の平面に地獄の様子を盛り込んで書くので、実際にはこのように閻魔さまが裁きをされている真ん前を落ちているわけではないのだと思います。
ひたすらひたすらただひたすらに落ちて落ちているのです。
しかもただただ真っ暗な空間なのだと伝えられているといいます。
落ちて、落ちて、落ちて。
底に着くまで実に二千年、真っ暗闇の中を落ち続けるのだといいます。
二千年ひたすら落ち続けることが罰なわけではありません。
二千年落ち続け、ようやく到達した地点で、ようやっと罰を受けることができるのだということなのです。
他にも地獄の責め苦の様子が描かれています。
舌を抜かれているさまを描かれているのは見えます。
針の山を登って行く様は見てとれましたでしょうか。
そう。
地獄は大きく分けて二つとなります。
それがそれぞれに分かれているのだといいます。
ここ。
ここ地獄は『八大地獄』なのだといいます。
そしてその八大地獄に対して、『八寒地獄】となるのだといいます。
そしてそれがまた八つの地獄にわかれます。
等活地獄
黒縄地獄
衆合地獄
叫喚地獄
大叫喚地獄
焦熱地獄
大焦熱地獄
阿鼻地獄
となるのだといいます。
上から罪の軽い順になるといいます。
この一つ一つに、十六の小地獄があるといいます。
書いているだけで気が遠くなりそうです
【絵解き】
お坊さんがまず語ったこのひたすら暗闇を落ちていく地獄は一番重い阿鼻地獄にあるようです。
阿鼻地獄にある、というよりは阿鼻地獄へ落ちる亡者というのが正しいのでしょう。
しかもこのひたすら落ちていく期間はもっともっと長く語られることもあるようです。
別名無間(むげん)地獄。
休む間もなく苦しみ続ける地獄であり、『阿鼻叫喚』の言葉の語源の阿鼻地獄となります。
阿鼻というのもまた『間がない』という意味といいます。
途切れることのない責苦を受け続けること432000000年といわれます。
またその責苦は他の地獄での責苦を全て足してさらにパワーアップしたものだというのです。
さすがに時間の関係で、ここはさらりと流しておしまいとされていました。
ネットで調べるとどんな人が落ちていく地獄であるか、どんな責苦を受けるのかは書いてあります。
私も見るには見たのですが…気が重くなるので割愛します。
小さくて見づらいですが、刀剣の刃が無数にあります。
刀剣の刃の山があるのは衆合地獄、上から三番目に重い地獄のようです。
刀剣の刃の山の上では女の人が誘っているといい、スケベな男はこれを追って刀剣の刃の山を登ってしまうのだと、お坊さんは語っておられました。
血だらけに描かれています。
途中で転落している姿もあります。
ようやく女の人のもとに到達しようかというところで女の人の姿は消え、いつの間におりたのか、今度は下で誘うのだと。
その繰り返しだとおっしゃいます。
そういう男性の堕ちる場所だと。
…私がここでそおっと夫の顔を覗いて見たのはいうまでもありません。
普通な顔で聴いていました。
そこには自分は堕ちないと思う顔でありました。
…ま、そうかもしれないな。
下の方には女の人ばかりが描かれています。
地獄はなんでも136もの種類があるといわれますが、女性専用の地獄があるようで。
一応は女性である私を前にして語りづらかったのか、あまり詳しくは語らなかったお坊さん。
描かれているのは灯芯で竹の根を掘る地獄と、その下に描かれているのはネグレクトをはたらいた母が落ちる地獄だと解説されました。
灯芯で、って…。
あの時代劇で見かけるお皿に油を入れてそこに糸をひたして灯とする、あの糸のことですか?
…どれだけ不毛な。
【絵解き】
…この地獄絵にはもっともっと地獄のようすは描かれており、お坊さんもその地獄での様子を一つ一つこんな罪を犯してこういった責苦を受けているのだといった説明をしてくださいました。
しかしいざ実際こうしてレスするために文章にしたり、果ては不確かとなった記憶をたしかめるべくネットで調べたりすると、気が重く滅入ってしまうのです。
この地獄絵に描かれたものなどほんの一部に過ぎませんので、あと少し、あと少し語れば終わることなのです。
でももう食傷気味で。
絵を揚げるのも、ましてやそれを文章化するのも厳しいと思えて、無理だなぁと、
あと一つだけ、お坊さんが何を思ったのか丁寧に説明してくれた絵で終わりたいと思います。
もうこの絵は拡大もせず、原画のままを載せておきます。
一人の男性が身体が蛇の女性二人に巻つかれた絵があります。
これは妻と浮気相手の女性の顔だといいます。
ずっと体に巻きつかれたまま恨み言を聞く罪なのだといいます。
火車に乗った絵については「これは軽い罪の人です」とだけ。
そして。
この地獄においては死ぬことがない、死ぬことができないので、身体がめちゃくちゃに原型をとどめないほどになろうとも、また元に戻されて延々と同じ責苦を受けるのだといいます。
はあぁ…。
そして最低でも何百年単位、罪を償うべく地獄の処罰を受けたのち、人は転生するのだといいます。
もちろん最下層に落ちれば、限りなく永遠に近い年月をそこでひたすら責苦を受けながら過ごすので、転生の道はほぼ無いのでありますが。
…まぁ、せめて地獄では自分の犯した罪を素直に認めたいと思いました。
嘘をつけばさらに罪が加算されそうです。
そんな嘘通りっこありませんから。
閻魔帳とか浄玻璃の鏡やら、嘘など決して通せるものではありません。
この絵には上部に六道の絵が描かれています。
六道図ともいえましょう。
天道。
人間道。
修羅道。
畜生道。
餓鬼道。
そして地獄道。
どこへ行くか。
そう、それは御仏の元での修行か、
あるいは十王さまのお裁きか。
それを決めるのは実は他ならぬ自分自身、なのかもしれません。
【かつぎ地蔵】さま
さて。
調べてまいりました、群馬県は前橋市の市立図書館で。
こちらの司書さんは大変丁寧なお仕事をなさる、というか心にまで寄り添ってくださるかのお仕事をされる方で、それはもう痒いところに手が届くというか。
私の調べたい資料がバンバンと揃い、びっくりするほど能率的にかつぎ地蔵さまについて調べることができました。
ここをお借りしてあらためて御礼を申し上げます。
結論から申し上げますと、私の推測どおり、あのお地蔵さまはあの上新田という町のはずれを守るお地蔵さまであり、あのお地蔵さまをかつぐわけではありませんでした。
それではいざこのお地蔵さまをどのように?
…じつは、ですね。
それはさすがに図書館ではわからなかったのです。
前橋市の一町会に過ぎない行事のこと、そこまでの資料はありませんでした。
ならば公民館、とも思ったのですが、この地域の公民館は常時人が駐在しているわけではないようで、平日も含め二度ほど足を運んでみたのですが、どなたもおられず、どこにこのかつぎ地蔵さまが安置されているかまではわかりませんでした。
あとは…うーん、気になるところではありますが、運を天に任せるしかないようで。
ですが。
ですがですね、どういった形でかつがれるかはわかりました。
いわゆる〝御神輿〟。
神さまではありませんので、お地蔵さまの御輿と申しましょうか。
お神輿の中にお神輿におさまるくらいの小さな小さなお地蔵さまが、上新田町の〝かつぎ地蔵〟さまに特化するならば二体、安置されており、この御神輿、ならぬ御輿をかつぐのでありました。
しかも上新田町だけはなく、前橋市の一部で同じようにかつぎ地蔵さまの習慣が伝わり、調べられただけで四町会。
同じ前橋市内でも利根川沿い、もしくは少し離れてはいるものの、その間にある町会にもかつてはあったと仮説を立てれば、前橋市の東にその〝かつぎ地蔵〟の慣習があり、それはむしろ、まさにあの【佐渡奉行街道】に沿って、あるいはその町会に隣接した町会で行われている(いた)ことがわかりました。
そしてさらに興味深いことに、前橋市のみならず玉村町にも〝かつぎ地蔵〟の慣習があり、さらにいうならば玉村町もまた【佐渡奉行街道】であるということ。
どんどん壮大に(?)なってまいります。
ワクワクが止まりません。
図書館で調べることには限界があることを知って、まずはこの、かつぎ地蔵を知ることとなった前橋市上新田町を歩いてみることといたしました。
と、いいつつも車を使うあたりが姑息というか…。
群馬県は免許保有率とか車の保有率が全国的にも一位二位を常に争うほどのクルマ大国、車が足代わりな県民性があるとか無いとかなので、生まれも育ちも群馬県民な私ども夫婦、歳を重ねるごとにその傾向はどうしても強くなります。
そうは言っても免許返納も視野に入れて、少しづつは歩く習慣を増やして行かなければいけないとは思い、日々努力しておりました私でありましたが、ここ数年動くとつらかった身体は、喘息の診断を受ける直前からもうズタボロでして。
今まで自転車でスイスイ出かけていたところももはや車の移動しか考えられないほどとなっており、そこにまた落ち込む私がいたりもするのですが…。
(以下、書いているうち愚痴となってしまいました。
ここまででお閉じください。)
呼吸器内科に受診するまでの三年間、胸部レントゲンには映らない、呼吸器内科の先生が驚くほどの大きな肺炎の跡があることにどこの内科を受診しても気づいてもらえず、気のせい扱い、果てはあからさまに精神疾患扱いまでするドクターまでおり、正直メンタル的につらい時を過ごしておりました。
肺炎の跡と書いてはおりますが、肺炎真っ盛りのときにすら気づいてもらえず、自己免疫だけで自然治癒させていた、ということです。
コロナには罹患せずここまで来ておりますが、あの病のせいでそれほどまで大きな肺炎にも気づいてもらえず、多くの患者を産み出すこととなったあの病のせいで薬の不足から薬すら出してもらえなかったわけで、いかにあの病が恐ろしいものであるかを痛感するのであります。
いくつか受診した内科医院あるいはクリニックの中には、コロナ検査をし症状だけ聞いて聴診器すらあてず、薬すら出さない医師もおりました。
コロナで無いことを確認したならば、そのくらいの診察をしても良かったのでは無かったのだろうか。
内科でありながら「今日は予約でいっぱいなので最短で二日後となります」
とまで受診者数を制限していたクリニックでありました。
しかも
「知っていると思いますが、呼吸器症状の関係の薬は不足してるので出せませんので」
つまりはコロナの検査だけでした。
はあぁ。
(愚痴レスが続いております、すみません)
ようやく呼吸器内科にかかることができ、飛躍的に呼吸が楽になったのも数日。
今度は起き上がれないほどのだるさが。
喘息という疾患に最もポピュラーに使われる薬剤が私には合わず、その副作用に苦しむこととなったのです。
二週間後の予約まで待てず、電話で相談したところ、先生からわざわざ折り返しのお電話をいただき
「それはオーバードーズだわ、すぐにその薬剤を減らしていきましょう。日に三錠のんでいる薬を一錠だけ、寝る前に飲んで様子をみましょう。体内に残った薬の効果が落ちてくるまで少し時間が必要になるけど、必ず抜けてくるし、これは就学前くらいのお子さんの飲む量だから怖いだろうけどその量は飲んでいてね」
す、すごいなぁ。
薬の効果も、ですが、先生の対応の神なことといったら♡
薬の効果はまさに匙加減なんだなぁ。
その人その人の体格、体質でこうも副作用という効果を産み出すこととなる。
ちなみに最初から先生は
「子供の飲む量ですが、これで様子をみます」
と体格からの判断をされていてのことです。
なので今はお薬の調整中であり、副作用からの身体の立て直し中となります。
再来年の午年には秩父三十四観音霊場が一斉に御開帳となります。
元気に行くぞぉ〜!
…信じられない光景を目にしました。
末法の世、ということですか。
とあるお寺の境内。
本堂の前、外にお護摩の席が設られていました。
弘法大師がその手に持つ【五鈷杵】という法具がその護摩壇に置いてありました。
護摩の場から席を外した僧。
出店に来ていた業者さんのところへ行くのがみえました。
その出店では商品の並べられたテーブルの前にポスターが貼られたベニヤ板が掲げられていました。
僧がそのポスターの顔写真の部分にパンチするのが見えました。
それだけでも品のない行いです。
しかしながらそれだけではなかった。
その僧の手にはよりにもよって『五鈷杵』が握られていたのです。
五鈷杵の尖った部分をポスターの顔に刺すような形で当てていたのでありました。
たしかに、かつて五鈷杵は武器でありました。
しかし法具となって久しく、ましてや真言宗のお寺では弘法大師の手に持つ五鈷杵は大切な大切な法具、であるはずですが…。
たとえ手に何も持たずとも、大の大人が大人気ない行動です。
しかしこの場合はもっと大きな意味をもちます。
僧が、たとえポスターの顔写真であっても、五鈷杵の先端を向けて刺すような行いを、人前で、人目も憚らず、とったということです。
昨年はこの僧、お数珠を地べたに置きました。
ここは本当に寺、なのでしょうか。
この方は本当に僧なのでしょうか。
尊敬する方の菩提寺であるため、大祭ということで伺っておりましたが、もう二度と、この寺に行くことはありません。
僧といえども人間であり、過ちを犯すことはあると、以前とある僧の横領事件を受けて思いはしました。
でもそれ以上にこの僧の行いは不愉快です。
人としての過ちではなく、僧として終わっています。
昨日から七十二候の第五十候の菊花開(きくのはなひらく)なようです。
わが家の猫のそれよりも狭い、ネズミのひたいの庭の菊はまだまだ咲きそうにありません。
それでも酷暑であった今年の夏の陽射しにも気温にも負けることなく、青々とした葉を繁らせてくれています。
庭の菊たちはすべて花瓶の中で根の出たものを土に植えたもの。
小さな、新たな命のつながりに感動し感謝して、いそいそと土を買い求め「頑張ってこのまま根付くんだよ。毎日お水をあげるから頑張って」
たまに小さく口に出しているときもあります。(怪しい 笑)
そんなわが家の愛おしい菊たち。
お墓参りのときにご先祖さまに、と思うのですが、お彼岸にはつぼみもついていないし、十月の父の祥月命日にはまだ咲かず、十一月の義父の祥月命日には花の時を終える。
あまのじゃくな私の育てている菊たちは、どこか私に似てしまう?
あともう少しすると、私の好きな菊の香りいっぱいな庭になります。
私がかつぎ地蔵について図書館に行って調べ、わからないことが出てきたのもありましたが、どんどんと壮大なこととなってきたと語っておりましたのを覚えておられますでしょうか。
早くにとりあえず書き出せばよいものを、なかなか気が向かず、体調も悪いこともあり、どうにも書くことができず。
それでも少しづつ呼吸器の不調はコントロールされるようなり、ここで書いておかないとお蔵入りさせてしまう不安を抱きだしました。
図書館の司書さんのお手を煩わせ、それどころか私に寄り添うように適切、的確な資料を揃えてくださったというのに、そこすらも書けていない。
いかんな。
…毎日思うのです。
重い腰をあげてみますか。
それでダメなら、…まぁそれはそれで仕方がない。
始めてみましょう。
まずは前橋市のどこの地域で『かつぎ地蔵』さまの習慣があるか。
それは私が調べたかぎりでは、【東(あずま)地域】。
…これがまた実におかしなことにこの東地区、前橋市の南西部にあるのです。
まずはこの謎解きから。
これは実は明治時代に、『東村』と呼ばれた村であったから、なのだそう。
それが昭和二十九(1954)年にこの東村が前橋市と合併して『東地区』となったから。
…なのだといいます。
さらにはこの東村にはあずま道(東山道=とうざんどう)という道が通り、このあずま道というのは実に奈良時代の官道(かんどう)であったといい、これは畿内から信濃・上野(こうずけ)・下野(しもつけ)・奥州へと続くものであったといいます。
このあずま道がこの明治の合併で東村となった村々をを横断していたといい、そのため東(あずま)村と命名されることになったといいます。
以下に挙げる図が前橋市東(あずま)地区、となります。
あずま地区の郷土カルタの絵札になります。
(続き)
この東地区、この『あずまカルタ』の地図ではわかりようもないのですが、利根川がこの地区の東側を流れ、さらには滝川と染谷川という川があります。
この滝川という川を含んだ町を『川曲町』といい、まさにこの滝川が実によくくねくねと曲がっており、
あずまカルタには
『滝川の曲がるところが川曲町』
と読まれているくらいであります。
この滝川、実はかつて人工的に造られた川であります。
江戸時代、いま総社町と呼ばれる場所を治めた総社城主秋元長朝によって開削がされた『天狗岩用水』からの流れをくむものであります。
天狗岩用水は利根川から取水して八幡川合流地点までの全長八キロ。
八幡川合流後また開削が進められたのがこの『滝川』であります。
滝川はこの川曲町で直角に近い曲がり方をしており、川曲町で滝川沿いを歩くとそれを実感できます。
滝川は二十一キロ延長され前橋市、高崎市、玉村町まで流れ、今もその土地土地の水田を潤し、利根川に合流するのです。
染谷川は榛名山麓を源流とし、この東地区では江田町を東西に二分して隣接する高崎市の大類町で井野川という川に合流しています。
…私が住んでいた地区は利根川の反対側で、川からはかなり離れた土地であったこともあり、この東地区というのもいま、この辺りを調べ歩いて知ったものであるくらい。
まぁ、ひとえに私がぼーっと生きているから、なのでありましょうが 笑。
かつぎ地蔵はこの東地区、そして玉村町にも残るものであるので、『佐渡奉行街道』沿いでもありますが、この滝川沿い、とも言ってもよいのかもしれません。
今は廃れて埋もれてしまった地域もあるかもしれないことを考えると実に興味深いものであります。
本日は父の三十三回忌にあたる祥月命日であります。
とはいえなんら法要も営むことなく。
記憶にある人間が心のうちで手を合わせる、あるいは墓前に詣でる程度でしかありませんが。
この、父の眠る墓を祭祀承継をしてくれているのは父の弟である叔父の息子さん。
従兄弟、という存在になりましょうが、私はこの方のお顔すら拝見したことがなく、お寺さんによると三重県にお住まいになられているのだとか。
祖父母は彼にとっても祖父母であり、また彼の父親である叔父も一昨年に亡くなったようで、このお墓には彼にとっても祖父母と父親が眠っています。
直系の方々の法要は営むにしても、伯父の法要などはまず考えもしないのがごく当たり前なこと。
実の娘がおりながら、一緒に墓に入っている父も合わせて祭祀承継し、墓を守ってくれていることを、ただただありがたく、申し訳なくも思うのですが、両親が離婚して、母に引き取られた私ども姉妹。
私などは葬儀にすら出られなかったくらいであります。
だからこそこの三十三回忌、私にとってはとても大切な日に思えておりました。
とはいえ、檀家でもないうえに、そもそもその祭祀承継者の従兄弟にあたる方に許可を取ろうにも連絡先も知らず。
せめてもの思いを込めて写経し、それをお寺さんに奉納してまいりました。
心だけの、たった一人の三十三回忌でありました。
そんな父を御仏が哀れに思ってくださったのか、空は気持ちの良い秋晴れ。
絶好のお墓参り日和でありました。
今日は旧暦九月十三日、十三夜です。
十七日がスーパームーンということもあり、見ることができる天気であれば大きな月でありましょう。
十五夜と十三夜、両方をお祀りしないと片見月といって縁起が悪いともいわれております。
そんなことを言われても、
(十五夜がお天気が悪くて見られなかった年は十三夜遠愛でてはいけないのか?)とおへその曲がったおばさんはずっと思って過ごしております。
この二夜の月(ふたよのつき)がそろって見られる年は縁起が良いとぐらいにしてくれると、ビビりであるためついつい縁起をかつぎがちなおばさんはこころ安らかに月を見上げることができるのですが…。
仏教では月待ちといい『十五夜』や『十三夜』などにそれぞれ仏さまが当てられていて、十三夜の本尊は【虚空蔵菩薩】さまであるとされます。
虚空蔵菩薩さまは、『十三』という数字に縁があり、毎月の縁日は『13日』、十三夜の月待ちの本尊さまであり、『十三参り』の本尊さま、十三佛信仰では十三番目=三十三回忌のご本尊さまとなり、まさに〝十三づくし〟の仏さまです。
あら?
では今日三十三回忌を迎えた父は十三夜でもあるため、より虚空蔵菩薩さまのご加護があるかしら。
三十三回忌は弔い明けとも言われますが、やはりそういう偶然の重なりには感謝してしまいます。
…でも虚空蔵菩薩さまのご加護が必要なのは、いい加減ボケの進んだ私なのだけれどな。
三十三回忌に寄せて。
三十三回忌というのは人が亡くなってから三十二年目にあたります。
その年に産まれた赤ちゃんが三十二歳となっているということです。
実に偶然のことではありますが、まさにその年に、それも同じ月に息子が生まれています。
私の場合、父母が離婚しており、夫すらが父に会ったことがありません。
仮に父と母が離婚せず、ごく普通に父として、祖父として存在していたならば、たとえ数年であったとしても、いろいろな会話があって、思い出も生まれたことでしょう。
…まぁ、その年に産まれた息子は無理ではありましたが。
でもそれは叶わなかった。
私以外の誰一人、父の顔も知らず、声も知らず、名前すらも知りません(…たぶん)。
そんな三十三回忌。
私は私ども家族だけ集まって、小さくていいので法要を営み、父の三十三回忌をしたかったのです。
檀那寺、父の眠る墓のあるお寺さんがそれを良しとしないならば、そうした法要だけを営んでくださる日光輪王寺がございます。
しかし。
夫は「たしかにおじいさんではある。だけれど、うちの子は誰も会ったこともないのだから、無理に集まってまで法要をすることはない」
と。
それを聞いたとき、私の胸の中に冷たい空気がすぅーっと流れ込んだ気がしました。
あ、そうか。
やっぱりそうなんだ。
三十三回忌。
顔を見たこともない夫の祖父の法要には私も、子どもたちも当たり前に参列しました。
…当たり前だから。
そうか…。
思えば父が亡くなった年、義実家に行った際
「今年は喪中ですので年末年始のご挨拶とかは差し控えます」と言った途端、
「はあぁ?離婚してる父親が亡くなったんだから何にも関係ないだろう。堅苦しいことはいうんじゃない。少なくとも〇〇(=夫)や子どもたちは関係ないから、普通に正月を祝えばいいんだ!」
と義父が言い放ちました。
…夫も一言も反論しなかったんだったな。
…離婚したって、親権がどちらにあったって、父だよ。
父親であることは変わらないんだよ。
子どもにとって…私にとってどんな父親だったかすら知らずに、そんな叩き斬るように断言するのはもう言葉の暴力だよ。
あ、ちゃんと義父にそういった内容のこと、オブラートでくるみはしましたが、啖呵を切りましたよ、私。
…らしいでしょ? 笑。
(続き)
義父に言ったくらいです。
当然、夫にも反論しました。
「顔も知らない祖父であっても、確実に血はつながっている。この法要に参列するしないは子どもたちの決めることで、参列する権利はある」
と。
でも、夫はたった半日であっても、子どもたちの時間をそれに費やさせることを許さなかったのです。
「やると決め、話せば必ず参列する努力をするから、(三十三回忌の法要を)やってもいいけど、子どもたちはやめておいてあげて」
…たしかに。
子どもによっては、土日に休みでない子もおり、そうしたら勤務希望をする必要もあり、時間をかけて地元に戻らなければならない子もおります。
親が離婚した子は、こんな歳になってですら、そんな言われようをされるんだなぁ。
少なくとも夫の〝家〟の考えは、そういったものなのだなぁ。
三十三回忌に当たる日の前日、夫は三連休でありましたが、お墓参りすらしようとは思わなかったようです。
…寂しかったなぁ。
たった一人の三十三回忌のお墓参り。
そしてそれ以上に寂しかったのは、夫がまるで私の心情を理解しようとはしてくれなかったこと。
もう親元を離れて、親と暮らしていた年数の倍以上の時を過ごした夫婦であっても、理解し合えない、理解してもらえないことってまだまだたくさんあるんだなぁ。
ま、他人同士が家族になるんだから、な。
はあぁ…。
父よ、私はあなたが好きだったよ。
よい思い出がたっくさんあるよね。
大切にしてくれた。
今日からはね、貴方は〝先祖〟なんだって。
ご先祖さま、私の子らと孫たちを、これからも守ってね。
【艮神社(尾道市)】
広島県尾道市に鎮座されます【艮(うしとら)神社】さんへお参りさせていただきました。
広島駅から尾道駅まで移動して、そこからバスに乗って千光寺入り口(的な)で下車いたしました。
え“?
…いつもこちらをお読みくださっておられる方々はそう思われたことでしょう。
関東圏でさえろくに移動しない私どもが?と驚かれたことと思います。
これは娘夫婦からのプレゼント旅行でありました。
しかも娘の旦那さまのお母さまが広島市出身ということで、幼い頃はかなりこちらに来ていたという彼が同伴してくれての超豪華旅で。
ええ、奈良にいきたい、京都にいきたいと言いつつも一度も重い腰が上がったことのない二人が、それを超えての広島でございます。
自分たちすらがその現実を受け入れがたく、夢のように思いつつ時を過ごしたのでありました。
この艮神社さん。
千光寺さんという高台にあるお寺さんのお膝元に鎮座なされる神社さんであります。
実は事前には千光寺さんへの参拝は決まっていたものの、艮神社さんは計画にはなかったもの。
地図でみると真横に鎮座されている二つの寺社なのですが、千光寺さん、高台も高台、ロープウェイまである高台ぶりで。
しかもこのロープウェイ乗り場は微妙に艮神社さんよりも手前であり、ああ、この艮神社さんは行かれないのだろうな、と思っていたのです。
しかしながら。
「どうする?ロープウェイで行く?それとも艮神社さんへおまいりしてから?逆でもいいし、ロープウェイが無理そうなら、往復歩きでもいいし。…ロープウェイ、怖いんでしょ?」
と娘。
娘が働きはじめるにあたって始めた一人暮らしのあと、始めたこの神社仏閣珍道中。
そんなに寄り添ってくれてのスケジュールであったとは。
ありがたいことばかりの旅の始まりでありました。
とはいえ…。
娘が離れて暮らすようになってから十年近い年月が流れている。
私がその間に眩暈の持病を持つようになったことも、片方の耳の聞こえに異常をきたしたことも、不整脈のあることも、喘息で定期的に受診し始めたことも何一つ知らない。
知らせずに済むなら知らせたくはない。
ただ、ともに四日間過ごすことで、どれだけのことがバレてしまうだろう。
一日三回内服している薬。
何より眩暈や不整脈、はたまた喘息の大きな発作でも起きてしまえば、知れるところになるどころか迷惑をかけることとなる。
そうならないように祈った。
事前にもたくさんたくさん祈った。
本当は自分のことを祈るのはよくはないと言われるのだが、今回ばかりは祈ることしかできなかった。
どの症状も出ることなく、内服している様子も見られることなく無事に四日間の旅を終えることができた。
帰ってから仏壇もどきに手を合わせ、御礼を申し上げた。
(続き)
…この艮神社さんの手水舎をお護りになられているこの亀。
正しくは玄武(げんぶ)、でありましょうか。
ただ亀は万年とも言われております吉兆の動物でありますから、亀でもあながち間違いではないような気もいたしますが。
玄武であれば四方のうちの北方を守る霊獣であります。
一方【艮】は鬼門、北東の方位・方角、やはり北の方位であります。
しかしながら尾道市の南に位置する艮神社。
尾道市という括りがいつからのものか、かつては備後国、であったでしょうか?
この備後国にしても、山陽道にとっても、この艮神社さん、決して北方に位置してはいません。
何にとっての北?
何にとっての鬼門?
はて?。
ここを北とした時、南にあたるのは、…海くらい?
歴史であるとか、ここを治めた人物とか、国司とか、さぁーっぱりわからない私。
夫に
「ここって何にとっての鬼門なの?」
と聞いてみましたが夫にもわからないとのことで。
ま、まぁわからないこともあるって。
そこで考えることをぱっとあきらめた私。
それにしても。
この亀?玄武?
…ポケモンのカメックスに似てません?
まるでカメックス。
見れば見るほどカメックス。
ま、そんなこと娘の前、娘の旦那さんの前では言えません。
今あらためて写真の画像を拡大して見て、…やっぱりカメックスに似ているよう見える。
私の気のせい…かしら?
カメックス
今朝、食事の支度をしながら付けておくテレビから、
「…人気アニメ「鬼滅の刃」の聖地として知られる神社の屋根の銅板が盗まれた…」
と聞こえてきた。
「えっどこどこ?バチ当たりな!ありえない!」
と夫。
「全国的に多発しているみたいだよ。足利市なんか結構あるみたいで樺崎八幡宮でもあったじゃない」
と、私が言うと同時に流れたのは…。
やはり同じく栃木県足利市に鎮座される【名草厳島神社】さんの見るも無惨な社殿のお姿で、二人は一瞬言葉を呑んだ。
「…栃木県足利市は23日、同市名草上町の厳島神社で、社殿の屋根の銅板が盗まれたと発表した。
市教委文化課によると、盗まれたのは縦15センチ、横56センチの銅板など約1630枚で、被害額は約65万円相当。
棟木部分など外すのが難しい場所以外、屋根全体から銅板がはぎ取られていた。
神社を管理する総代が9月16日、異状がないことを確認しており、その後の犯行とみられる。
この神社は人気アニメ「鬼滅の刃」の聖地として知られる国指定天然記念物『名草の巨石群』の指定地内にあり、社殿は1872年に再建されたもの。
駐車場からは600メートルほど離れているが、参道は途中まで舗装されている。
観光客が3日に気付き、同神社が4日、足利署に被害届を出した。…」
テレビのニュースの放送内容を録音して一部を書き起こしました。
はあぁぁ。
…無人だからな。
樺崎八幡宮さんと同じく、民家はそばにはほとんどないし。
神さまの鎮座されるお社の屋根の上にのぼって、畏れ多くもその屋根に葺かれた銅板を剥ぎ取って盗み去る!
無宗教であっても、〝畏れ〟という感覚は身に染み付いている。
はず。
来週からしばらく毎日雨の予報が続いています。
その間の雨漏りや傷みの進行はどうなのだろう。
とりあえず買い取ることをやめて。
それとも現物のまま外国へ?
私がここで憤慨したところで何も元には戻らず、何も解決はしないのだけれど。
…おばさんは猛烈に怒っています。
(名草厳島神社さんの続き)
『…石段をのぼるのも拝殿が巨石群の上に建てられているから。
巨石群最大の御供石と、巨石の上に建てられた厳島神社。
落ちついた、装飾は一切ない建物が、巨石の上にまるで意志をもって座っておられるかのような┉ここを護ってくださっていることに喜びと誇りを持ってくださっておられるような威厳を持って、そこに鎮座されていました。
周りのいくつかの巨石の肌を静かに静かに、清らかな水がきらめきながら、岩肌を撫でるように流れています。その神々しさといったら┉。
こちらの厳島神社は、伝承によると、平安時代初めの弘仁年間(810年~824年)、空海上人が、水源農耕の守護として弁財天を祀ったのが始まりといわれているようです。白い蛇の道案内により、清水の流れる大きな岩の前に出た上人は、岩の前にすわり、経文を唱えて弁財天を勘請し、前に祠を建てられたといいます。
元禄六(1693)年、このそばにあります金蔵院住職が、領地検分の家老に、弁天宮の再建を願い出て、下附金三両でお舟石上に石宮を建立したのが本宮であるといいます。
明治の神仏分離令により厳島神社となっています。
一番大きな御供石は高さ約11m、周囲約30mといわれています。一見小さく見える上の三角状の笠石ですら、およそ3mもの高さがあります。
こう書けば少しはその大きさが伝わるでしょうか。その御供石の岩の隙間を通り抜けることを「胎内くぐり」と言っているようで、ここを通り抜けると子宝や安産に御利益があると信じられています。…』
2021年の8月にこちらにうかがったときの珍道中錄を一部貼り付けてみました。
直接そこに誘導できるような技を習得していればそれもよかったのですが、どうにもわからない。
そもそもが全文を読み直していただくほどの内容ではなく、一部ですが貼り付けてみます。
初めてこちらを訪れたときの私の感動が少しでも伝わりますでしょうか。
こちらもまた、大好きな、何度でも訪れたい神社さんの一社でありました。
(以前も貼った、鬼滅の刃の聖地とされる所以であろう岩であります)
(名草の厳島神社さんの続き)
足利市で何件も起きている銅葺の屋根等の盗難事件。
これは盗む人間が一番悪いのはもちろんです。
でも現金化できるからこそ、何件も何件も起きるのだと思うのです。
つまりは十中八九、寺社のような特殊な建物から剥がして盗んできたと、一目でわかるものを、しれっと買い取る業者がいる、ということ、です。
その盗人にとっては、恰好の、無人の、銅という現金化できるお宝がつけられた建物に過ぎないのでありましょう。
一方、買い取りの際、買い叩いても、とりあえず現金化さえできれば良しとしている相手から、盗品を買い取って、…そこで加工して転売するのか、そのルートは皆目見当もつきませんが、儲けがあり、足がつかないルートを持っている、ということなのでしょう、こういった盗品を平然と買い取る業者は。
私、神社仏閣珍道中などとふざけたタイトルでずっとずっと文章を書いておりますが、決して信仰というに対してふざけている者ではありません。
ただ、確かに私の場合、そうした神社仏閣から、祈りの場から、離れたところで生活していた人物ではありますが、それを少しでも埋めるべく、神さま、仏さまにお詫びを申し上げながら巡礼しているものであります。
その祈りの場から距離を置いていても、知らないからこその畏れはありましたものの、むしろそこに憧れがあり、だからこその今の寺社巡りなのだと思っております。
そんなにも無宗教になれないのが、人なのだと思うのです。
思うのですが…こうした犯罪、いやあまたの犯罪がおこなわれるということは、そうではない、…ということなのでしょうか。
考えてもわかりません。
わかるくらいならもっと簡単に犯人は捕まることでしょう。
闇バイトという簡単にお金を稼げるという言葉に乗って、人を殺しているのに、「何年くらいで出所できますか?」と接見した弁護士に聞く人間が複数人いるといいます。
罪の意識というものが変化してきてしまっているのでしょうか。
そんな簡単に出所できないと言われて途方に暮れるという〝実行役〟と呼ばれる人たち。
指示に従っただけ、という意識、認識でしかないということ、なのでしょうね。
こうした闇の社会でなくなりますよう、祈ります。
と。
本当は同じ足利市の、明るい話題をお知らせしようとしていたのです。
それは十一月一日から足利市で行われるイベント【足利灯り物語 2024】。
市内の足利学校、鑁阿寺、足利織姫神社、などで繰り広げられる灯りによるイベントで、
[足利学校]
・建造物や庭園をライティング
・あしかがフラワーパークの監修による花手水、和傘、竹灯りのライトアップ
[鑁阿寺]
・国宝鑁阿寺銘仙ラッピング
・推定樹齢550年の大銀杏をライティング
・本堂、一切経堂、多宝塔をライティング
・楼門内に安置される仁王像をライティング
・太鼓橋北側に大型六角銘仙灯りの設置
・参道に銘仙灯りを設置
[足利織姫神社]
・229段ある石段に、色とりどりに変色する銘仙灯りを設置
・社殿をライトアップ
・鳥居両脇に大型六角銘仙灯りの設置
こちらは他の会場よりも長い期間、また長い時間をライトアップされます。
コロナ禍前からあった恒例のイベントで、私どもも一度行ったことがあります。
…あのときはもっと寒かったなぁ。
その幻想的な灯りの織りなす異空間は、心躍り、そして心温まるものでありました。
あ、過去の写真はないです。
あったしても技術も、また機械(ガラケーVSスマホ)の性能が格段に違います。
関心を持たれ、夜のイベントとはなりますがお越しになりたいと思われた方がおられれば。
このイベント、夜からのものでありますのでお帰りは当然夜道となります。
お泊まりも良いかもしれません。
お泊まりは群馬県へどうぞ。
(艮神社(尾道市)さんの続き)
おお、まさかのカメックスで終わり?と思われた方、まことに申し訳ありませんでした。
こちらの神社さんは〝艮〟という方角的な見方をするものなのか否かと、無い頭をひねっていたところに、カメックス、…ではなくて、もしかしたら玄武?と思われる石像に、やはり北を守っている?とさらにさらに首を傾げることとなり、いろいろ調べはじめてしまい筆が止まってしまった次第であります。
で。
まずは原点である、というか真実を伝えるご由緒書きにいこうということにいたしました。
…ええ、(まずはそこからだろう!)、そう思われますよね。
煩悩のかたまりであるおばさんは、最近、一粒で二度美味しいをのぞむところが高じて、ご由緒書きを見る前に妄想、…ではなくて、いろいろ考えてみてからご由緒書きを見るようになっておりまして。
まぁご由緒書きの無い寺社も数多くある故、そうした習慣が生まれてしまったこともあるにはあるのですが。
それでも神社さんを訪れる前には御祭神さまは調べます。
そうでないと失礼にあたると、そうした考えに至ったため、です。
もちろんそれ以外のことを調べて知っていて訪れた方がより深くその神社さんを知ることができ、もしかしたら一生涯で一度の参拝になるかもしれない神社さんなどは殊更そうした方が良いとは思うのですが、同時に先入観も生まれます。
知っていることワクワクする気持ちが減ることも無きにしも非ずで。
そうやって遠回り遠回りして、深く考えたり知ったりすることも楽しかったりすることもあるのです。
…まぁ、知らずに行って見落とすことが多いことがあるのも事実です。
調べて行っても忘れてしまっていることもあるくらいの人物ですし。
調べに調べてうんちくを語りたい人物との二人三脚でもありますし。
ああ、また前置きがこんなにも長くなってしまった (・_・;。
(続き)
こちら【艮神社】さんは大同元(806)年の創建と伝えられ、それはお隣の千光寺さんと同じ年のことであるといいます。
古くは【多氣遠宮】・【建遠神社】と称されたといい、素戔男命さまをお祀りした神社であったといいます。
天延三(976)年に吉備津彦命さまが合祀され、1200年ごろ【幣多賀宮】との二社合祭、となったのだといいます。
のちに火災に遭い、文明七(1475)年、平盛祐が願主となって再建されたといいます。
その後も屋根を葺き替えたり、本殿拝殿を造立したりと、されたとあり、たびたび社殿の造営があったようです。
…おかしい。
艮神社さんのご由緒書きであるというのに、書かれていないのです。
艮神社と称されるようになった年月が。
(続き)
艮神社さんのご由緒書きに、いつから艮神社を名乗るようになったかが記載されていない…。
まぁ、いたしかたないことなのかもしれません。
〝のちに火災に遭い、文明七(1475)年、平盛祐が願主となって再建された〟
と書かれておりますことから、この火災以前の資料全てが焼失してしまったのかもしれません。
特にどこかの鬼門を護るようにも思われないこの艮神社さん。
…。
…もしかしていずこかにご鎮座されます『艮神社』さんを御遷座されている?
それがいつの時代かの資料が神社のみならず鎮座されます尾道のどこにも残されていない、とか?
じつはね。
この尾道艮神社さんの〝艮〟の意味や、いつから艮神社さんと称するようになったかをネットで考察される方は多くおられました。
…それはそうですよね。
私のようにぼやーっとした人間でさえ不思議に思ったことなのですから。
みなさんいろいろ考えておられます。
それを読むのも楽しかったです。
で。
これが今現在私のたどり着いたところ、であります。
その先の、ではいずこの〝艮神社〟さんを遷座されたかとかも調べてはみました。
それは無理でしたね。
…艮神社さんが多すぎて。
全部の艮神社さんを調べて、そこにそうした記述が残されていないか、を調べることなんて、ネットの上でなんか到底無理ですから。
そもそもがきっと尾道の艮神社さんの歴代宮司さまがとうにあたられたことでありましょう。
でもわからないのでこのご由緒書きとなっているのだと思います。
全国には六十七社の【艮神社】があります。
そのうちの六十一社が広島県に鎮座されているという(あ、このカウント私がしましたのであまり当てにはならないかも。ご興味がありましたらカウントし直したほうが良いかもしれません 笑)。
そして各々の艮神社さんでお祀りされる御祭神さまは微妙に異なっておられる。
ということから、いつの時代かに、いずこかの〝艮神社〟さんを遷座されたのではないかという〝私なりの〟考えに至りました。
…曖昧ですけどね。
いやぁ、自分なりに調べて納得いくところでストンと落ちつけるのがいいんです。
先人たちが調べて調べてのこと。
この尾道艮神社さんのご由緒書を作られた方が書いた内容がすごく腑に落ちる。
そこまで自分なりに調べてみたから、いいんです。
それにしても衝撃のニュースです。
…ことしに入ってそんなことが激増しておりますか。
…北海道のニュースです。
最近、彼女ができたと嬉しそうに話していたという被害者。
そのあまりにも残虐な、人を人とも思わない扱いに身震いしたものです。
しかしその犯人を知って心の底から震撼しました。
誰あろう、その彼女と呼ばれた女性の所業だったというのですから。
もうまさに世も末。
昔の世も末と言ったら、飢餓で死者が出るような状況で。そんな中では身包みを剥ぐようなことはあったかもしれないけれど。
いや、そんな簡単に世も末、とか言ってはならないよな。
誰もが苦しいこの時代であっても、道をたがわず歩む人の方が圧倒的に多い。
ほんの一部の人間の所業にそんな思いに至ってはいけない。
だが、やはり怒りと悲しみに身体が震える。
他の一連の闇バイトとか称された、強盗致傷、強盗殺人も。
艮神社さんの左脇を進み、突き当たった場所に連なる路地を『猫の細道』と呼んでいます。
(…この間張り切って書いて消してしまったものは無理なので先に進むことにしました)
猫の細道にお堂がありました。
お地蔵さまがお祀りされています。
苔むしたりはしていないものの、目鼻立ちや衣、手の様子などがよくわからなくなっておられました。
あまりにも白いので、もしかしたら結構強い力で洗浄したりしたのかしら…と思ったくらいでした。
お詣りを終えて道を歩き出そうとすると、何やらポップな、ラミネート加工された貼り紙があります。
…。
えっ?
切り株から出てきたお地蔵さまぁ?
昔ここを開拓したときに切り倒した切り株からでてきたと?
なんでも昭和31年に建物を建てる際切り倒した切り株から出てきたとのことです。
もう少し以前の話なら、伝承かぁと思って通り過ぎるところです。
それでも半信半疑な私。
だめだめ!信じる者は救われる。(…あれ?これはキリスト教?)
それにしても。
木がお地蔵さまを包み込んで生育する…どれだけ気の遠くなるような年月がかかっていることでしょう。
猫の細道というくらいだから猫が多いかとワクワクしておりましたが、さほどはおりません。
むしろ至る所にペイントされた猫が目を引く路地のような細道でした。
小石。
壁。
石段。
福猫石神社なるものもありました。
かなり薄暗くてちょっと私には怖かったです。
神さまをお祀りしている、わけではなさそうで、この細道の至る所に置いてあった猫の顔をペイントした石がたくさん祭ってあるように思われました。
この細道にいる猫さんたちは飼い主さんがいるかもしれないので、写真にはおさめませんでした。
この先を少し行った広場に猫さんが悠々と過ごしていて、しかも人馴れしているので撫でさせてもらいました。
ひとしきり撫でて立ち上がると、娘が
「はいっ」
とお手拭きを手渡してくれました。
い、いやぁ、撫でさせてくれる猫は撫でるってものよ、苦笑。
…いろいろ手のかかる母ですみません。
朔日…とはいっても厳密にいえばあくまでも太陽暦なので、〝おついたち〟、というのがしっくりくるかもしれない。
そんな一日の日。
夫が有給休暇をとっておりました。
月一の坐禅であったり朔日参りであったりと、一人で過ごす時にはそれなりに予定があるにはあるのだが、
「どこかに行こうか」
…甘美な響きでありました。
それでも神社さんにお詣りしたいことは譲らない。
いろいろ候補を挙げあい、日光の東照宮さんへお詣りすることといたしました。
「平日だから大丈夫じゃない?」という夫の言葉はどこまでも否定しつつ…。
日光もまだ紅葉には早かったです。
そして。
夫が言っていた「平日だから」が思いの外的中している道中に、正直驚きつつ、群馬県から栃木県へと入り、日光への一本道へと入っていきました。
でもさすがに駐車場は満車でありました。
…第一駐車場は。
第二駐車場はなんとガラ空き。
こんな日光は初めてです。
(日光山 続き)
日光の輪王寺および東照宮の参道は広く、三車線分くらいはゆうにありますが、そこもがらがら。
…どうした?!
しかも時は秋、本当にどうしたというのでしょう。
まずは輪王寺さんへ。
入場券を買い求めて石段をのぼります。
チケットを見せて入ったところもほとんど人がおりません。今までならここは満員電車のそれくらいに押すな押すな…という方は一人もおられませんが、係員は「もっと奥までお詰めください!」と拡声器を使うくらいで(のちにスマートなピンバッチに変わりましたが)。
がら〜っ。
初めてゆっくりと参拝できそうです。
現在、世界遺産登録二十五周年ということで、初めて御開帳された仏像があります。
…初めて、ですよ?
二年ほど前に数年に一度御開帳される軍荼利明王さまのときは、そのまさに詰め込み日光方式でありました。
もはや不気味なくらいです。
係員の誘導もなければそこで必ず展開されるありがたいグッズの説明と販売もありません。
…ちゃんと今回初の御開帳となった五大明王象鼻の特別グッズも作られておりますし売店で販売もされていました。
どうした?! 日光!
(撮影禁止のため画像はお借りしました)
(続き)
護摩堂を出て。
再び参道に戻ると…!!
…これぞ日光!
すごい人です。
それにしてもこんなにたくさんの人。人。人。
私たちそんなに長く三仏堂と呼ばれる輪王寺さんの御本堂にいたわけではありませんし、護摩堂でもそんなに長い時を過ごしたわけではないはずです。
個人の方々も。
ツアーの方々も。
修学旅行or校外学習の子供たちも。
私どもが三仏堂に入る前に見た光景が夢であったかのように思えてきます。
…今までで一位二位を争う混みようです。
東照宮の鳥居の内はもっと大変なことになっていました。
かつて休日に訪れたとき、くらい?いやそれ以上?
と、とりあえずチケット売り場に並びましょう。
前に並んでおられる方々も、そして後ろに並ばれた方々もみな外国からのお客さまでありました。
異国それも海を隔てた小さな島国である日本を目指して、お金を使い、時間を使って、わざわざお越しになった方々でしょう。
凄いなぁ。
そしてありがたい。
日本の文化に関心を持ってくださって、慣れない土地から土地へ、緻密なスケジュールを組んで、夢見た日本のさまざまな地を目指して。
中には車椅子の方もおられます。
移動はどれだけ大変だったでしょう。
「Excuse me.」
へっ?
後ろの方からお声がかかりました。
「How much なんちゃらticket?」
えっ、えっとぉ〜。
おばさん手で1、6、オー、オーとやってみました。
…わからないようです。
「ワンサウザンド シックスハンドレッド」
とほぼ日本語に聞こえる発音で答えたのは夫。
首をかしげるその方たち。
えっ?通じないの?
「Is this enough ?」
…と言ったのかどうか、女の方が一万円札を手にして首を傾げました。
「オッケー」
しかし。
この先にあるのは自動支払機。
大丈夫かな?
私たちの番が来ました。
なんだか日本人にもわかりにくい仕様です。
なんとか購入に成功しました。
そんな私どもは代わりに購入してあげられるかどうかも自信がなく。
せめてもの親切心で英語表示にしてその場を離れました。
「Nice! Excellent! Thank you.」
…いいえ、英語喋れなくてsorry。
(輪王寺でお授けいただいた切り絵御朱印)
(続き)
入場券を購入する受付は仁王門へと向かう石段の左横。
さあ、いざ東照宮へ!
…コロナ禍もあったのですけれど、それでも日光へは何年か前には参拝しておるのです。
おるのですが、輪王寺と大猷院ばかりで、…東照宮は一体何年ぶりになるのだろう。
しかも日光自体が久しぶりです。
仁王門をくぐると。
人、ひと、ヒト。
仁王門をくぐってすぐに目に入ってくるのは【神庫(じんこ)】。
鉤の手に三棟並んでいます。
いまは入ってすぐの下神庫が修復工事中なようでシートで覆われています。
校倉造りの建物です。
以前お聞きしたところ、お祭りで使う道具、装束や道具などが納められているのだといいます。
以前はそばまで行けなかった…少なくとも私どもはそう思い込んでいたのですが、(今は)すぐそばまで行くことができました。
この上神庫は側面が見ることのできる建て方で、この側面、〝妻〟と呼ばれる部分に細やかな彫り物があるのです。
今まではそばに寄ることが、…できなかったのか、できたけど勘違いしていたのか、まぁよくは見えず、象、かなぁと思っていたにとどまっていたのですが、今回ははっきり〝象っぽい〟ことがわかりました。
何?その象っぽいって?
…そう思われた方もおられましょう。
実はこれ〝象っぽい〟であってるんです。
下に写真を添えておきますが、この彫刻、その名も実に【想像の象】!
東照宮建立時のチーフアートディレクターの『狩野探幽』が、実物の象を知らずに想像で下絵を描いたといい、、まさに想像の象、なので、そのままそう呼ばれているのだそうです。
で。
実は、ですね。
この三神庫、鈎の字だとは言ったのですが、実は中神庫の隣、下神庫のそばににもう一つ建物があるのです。
三神庫と同じ朱色に塗られた建物なのですが、小さく、窓もなく装飾は一切なく、存在自体を憚るかの様な建物なのですが…。
これも以前お聞きしました。
使ってはいないけれど、トイレ、なのだそうです。はばかりだけに…憚るように建てられている?
通路を隔てた上神庫の前あたりに、大きくそびえる『高野槙』があります。
その横が神厩、今回はお馬さんはおられませんでしたが。
その右隣にかの有名な【三猿】を含む猿の彫刻が並びます。
(想像の象)
(続き)
この神厩(しんきゅう)の隣にある高野槙(こうやまき)は三代将軍家光公のお手植えのものといいます。
栃木県の名木の一つです。
神厩にお馬さんは不在でしたが、こちらの神馬は白馬であることが条件とされているといい、たしかに以前見たお馬さんも白かったです。
神厩は実際に使用される厩であるため、漆等を使わない白木のままの建物です。
【三猿】を含む猿の彫刻はどれも見事です。
八面の彫り物からなり、猿の一生を描いているといわれます。
三猿は子猿のころ。
子猿とお母さんから始まって、大人となった猿がお母さんとなるというストーリー、…と言ったらあまりに端折り過ぎていて叱られそうですが、まぁ、そういった内容であることは確かなので。
神に仕える神馬の居室にもこんな彫り物が施されます。
猿である理由があり、昔から
『猿は馬を病気から守る』とされていたからといいます。
この神厩の横に御守や御札などを授与する授与所があります。
主に馬や三猿に由来するものが多いですが、刀剣型の物もありました。
実はここも『国指定の重要文化財』。
かつては警備の役人の詰所、日光奉行が支配していた番所でありました。
三猿は人気で人だかりが絶えず、お馬さんもいないこともあって近寄ることもせず、写真も撮ってありません。
(家光公お手植えの高野槙)
(続き)
手水舎が見えてきます。
いろいろな呼び方があり、こちらは【御水舎】と呼ぶようです。
コロナ禍以降使用が開始されないのでしょうか、それともまた改修工事に入るのでしょうか、紐で周囲を囲っています。
でもそのおかげで、ゆっくりと御水舎を見ることができます。
参詣者が手と口を浄める場所ですらがこれほどに豪華な造りとなっています。
どこをとってもため息が出るほどの美しい装飾です。
実はこうした建物として手水舎を造ったのもこの東照宮が最初といわれています。
ところで。
見えますかね?このレスに載せた写真の屋根の下に龍が彫られているのですが、この龍、翼がある、水を司る『飛龍』と呼ばれる霊獣です。
あまりの混みように、ならば私たちはゆっくりと彫刻や建築物などを堪能して進もうではないかと、ここ御水舎でもかなりの時間をかけて。
もう鳥居はすぐそこ、なのですがね。
やはり日本で初めて造られたという青銅製の、その名も『唐銅鳥居』。
その先に石段があって、上にそびえているのがかの有名な【陽明門】。
結構な頻度で補修修復がなされていて、今はその修復が終えて全景が観られる時であります。
高さもあるので見えないところも多いですし、何より人で見えないんですけどね 笑。
そんな陽明門に目を奪われ、石段をのぼってしまいがちですが、その前にもたっくさん見どころがあるんです。
まずは石段のふもとには、かの伊達政宗公が奉納した【南蛮鉄燈籠】。
…まぁ、鉄なのですっかり錆びてしまっているのですが、ね。
そして。
石段を登り終えたところの手すりの柵にとても変わった石造りの唐獅子さんがいます。
私、この子たちが好きでねぇ。
必ず立ち止まって声をかけてしまうんです。
【飛び越えの獅子】という名前があるようですが、あんまり気づかれていないかも。
何せ人が多いですし、目の前に豪華絢爛な陽明門がそびえたっていますし。
この唐獅子さん、柵の柱に直接彫られた、大変珍しく、しかもこれを彫るのは大変難しいものであろうと思われるものです。
もし日光東照宮に行かれたらぜひぜひこの可愛らしい唐獅子さんたちにも会ってあげてください。
(続き)
唐獅子さんが貼りたくて、ちょっとだけ書きます。
陽明門は何度観ても飽きることがありません。
まさに日暮らしの門。
高いところなどまるで見えないんですけれど、ね。
今はスマホの時代。
そのカメラの性能はかなり優れているため、肉眼で見えづらいものを写し撮ってくれます。
これは本当にありがたい。
まぁ、私などはスマホで最も使うのがカメラ機能、…というよりは他の機能など使ってもいないと言っても過言ではないくらいです。
陽明門といえば、その美しさに一日観ていても飽きないということから日暮らし門とも呼ばれるくらいですが、観れば観るほど、観る回数を重ねるごとにその言葉にうなづくものであります。
ゆえに人だかりが絶えません。
みながその門を見上げて立ち尽くしています。
(大好きな唐獅子さん)
(続き)
石段をのぼった先に鐘楼があります。
この日は右側通行とされていますので、向かって右側、ということになります。
実は私、この鐘に違和感を感じています。
普通見かける鐘楼は高さがあり、土台があって柱がありますが、この鐘楼、地面に直接柱が立っています。
ですので厳密には鐘楼ではないのかもしれません。
鐘撞堂となるのでしょうか。
もう一つは鐘の形。
よくお寺さんで拝見する梵鐘より、〝しゅっ〟とした感じ、シンプルです。
〝乳〟と呼ばれるボツボツとした突起がないようにも見えます。
実はこちらは『朝鮮鐘』と称されるもの。
小ぶりに見えますが、直径は一メートル。
四代将軍家綱公の誕生を祝賀して朝鮮からやってきた通信使が献納した物だといいます。
異国のデザイン、異国からの贈り物であるためでありましたか。
鐘を撞く撞木はありません。
これは…明治の神仏分離令によるものでしょうか。
それとも、?
陽明門から左右に延びる回廊と、石燈篭。
私の中で東照宮の特色の一つに、〝燈篭の多さ〟があげられると思います。
と、申しましても、全国に百社以上はあるという東照宮のうちのほんの、本当にほんの一部しか知りませんが…笑。
日光の東照宮の燈篭の数は実に百二十三基といいます。
のちに写真であげますが、写真の四本の柱、屋根に覆われた八角形の青銅製のものも燈篭だといいます。
現代の世では使われることはないのかもしれませんが、これは回転式、回転するものなのだそう。
ここに灯りが灯されたら、さぞや美しいものでありましょう。
ちなみに。
この燈篭上部に取り付けられた〝葵の紋〟の上下が逆さなのだとか。
外国で造られ、情報に誤りがあってのことなのか、それとも逆さ柱のように意味あってなものなのか…。
それゆえ、『逆紋の廻り燈籠』とも呼ばれているそうです。
この一角は柵があり奥にあることから、私には上手くとらえることができず、写真には撮れてはいないのですが、〝蓮燈籠〟、〝釣燈篭〟
と呼ばれるものもあります。
東照宮内にある案内の立て看板によると、いずれもオランダ国からの奉納品といいます。
(続き)
さあ、いよいよ【陽明門】。
家に帰ってスマホの写真を撮る見直してみて…なんと!全景の写真がありませんでした!
おのぼりさんなので、テンションが上がり頼まれもしないのに夫を入れての写真を撮ってしまっておりました。
型番の古いiPhone、消しゴムマジックも付いておらず。
…基本、映ったものがそのままに写って残る、それで良いと思うというポリシーを持つのではありますが、それでもそれを使いこなしている夫をみると、時に羨ましく思えるときもないわけではないのですが…おっと、閑話休題!
それにしても。
どれだけの彫刻が施されているのか…。
何度見ても感嘆いたします。
徳川家康公が好きかどうかとか、
徳川の支配とか、
これを建てるにあたって、徳川の、あるいは幕府の威信にかけて行われたであろうあれこれとか、
それをどう思うかとかは取っ払って、純粋に凄いと思うのであります。
見上げるだけではよく見えない、小さな小さな彫刻!
スマホで拡大して見ますとそれはそれは細やかに人物が彫られているのです。
文明の利器スマホ様、様であります。
(ちなみにオペラグラスも持ってはいるのですが、こうした聖域で使用するのはやはり多少の抵抗感があって、仮に持っていても使用できずにおりました。
あくまでも鳥を見たくて購入してみたものですし)
ちなみに人物が彫られているのはこちらの陽明門と唐門のみ、だと聞いたことがあります。
緻密で繊細です。
さすが当時の彫り師たちが、必要とする材料を全て惜しむことなく使うことが許された環境下で、己の持つ技のすべてを注ぎ込んだ彫刻たちです。
どれだけいるのかわからないほどの龍たちも、どんな角度から入ろうと見逃さない、かのように様々な角度で存在しておりました。
隣同士阿吽の口であったり。
龍だけではありません。
吉兆の霊獣がたくさん!
この陽明門の扁額の下に
【息】、と呼ばれる霊獣が彫られているのだいいます。
実はこの霊獣、読み方すらが解明されていないほどの幻獣、なのだとか。
…見えませんが、ね 苦笑。
見えないくらいで良いのかもしれません。
幻の霊獣ですから。
さすが、いつまでながめていても飽きない【日暮らしの門】と呼ばれる門であります。
…人混みが苦手なのと、飽きっぽいのと、でそう長くは観ないのが私ですが、ね 笑。
『カリン』
カリンと申しましても、ドラゴンボールのカリンさまではありません。
ポケモンのカリンでもありません。
果実のカリンです。
先日参拝させていただいたお寺さんで、
『ご自由にお待ちください』
と寺務所の入り口に置いてありました。
まぁ、この『ご自由に』という言葉に弱い人物であることも決して否定いたしませんが、カリンということに心惹かれ、一ついただいてまいりました。
実は私、カリンを初めて手にいたしました。
なんと経験の浅い人生でありましょう 苦笑。
初めて手にしたカリンは、大変やわらかな、優しい、そしてなんとも上品な、天界の香りとはかく言うかと思うくらいの香りがいたしました。
おおっ!と思ったのもつかの間、カリンの実、実にベタベタとするではないですか。
うーん(~_~;)
と、そのカリンを持ち帰る人のために、カリンのそばに紙袋をご用意くださっているではないですか。
かくして、初めてカリンをゲットしたおばさん。
この香りを楽しむだけでも良いようです。
しかしながら。
私の生まれて初めてとなった持病であるところの喘息。
カリンというのは咳止めに効果があるという話をお聞きします。
これはなんとか調理して摂取したいものだと思ったのが、いただいてまいりました理由でありました。
もちろん初めて手にした果実ですので、その調理法など知りません。
さっそくネットでカリンの調理法を調べました。
よく聞くかりん酒は、ほとんどアルコールを摂らない私にはあまり適さず、しかももし上手くいって美味しいものが出来たなら、夫にみな飲まれてしまう危険があります。
で、レシピにジャムとかも出てまいりましたので、これならできると煮込みを始めました。
まず皮を剥いて。
…か、硬い!
スっごく硬い!
かぼちゃでこんな硬さのものがありますが、とりあえずはかぼちゃは皮を剥かずにすみます。
当然実も硬い。
…できないけど?
煮込めど煮込めど、とろみなどでません。
(続き)
とろっとすらしてこない、カリン。
お鍋を覗き込んだ夫が、
「おっ、今日はまたずいぶん多くたけのこを煮込んだんだね。細かく切ってあるから混ぜごはんに?」
…とても嬉しそう。
「いや、違う」
「えっ?じゃ何?」
「カリン」
ええ、夫が申しますまさにそのような見た目の〝カリンの煮物〟。
くーっ。
なのでもうこれは思い切って水を増やして、シロップを作ることに変更しよう。
ちょっとクセがあるけれど、飲めないほどではありません。
ん?
んん?
なんだか気道の閉塞感がすごく楽、です。
まぁ、そういう効果があると知ってカリンをいただいてきたくらいだから、思い込み、かもしれません。
ところが。
二度目も。
三度目も。
喘息の、レスキューの吸入薬よりも 早めに効くように感じられます。
これは♡
参拝させていただいたお寺さんのご本尊さまは薬師如来さまではなく、お釈迦さまでございました。
お釈迦さまの御利益でありましょうか。
いずれにしても大変ありがたいものを頂戴いたしました。
(日光東照宮 続き)
陽明門をくぐると。
目の前に唐門と呼ばれる門があるのですが、陽明門の素晴らしさにみな振り返ってその裏から見た姿を見てはまた感嘆の声をあげる方がほとんどであります。
今回、ひとしきり陽明門の内側を見上げたのち、唐門へは向かわず。
かと言って家康公の墓所にも向かわず、祈禱殿から拝殿へと続く下駄箱にも向かうことなく…。
向かったのは、陽明門をくぐってひだりてにあります『神輿舎』でありました。
神輿は〝みこし〟と読まれるのが普通一般ですが、この〝神輿舎〟は〝しんよしゃ〟
と読むようであります。
…などと綴ってはいるものの、現地ではすっかりその正しい読み方を忘れてしまい、「みこししゃ」と呼んでおりましたが 笑。
神輿舎のなかには三基の御神輿が祀られています。
向かって左側の御神輿の前には奉納されたガンダムのプラモデルが置かれていました。
このガンプラ、今年世界遺産登録二十五周年を記念して奉納されたものだといいます。
家康公が関ヶ原の合戦の際に着用したとされる『南蛮胴具足』の色調を基にした色彩で作られ、またその際の兜を着用しているのだとか。
ところで。
夫曰く、こちらの神輿舎の天井に描かれた天女さまは、天女さまの絵では日本一の美しさと言われているのだとか。
日本一美しい天女さまとあらば、美しさとはほど遠い妻を持つ夫としては、是が非でもひとめお目にかかりたいのでありましょう。
ただ…落ち着いて考えますと、たとえ絵であっても天女さまのお姿に順列をつけるなど失礼な話では?と密かに思ってみたり。
そんな夫、神輿舎の前に立ち「見えない」と落胆の声をあげました。
ガンダムのせいか、それともやはり美しい天女さまをひと目見ようと思われてなのか、何やらやたらと人が集っているのです。
それも男性が圧倒的に多い。
自撮り棒とやらを差し込む強者も男性でありました。
こちらは間違いなく天女さまが目的でありましょう。
(続き)
真正面に見て見えなければ少し屈めば良いと、実際にそうしながら夫に伝えて…。
屈んだまま撮影させていただいた天女さまの御姿をあげさせていただきます。
拡大し、少し明るさを調整しておりますが、肉眼で拝する天女さまはこの画像とはまるで異なる美しさでございます。
ちなみに。
このあと、拝見させていただいた天女さまのお美しさを少しでも目に焼き付けたいのか、
…しばらく私から離れて歩いていた夫でありました。 ε-(-。-; )
この神輿舎から御神輿が三基出された状態となるお祭の日。
この天女さまの下で手を打つと、なんと、鳴き龍のように鈴を鳴らすかのような音が聞こえるのだとか。
どこまでも心憎いほどの演出の施された日光東照宮でございました。
(もちろん、この神輿舎には、たとえ神輿が無かろうと一般の参詣者は昇殿することはできません)
(続き)
唐門へ。
陽明門をみたあとであっても、やはりこの門は大変美しく素晴らしいものであります。
それもそのはず。
本社、拝殿・幣殿・本殿の正門であるこの唐門は、拝殿のまさに真正面。
江戸時代においては
『御目見得(おめみえ)』と呼ばれた将軍に拝謁できた大名や家臣のみ使うことが許された門であります。
今でも国賓等の許された参拝者だけしか使えないといいます。
唐門にもまた人物が描かれております。
【舜帝朝見の儀】という題材で一本の欅に彫られているといいます。
それを知って見上げると、その凄さ、素晴らしさに圧倒されます。
拡大してみますと、奥にも人が彫られているのが見えますが、実に四列、二十七人もの人物が一本の欅の幹に彫られているというのだから驚きでしかありません。
唐門の門柱は紫檀や黒檀などで寄せ木細工の『昇(のぼり)竜』と『降り(くだり)竜』が施されています。
迫力が凄いです。
私はこの竜が大好きでいつ来てもしばし立ち止まり見つめております。
この日もしばしこちらの竜を見つめたのち、向かうは【奥社】。
こちらでは奥宮ではなく奥社と呼ぶようです。
奥社は東照宮の御祭神【徳川家康公】の墓所であります。
奥社に向かう門、『坂下門』にかの有名な【眠り猫】があります。
(続き)
奥社へと向かう『坂下門』の下はいつ行っても人だかりが凄いです。
たとえるなら、『福まき』という神社さんやお寺さんで行われるイベントで、撒かれる〝福〟を手に入れたいと集まる方々でしょうか。
眠り猫には特にご利益等は一切ありませんが、有名であること、日光東照宮のシンボルの一つであること、国宝であること、などなどそれぞれの方そこに群がる理由はありましょう。
しかしながら、そんな一切合切の理由より、ただただその彫刻の素晴らしさ、猫のあまりのリアルさ、そして何より可愛らしいことにも寄るところが大きいかもしれません。
写真であらためて見れば見るほど、その素晴らしさにため息がでます。
白黒の猫の、毛の微妙に混ざった感じ、
撫でたら本当にあの猫の毛なのではと思うくらいにふわふわな感じ、
つぶった目の感じ、
鼻のところの輪郭、
顎のところの輪郭、
猫の寝姿のリアルさも
全てがここに表現されています。
初めて見たとき、その小ささにも驚いたものです。
おそらくは実際の猫よりも小さな彫刻です。
この眠り猫の小さな彫刻単体で国宝というのですから驚きです。
それを特にプラ板などで覆ったりしないところが日光らしい潔さです。
眠り猫の裏側には同じくはめ込まれた雀の彫刻があります。
猫も居眠りし、本来なら餌とも言える雀と共存するほどの平和をあらわしている、ともいわれ、それゆえにこの二枚一組の小さな彫刻はまさに平和の象徴であるとされています。
彫刻も間違いなく素晴らしいもの、それは言うまでもありませんが、このキュートでリアルな猫の寝姿に癒されるから、なのではないかしら。
世の中に動物好きさん、猫好きさんが多いから?
…今回は某優秀な(ただし型遅れ)のスマホにより、この眠り猫の拡大した写真を撮影することができました。
ここをくぐって、坂下門を抜けると、…長い長い奥社への参道となります。
(日光東照宮 続き)
日光東照宮【奥社】は、御祭神徳川家康公の墓所。
石段を登りつめた先に拝殿があります。
後の世にこのように世界各地から参詣の方々が訪れることなどは夢にも思わず、
ただ家康公の
「(御自身の)遺体は久能山におさめ、(中略)一周忌が過ぎたならば、日光山に小さな堂を建てて勧請し、神としてまつること。」
との御遺言に従い、死後、朝廷より
【東照大権現】の神号を贈られた家康公をこの地に祀られたものであったものです。
ただ、家康公が望んだ『小さな堂』は、家康公を敬愛する三代将軍家光公によって、いま見るような絢爛豪華なものに生まれ変わっておりますが 笑。
この奥社=家康公の墓所に関する限りは、江戸時代には将軍さましかこちらを参拝することができなかったところですので、拝殿前のアプローチの短さが短くて、今石段の途中必ず渋滞が起こりますが、
お一人のみの参拝ということから考えればごく当たり前、普通のことでありました。
それにしても、この長い石段。
将軍さまにおかれましても、大変なこともあったのですね。
天和三(1683)年に、それまでこの参道に建てられていた石鳥居が唐銅鳥居に建てかえられています。
勅額は、後水尾天皇の直筆といいます。
が。
この鳥居は石段の途中から見上げる形で、こんなところでバランスを崩した日には、石段上で将棋倒しがおこり、大変危険ですので、気をつけて見上げ見るくらいしかできません。
ゆえにこの鳥居の撮影は少なくとも眩暈持ちの私には不可、であります。
鳥居の向こう、右隣に見えるのは『銅神庫』。
宝蔵とも呼ばれ、江戸時代には家康公の位記や宣旨類、甲胄、刀剣など貴重な神宝を収蔵していた建物だといいます。
奥社拝殿へと続く最後の石段脇を護る小さな小さな狛犬さん。
直置き、ではありませんが、ほぼ地面、まるで本当に番犬のように、忠犬のようにたたずむこの狛犬さんが大好きです。
こちらは、
松平右門大夫正綱、
秋元但馬守泰朝、
両氏の寄進によるものだといいます。
このご両名は家康公の御遺臣で、寛永年間の当宮造営の功により、特に奉納を許されたのだと説明にありました。
(続き)
ちょうど長い石段を登ってきて、奥社の拝殿の姿が見えてホッとする場所でもあるからでしょうか。
この神庫のあたりはいつも渋滞が発生しております 笑。
そして。
石段をのぼるとすぐに拝殿前なため、人の多さもありこちらも写真撮影どころではありません 笑。
奥社の、というより日光東照宮で一番の聖域でありましょう、奥社拝殿の裏手から家康公の墓所へと続く青銅製の門、です。
『鋳抜(いぬき)門』と呼ばれます。
なんでもこの門、扉以外の、柱や梁などを一つの鋳型でつくったことからこう呼ばれるのだといいます。
門一つを(扉は別だとしても)一つの鋳型からとは。
驚きます。
こちらの門の内側の、宝塔の内に収められているものこそが家康公の神柩。
建立以来一度も開けられたことはないといいます。
ただし、宝塔自体は当初は木造て、後に石造りとなったものの大地震があって破損したといい、第五代将軍綱吉公が現在の『唐銅製(からかねせい)』に建て替えたといいます。
〝唐銅〟とは、金・銀・銅の合金だといいます。
一際目を引く鶴の像はなんとロウソク立てだといいます。香炉や花瓶とあわせて朝鮮国王からの贈り物だといいます。
おそらく写真に見える唐獅子さんが香炉の蓋に取り付けられているのだと思います。
鶴の足元には…亀、でしょうか。
(続き)
鋳抜(いぬき)門の…腕木とか肘木とかいわれる部位にあたるのかどうか…くるっと大きくカールした三本の何かを口から出している『蜃(しん)』と呼ばれる蜃気楼を産み出す霊獣がいます。
肉眼ではくるっとカールしたものが見えるかどうかというくらい。
距離もあることながら、角度があってなかなか全貌が見えないのです。
それならば写真で…とも思ったのですが、やはりスマホぐらいでは撮ることができませんでした。
…いつかリベンジ…出来るかしら。
距離もあるうえ、何せ腕が致命的に悪いし。
その姿は龍に似ているといいます。
ネットを検索するとそれはそれは美しくて凛々しいのです。
まぁ、蜃気楼自体がなかなか見られるものではありません。
そんなことから蜃はここに配置されているのかもしれません。
ここは聖域中の聖域でもあります。
でもいつかこの〝蜃〟をなんとか自分の手で撮影して見たいもの。
夢は大切です♡
(この〝蜃〟の画像はネットからお借りしております)
(続き)
家康公の墓所であります奥社への参拝の後は、あの唐門の内側、拝殿へ参拝を。
と、その前に。
唐門のわきに連なる透塀(すきべい)の右側に延び、それがちょうど直角に曲がる辺りに、一基の鋳銅製の灯籠があります。
そう、一基だけ、なのです。
あたりを見回して見てももう一対はありません。
通例灯籠は参道の左右に置くものと考え一対で奉納されるのがほとんどです。
この灯籠は東福門院さまが奉納なされたもので、その名も『東福門院の一本灯籠』、最初から一本奉納されたものといいます。
東福門院さまは徳川和子さま。
二代将軍秀忠公の娘で御水尾天皇の中宮であらせられます。
灯籠の、まさに灯りを灯す部分は格子状になっていて、天人の像が取り付けられています。
天人のある部分の上部には五鈷杵のようにも思われる飾りと、また天人の下には丸に桐の桐紋が鋳られています。
笠には如意宝珠、下部には蓮の花びらと、かなり仏教色の強い灯籠であると思われます。
この灯籠と、祈祷殿の間に、拝殿へと続く通路があります。
拝殿へと向かう際は靴を脱ぎ靴箱に納めます。
ここから先は写真撮影は禁止です。
朱塗りされたピカピカ、ツルツルの廊下を歩きます。
靴下越しにひんやりとした冷たさが伝わります。
Lの字に本社の周りを囲うこの回廊は柱も天井裏(梁がみえる天井板のないもの)もみな朱塗りで、とはいえ日の光が射すよう明るい廊下となっており、歩く脇にも見事な彫刻がはめ込まれています。
唐門の内側が拝殿の入り口につながっています。
階段があって。
拝殿の入り口から見えない金色の光の粒が溢れ出てきているような、圧倒されるオーラがあります。
…参詣者も多くてまさに満員電車に乗り込まんとするかといった状態、こちらにも圧倒されます 笑。
通行口は三箇所。
左側は出口専用と指示されます。
人の多さにも圧倒されますが、この入口の豪華なこと、豪華なこと✨✨
これでもかというくらいに金色に光り輝いております。
すし詰め状態の拝殿内。
かつてはここで解説する係員の方がいて、ここで解説を聞いたのち、ありがたい御守のご紹介を賜るのがいつものパターンでありました。
こうした〝ザ・日光〟的な販売方式はやめたのでありましょうか。
(一本灯籠)
栃木県日光市【清滝神社】さん
夫が、日光でずっと行きたいと思っていたところがあると言い、向かったのは『清滝(きよたき)』。
ところが。
彼がナビにセットしたのは『清滝(きよたき)神社』さん。
その滝をお守りくださる 神さま、神社さんをお詣りするところから始めるなんて、自分の夫ながら、すごく良いこと。
良い心がけだなぁと内心感心しつつ…。
…ただその神社さんを見逃して通り過ぎてしまうところも、さすがわが夫 笑。
Uターンして。
Uターンしたおかげで、反対車線を走行中には気付けなかった駐車場の存在もわかり、もしかしたら、この神社さんにおられる神さまのお導きでありましたでしょうか。
規模こそさほど大きくはありませんが、広い境内がそれはそれはきれいに掃き清められ、大変あたたかで優しい気に満ちた、居心地のよい神社さんでありました。
御神木、でありましょうか。
大きな大きなイチョウの木です。
手水舎があります。
少し変わった手水鉢です。
すぐそばを小さな小さな、川というのもはばかられる水の流れがあります。
これは…。
とても心の癒やされる、そして心落ちつく境内であります。
朱色に花青 青銅色の美しい拝殿です。
古伝によれば。
弘仁十一(820)年 弘法大師空海が来晃し、滝尾・寂光・生岡等と共に当社を創建した。
社名は、社殿背後のお滝を含めた地形が、中国大鷲山の清滝に似ているところから命名されたという。
往時は、二荒山登拝の要路として、又、密宗修験の霊場として大いに栄えた。
お滝の御神水は、古来生命保全の霊水として広く信仰されており、又社前の池は、応永十二(1406) 鎌倉管領の追討を受けた 常陸国小栗城主小栗判官満重を恋慕する美女照手姫が判官の無事息災祈願の際に洗顔したところから〝照手姫の化粧池〟と伝えている。
御祭神は、大海津見神さま
配神は、高龗神さま
二荒山三神さま
(大己貴命さま・田心姫命さま・味耜高彦根命さま)
八坂神さま
稲荷神さま
特殊神事 古式 湯立神事
とありました。
まずは、何をおいてもお詣りです。
社殿のすぐ前を護られる狛犬さま。
大きさは小さめながら、迫力ある眼光と美しい肢体です。
すっかり魅了され、しばし周りをウロウロと♡
ん?
社殿の横に立て札が…。
清滝の滝とあります。
(続き)
小さな小さな、でもその水は大変美しく、そして趣きのある池がありました。
…照手姫さまの化粧池、でしょうか。
前レスで書かせていただいている
『…鎌倉管領の追討を受けた 常陸国小栗城主小栗判官満重を恋慕する美女照手姫が判官の無事息災祈願の際に洗顔したところから〝照手姫の化粧池…』
のこと。
もしやご利益で若返ったり、美しくなれたり、…しなかったのは、車に戻って見たバイザー裏のミラーですぐにわかりました 苦笑。
そもそもがそのようなご利益があるなどとは一ミリも書いてはありません。
ただの私の願望でありました。
落ち葉と、何の囲いもない池のほとりであることとから、ズルっと足を取られそうなところを歩いて。
御本殿の傍を拝しながら。
小高い山?
あ。
た、滝だっ!
こんな社殿のすぐそばに…。
なんとありがたくも神々しい光景でありましょう。
しばし滝を見上げて。
かつて空海上人がここを訪れ、この滝を見上げ、清滝、と名付けたことに思いを馳せ。
…なるほど。
『清滝』は『清滝神社』さんの内にありましたか。
それはナビに清滝神社さんをセットするはずです。
清らかな滝からの流れを追うように歩いてまいりました。
美しい水です。
流れのゆるやかなところでは、まさに鏡のように、木々や青い空を映しています。
そんな豊かなものを心にお授けいただいて…。
もう一度、社殿にご挨拶にまいりますと、お書き置きの御朱印が柱に掛けてあることに気づきました。
社名の記されたものと、
見開きで筆で描かれた龍の絵のあるものと。
手書きの龍がとてもかわいらしくて、迷わず見開きの絵入りのものにいたしました。
そおっと。
破れたり折れたりしないように。
あれ?
次に出てきた龍の絵は、私が手にしたものと全く異なったものです。
うわあぁ✨。
すっかり嬉しくなった私。
宮司さまの心こもった、一枚一枚思いを込めてくださった素敵な、素晴らしいおもてなしでありました。
宮司さまの心こもった、一枚一枚図柄の異なる龍の絵の描かれた御朱印。
一枚一枚が手書きであることから、この御朱印の画には著作権があるものと考え、こちらにあげることは控えておくことにいたしますが、この龍の絵、墨でスッと迷うことなく筆を走らせて描き、色もおつけになられたものです。
そんななんとも心のこもったおもてなしを受けて、後ろ髪を引かれる思いで車に戻ります。
あ、そうそう、お隣に小さなお堂があったので、行ってみなくては。
【清龍寺(せいりゅうじ)跡】と書かれています。
お寺さんがあったんだぁ…。
たしかに。
清龍神社さんは弘法大師さまが訪れて建立された神社さんでありました。
その横にお寺さんがあったとて、なんの不思議もありません。
【清龍寺跡(清龍権現別当勝福山金剛成就院清滝寺)】
弘仁十一(820)年、沙門空海上人(弘法大師)により創立。
その後円仁(慈覚大師)によって天台宗に改宗した日光山満願寺(今の輪王寺)別院として、蜜門灌頂の道場であった。
お堂の前に設置された案内板に書かれています。
このあと。
夫がナビに入力し向かったのは…。
『清龍(せいりゅう)寺』さんでありました。
栃木県日光市【清龍寺】さん
栃木県日光市の【清滝(せいりゅう)寺】さんへ参拝させていただきました。
少し細くなった急なカーブの道を曲がった先を少し行くと、すぐにお寺さんが見え、お寺さんの門前を通り過ぎるとすぐに駐車場がありました。
清龍寺さんの前のお宅の方が、きびきびと洗車をされておられました。
動きに無駄がなく、車のお好きな方なのだろうなと好ましく思いながらそばを通りますと、目があい、お互いにご挨拶したその後に、
「お寺にご用ですか」
とおっしゃられました。
お若いのにコミュ力のおありになる方だなぁと感心しながら
「はい。清龍寺さんはこちらから入るのでよろしいのでしょうかね」
こちらでは曲がってすぐのお寺さんであるためなのか、丁寧に案内の立て札が二箇所ありました。
「ええ、どちらからでもお入りになれます」
とその好青年がおっしゃるのを聞き、
お礼を申し上げて、すぐそばにある手前の入り口から入らせていただきました。
…あれ?
庫裏?
しかしながら。
近年一見一般的な家屋に見える御本堂があります。
ここは慎重に見極めましょう。
「…奥、かしらね?もう一つの入り口から入るのが正しかったかな」
そんなことをブツブツと話していると、先ほどのお若い方が作業の手を止められて、やって来られました。
「何かご用がありますか?」
え。
もしかしてお寺の?
まさに洗車用のコーディネートに身を固めておられ、ましてやお寺の敷地内でもなかったため、お寺の関係の方とは思いもせず。
それにしても作業の手を止めてまでお越しくださるとはありがたい。
「お参りさせていただきにまいりました。
それと。
もし御朱印をお授けなさっておられるなら、お授けいただきたいのですが…」
「ああ、大丈夫です。ただ少し時間をいただきますが大丈夫でしょうか?」
…ん?
この話し方…。
この話の展開…。
もしかしてお坊さんで?
内心びっくりする私どもを庫裏へと招き入れてくださいました。
広くて綺麗に整った玄関です。
と、そこには…
(続き)
前レスの可愛らしい画像は
しょうぐうさん❣️
天台宗のマスコットキャラクターです。
『一隅を照らす』からの
〝照隅〟さん、なのだと思います。
かの総本山である比叡山でのイベントではこのしょうぐうさん(の着ぐるみ)が境内を歩くこともあるといいます。
一度で良いので歩くしょうぐうさんにお会いしたいものであります。
あれ?
…て、天台宗?
たしか空海さんが開かれたお寺さんなのでは…。
ま、まぁ、長い歴史の中宗派が変わることはままあるようです。
ましてやここ日光にあっては、輪王寺さん、殊、天海上人の影響もありましょう。
それはさておき。
この〝しょうぐうさん〟のぬいぐるみさんにお会いできたのも初めてのことでありました。
…可愛くないですか♡
しかも小さな木彫りの火鉢や鉄瓶、茶器、なんてセンスの良い♡
と、しょうぐうさんで騒いでおりますが、このときお参りがまだでございます。
洗車のお手をとめて、御朱印帳への墨書きをしてくださるということで、先に庫裏へとお邪魔しておりました。
庫裏から境内を通って。
途中、池がありました。
池の向こうにお不動さまがおられます。
手水舎があります。
美しい水が絶えずあふれ出ています。
湧き水、でしょうか。
そして御本堂。
赤いお堂です。
格子にはめられたガラスに、深まりゆく秋が映ります。
この清滝寺さんはかつて明治の廃仏毀釈により廃寺となったといいます。
現在清滝寺さんが建つ場所にはかつては『円通寺』(=長興山福聚院円通寺。明治四年廃寺)さんが建っていたということです。
こちらのご本尊【千手観世音菩薩】さまは、『日光山中禅寺』のご本尊の末木で彫られたものと伝わり、(距離としてはだいぶ離れてはいますが)中禅寺の前立ち本尊の役割を担っていたといいます。
男体山に建つ中禅寺はかつては女人禁制であったため、この清滝寺は女性の参拝者のための札所として栄えたといいます。
しかし、明治時代となり廃仏毀釈の動きを受けて、円通寺さんと共に廃寺となります。
それを明治四十二年、足尾銅山採掘に本格的に着手した『古河電工』さんが、足尾への進出という大きな力を得、町も潤い、復興し、この清滝寺さんの再興とあいなったようです。
その際清滝寺さんを円通寺さん跡に建て、合併再興としたようです。
(続き)
御本堂のわきに苔むした石仏さまが並んでおられます。
苔でもとのお姿がわからなくなっています。
青々としたお髪とお召し物のように苔が…。
ちょっと可愛らしくてクスッと笑った瞬間、
…失われた手に気づいて言葉を失いました。
それでも微笑んでくださる石仏さま。
御本堂わきのつきあたりにおられた御仏さま。
遠くから見るとまるで内陣におられるご本尊さまのようであります。
ワクワクして近づくと…。
やはり痛々しい傷跡が。
思わず声が出ました。
…そうでした。
こちらはあの維新で廃寺とされたほどのお寺さんでありました。
苔がまるで人間の愚かな過去を静かに覆い隠してくれているかのようにも思えます。
御仏が意思をもって、あえて苔をお召しになられたかにも思えてしまい、切なく、そしてありがたく…。
…愚かでごめんなさい。
こちらのお寺の御詠歌は
『おおいなる 仏の御手のちからにて 濁る心も澄む清滝』
とのこと。
より深い言葉のように思えて、心にささります。
(続き)
御本堂の横から再び御本堂の前へ。
おや?
…舟?
舟に乗る御仏、でしょうか。
前にまわってみますと、なるほど舟に乗られた如意輪観音さまてありました。
水の豊かな地であります。
石工さんの遊び心、でしょうか?
それとも有事の時、如意輪観音さまが舟で移動なされるように?
その前には美しく並ばれた六地蔵さま。
一体だけ少し大きく彫られたのでしょうか?
視線を少しまわしてみますと何やらお堂があります…というよりは覆屋ですね。
額が掲げてあります。
『しらみ地蔵』さま。
…し、しらみぃー?
まさかのしらみ。
まさかあのしらみでしょうか?
紹介文の書かれた案内板があります。
『日光市指定有形文化財
石造地蔵菩薩坐像
年記銘から天正年間(1573~1591)に製作されたことがわかり、この時期の日光における石仏研究の貴重な資料である。
像容は近世の坐像と比較し、肩が極端になで肩となっている。袈裟の文様線は単純で、首部の襟ぐりが深い。像の厚みもあり量感あふれるが、全体的に簡素である。
かつては清滝神社付近の路傍に祀られていたと伝えられ、この前で浮浪者がひなたぼっこをしながらシラミ取りをしていたといい、そのことから『しらみ地蔵』と呼ばれている。
平成18年3月3日指定
日光市教育委員会』
えっ…。
そ、そんな命名?
なんだかとてもバチ当たりな気がするのは私だけでしょうか。
ひなたぼっこをし、虱を取るのが、長閑な光景、といえば光景でもあり…。
虱を取るのを見守るお地蔵さまが、イヤなものをとり除くのを見守り、それをとり除けるようお力を貸してくださるというご利益へとつながったようです。
うーん。
…空が白んでくる、とかじゃなくて、虱?
ちなみに。
このしらみ地蔵菩薩さまは関東百八地蔵尊霊場の四十九札所のお地蔵さまとなります。
入り口に大きな石塔がありました。
【坂東十八番】
…坂東三十三観音霊場のこと?
…こちらは違うはずですが。
坂東三十三観音霊場の十八番札所は…、
あ、なるほど、…中禅寺です。
こちらはかつて中禅寺の前立ち的なお寺さんでありました。
中禅寺さんに詣でたくとも許されない、女性たちが、せめて思いは中禅寺へと馳せることができるようにと、このような石塔を建てたのでしょうか。
栃木県足利市【薬師寺】さん
しばらく前となりますが栃木県足利市にあります【薬師寺】さんへ参拝させていただきました。
初めてのお寺さんです。
山門の前に立つと、
一瞬立ち止まって見返す斬新なデザインの御本堂がお出迎えくださいました。
昭和の時代建てられた鉄筋コンクリート製の御本堂には、往々にして既存のお寺さんの建物の概念を覆すものをみることがあります。
一礼し境内に足を踏み入れると、ひだりてにある昔ながらのお堂に何やら人が集まっています。
実はこの日こちらの普段は非公開の薬師如来さまが公開していただけるとのことでありました。
足利市の文化財公開日でもあったのですが、来年春、修復のためしばらくこちらのお寺に不在となることもあって、この日から申し出をすれば拝観させていただけることとされたようです。
逸る気持ちを抑えて、抑えて…。
まずは御本堂へと向かい、ご本尊さまにご挨拶を申し上げます。
御本堂の戸も開けてくださっておられ、ご本尊さまに直接お目通しいただくことができました。
ありがたいことです。
その後、焦る気持ちを抑えて、走らず、薬師堂と思われるお堂へと向かいます。
こちらの薬師堂は昔ながらの木造のお堂であります。
薬師堂は思った以上に人が集まっていました。
そんな人と人の隙間から、見えないお薬師さまに手を合わせます。
隙間から見える僧の座られる座の彫物もすばらしい!
どうしても下の方しか見えないので、目にはいったのは畳。
畳敷きのお堂は今は珍しい気がいたしました。
しかも新しい、まだ緑の残る畳です。
護摩壇が組まれています。
御護摩が焚かれるということですと殊更畳敷きは珍しいかもしれません。
そしておばさんは少しずつ更なる人と人の隙間を探して移動するのでありました。
あ。
立派な御厨子の中にお薬師さまのお姿が見えました。
柔らかな眼差しと、お姿を拝した瞬間、包み込んで護ってくださるようなお力を感じるお薬師さまがそこにおられました。
そしてさらには。
一見、昔の家庭によく見られた部屋の二辺を使って祀った神棚を思わせるような棚があり、そこにはお像がたくさん祭られている、…ように見えました。
中で説明をしてくださる方がおられるのが見えました。
作務衣姿であられます。
ご住職さまでありましょうか。
(続き)
説明を聞かれる何人かの方はスリッパを履いてお堂の内におられます。
私があまりにも覗き込んで説明を聞いているのが目についたのでしょう、
「スリッパの数は足りませんでしたが、一応掃き掃除もしてありますので、よろしければどうぞ中へお入りください」
とお声がけくださいました。
…子どもたちと一緒だったら顔を顰められ、のちに叱られるところです。
しかしこの日は夫と二人✌︎
こうした時、長年の経験から、なのでしょう、決して行動を共にはしていない夫です。
あくまでも他人事、なのでしょうね。
すでに呆れ果て諦めているのでしょう。
…ん?
そういえば、買い物などでも決してそばにはいません。
というか、思えば若いころからそうだったかも…。
まぁ、どうでもよいことです。
周りの、やはり遠巻きに見るしかなかった方々は大変喜んでおられました。 …ケガの功名、でしょうか。
さらには
「せっかくですからもっとそばでご覧ください」とおっしゃるご住職さま。
えっ✨
人々の列が恐る恐る前へと動きます。
「どうぞもっとそばで」
とご住職。
な、なんと御厨子の前までをお許しくださったのです。
…言葉にはなりません。
藤原末期から鎌倉初期の作であろうかと推察されるといいます。
許されるならずっとお堂の中にいたい、そんな幸せな気分です。
お寺さんとしてはお許しくださるのですが、このイベントに連れてきてくれた夫は、この後もあちこちを廻る計画を立ててくれております。
去り難い思いを抱きつつ…。
説明を終えられご住職さまは今度は御朱印への対応にまわられるとのこと。
お手を煩わせてばかりで全く申し訳ないことではありますが、御朱印をお授けいただくべく客殿兼庫裏へと向かう私。
夫は…どこでしょう。
神社さんやお寺さんを参拝しても、参拝後の探索は全く別行動をとる二人であります。
この距離感が良いのですが、時々山深い無住のお寺さんなどでは心細くなります。
あまりに戻らないと、…もしや神隠しに…などと思ってしまう。
ええ、そんなとき聞こえる鴉の鳴き声や、風のわたる音のなんとも効果的なことといったら ( ; ; )。
しかしながら、そうかといって行動を共にすることはない、あくまでもマイペースな二人でありました。
(続き)
こちら、足利市の川崎薬師寺さんの御本堂は昭和四十年に再建されたもの、といいます。
河川の洪水対策で移転となったためといいます。
江戸時代に建てられたという御本堂の移築は難しいものだったのでありましょうか。
諸事情はありましょうし、移築は移築で大変な手間もお金もかかるものでありましょう。
どんなお堂であったのでしょう。
鉄筋コンクリート製の御本堂はやはり寂しくもあり、変わったデザインで建てられていると私は少しだけ哀しくも思えるのです。
ただ今後の管理を考えると、たとえばあのお寺の甍の傷んだ時など、費用の面でずいぶんと変わってくるものでありましょう。
古き良きものだけにこだわっていく時代はこうして変わりゆくものとなるのかもしれません。
こちらのです御本尊さまは延命地蔵さま。
左手に宝珠、右手に錫杖を持たれ、左足を下げ半跏坐をとられていました。
江戸時代のものと伝わるといいます。
御内陣向かって右にお祀りされておられる弘法大師さまは特に
【廿日大師】と呼ばれる御像のようです。
はて。
廿日大師という表現を初めて目にいたしました。
こちらは真言宗豊山派のお寺さん。
御像を拝して五鈷杵をお持ちなことから弘法大師さまであることは間違いなさそうです。
とすると廿日ということになにかありそうです。
調べたところ、ヒットするのは高野山の別格本山 清浄心院というお寺さんばかりでありました。
こちらのお寺さんの記述を拝見させていただきましたところ…
『承和二(835)年三月二十日。
弘法大師・空海さまはご入定される前日に、自らの像を彫刻され、「微雲管(みうんかん)」の3字を木像の後ろに刻まれました。
この像は「廿日(はつか)大師」と称され、今も私たちの幸せを願ってくださっております』
とありました。
併せてこちら薬師寺さんでいただいた資料を読ませていただいたところ、こちらの第三十二代のご住職さまが夢でこの高野山清浄心院さんに祀られる廿日大師さまの御姿をみたことにただならぬ縁を感じ、高野山に戻り、この像を作られたとのこと。
こちらの廿日大師さまの御肩にも『微雲管』と刻まれているとのことでありました。
通常お見かけする弘法大師さまの御像よりもほっそりとお痩せになられているのもそういった御像であることからでありましたか…。
(続き)
栃木県足利市に建つ川崎薬師寺さんは、お若いご住職さまに、新しそうなお寺さんですが、実は建久元(1190)年に創建されたお寺さんだといいます。
もとは天台宗のお寺さんであったものがおそらく江戸の時代に改宗されたようだとお話しされていました。
古くから伝わる伝統を大切にしつつ、新しい風を取り入れていこうとされるお姿に頭が下がります。
このたび拝観させていただきましたお薬師さまは来年以降修繕事業を控えられているとのことです。
江戸時代に補修された部分の塗膜を剥離させ、欠損部分の再建も行い、平安時代のお姿を取り戻す修繕となるとのことでありました。
ちなみに。
このお薬師さまは通常は非公開なだけで、秘仏ではないとのこと。
真の秘仏の御仏は小さな御厨子に納められたお薬師さまと伝わるとおっしゃっておられました。
ご住職さまにおかれましては、大変丁寧なご説明をいただきありがとうございました。
栃木県足利市の川崎薬師寺さんをあとにし、次の目的地に向かおうとナビを使っての移動をしました。
しばらく走行すると『阿弥陀堂』とナビの画面に出てまいりました。
これはぜひお詣りさせていただきましょう。
ところが。
ナビの示すところには古い集会所のような建物が。
…たしかに、地元でもかつてお寺さんであったところが集会所になっている、などという話を聞いたことがあります。
ただ、こちらはそもそもが元お寺さんであった建物とは思えない…。
強いていうならば、…庵?
しかも今使われているようには思えない。
ただ、その建物の敷地内には何体かの石仏さまがおられました。
そのうちの一体はお美しい如意輪観音さま。
この如意輪観音さまだけ屋根だけではありますが覆屋がありました。
阿弥陀さまではありません。
帰宅後この阿弥陀堂について調べてみました。
すると。
な、なんと!
こちらの阿弥陀堂の御本尊であられる【木造 阿弥陀如来立像】さまを、私、つい先ほどまで拝観させていただいていたということがわかったのです。
実は。
先ほどまで参拝させていただいていた栃木県足利市の川崎薬師寺さんの御本堂の御内陣、御本尊の延命地蔵さまの向かって左側に祀られていた両手を無惨にも無くされ、表面の塗りも剥げて黒ずんだ像高三十から三十五センチといったどなたかも分からない立像が祀られていたのです。
この御仏こそが、こちらのこの阿弥陀堂の御本尊さまであるというのです。
昭和のカスリーン台風の洪水で損傷を受けられたといいます。
いま残る阿弥陀堂もそうであったのでしょうか。
薬師寺さんの御内陣にそっとお祀りされた、お手を失われた御仏の御像、それがなんとも痛々しくて、心に残ったものでありました。
薬師寺さんと阿弥陀堂は同じ川崎町ではあるようですが、少し距離が離れております。
今、阿弥陀さまは薬師寺さんにおられますが、今日も薬師寺さん界隈から阿弥陀堂の辺り、広く川崎町を、そして川崎町にお住まいの方々を、お手を失われたお姿のままお護りくださっておられるのかと思うと本当にありがたく思われます。
いつかこの阿弥陀如来さまも修復される日が来るとよいなと、あらためて思うのでありました。
【足利市西場の百番観音さま】
足利市の西場というところ。
こちらには石仏さまがたくさんおられるといいます。
うかがう前からワクワクいたします。
しかもこちらに向かう前にも思いもよらない阿弥陀堂で石仏さまにお逢いすることができました。
西場の小さな山の山裾にたくさんの石造物の並ぶなか、
一際目を引く『勢至菩薩』さま。
『二十三夜さま』であります。
なんとお美しいことでしょう。
お優しいお顔だちです。
衣の流れるようなさまといい、
天衣と呼ばれる肩のところの薄布のフワッと浮いた感じといい、
なんと素晴らしい彫りでありましょう。
御手は軽く組まれておられますでしょうか?
蓮座の彫りも、
その下の台に彫られた菊の花弁の細かなこととかも本当に本当に素晴らしい。
堂宇や覆屋もなく、風雨に晒されてなおこの美しさを保ってくださっております。
寛政八(1796)年の作のようです。
奇跡のようです。
願主はかつてここにあったという『勧行寺』さんの阿闍梨『円海』さま、とあります。
この地に百観音を勧請したという僧侶であります。
ところで。
二十三夜講の御本尊さまであられる勢至菩薩さまではありますが、お寺の御本堂で独尊でお祀りされることは稀であります。
観音さまと対になり、阿弥陀如来さまの脇侍、阿弥陀如来三尊像としてお祀りされることがほとんどです。
いつものようにぽわぁとこの勢至菩薩さまにしばし見とれて立ち尽くし。
そして去り難い思いを振り切るかのようにいま一度合掌して…。
(続き)
この石造物の並ぶ道端の上、小高いところに、百観音さまがお祀りされております。
少しのぼると、広い空間が広がっていました。
そして御堂がぽつん。
中には大日如来さまがお祀りされていました。
ここはかつてあったお寺の跡。
そのお寺さんでお祀りされていた御仏でありましょうか。
『勧行寺跡と百番観音』
創建、廃寺の時期はいずれも明確でないが、本寺(寿◯山(? 白いテープに〝寿〟の一文字だけが書かれたものが貼り付けてあります)勧行寺)は、格式のある修行寺として隆盛をきわめたが、今はお行様(おぎょうさま)と伝えられている。
寛政年間大阿闍梨円海和尚が、西国、坂東、秩父の百番観音を勧進する偉業をなし遂げ、完全な形で百体の石仏が保存され、往時の民衆の厚い信仰を物語る貴重な文化財である。 西場町文化財保存会』
廃寺となった時期すらがわからないほどの時を経ているとのこと、もはや私には当時の様子を推察することは叶いませんでした。
寂しい空間です。
廃寺跡、ということもあってのことでしょうか。
きれいに整備はされているのです。
そしてここには、この地点にはまだ一体の石仏さまもおられませんでした。
(続き)
その後、思ったよりも登った先に、…三列に整然とお並びになられた観音さまがおられました。
そのお姿は同じ大きさで統一されており、たくさんの尊像が並ばれる様子が目に入った瞬間、まだ斜面にいながら思わず手を合わせたくらいに、神々しい光景でありました。
【西場の百観音】
勧行寺(廃寺)跡に石造の観世音菩薩像が百体、南面して三段に整然と並んでいる。
これは、西国三十三箇所、坂東三十三箇所、秩父三十四箇所の各霊場の観世音菩薩像を勧請して、造立されたものである。
造立時期は記年銘から寛政二(1790)から同十年にわたるものと推定される。
一部に若干の損壊が見られるが全体的に保存も良く百体整然と立ち並ぶ状態は偉観であり、西国・坂東・秩父の霊場巡礼の功徳を分かち合おうとした勧行寺僧侶の布教姿勢と、それに呼応した村人の信仰の姿を知る上で貴重な資料である。
…足利市教育委員会
…前回のレスと分かれてしまったのでお気づきになられるのはむずかしくなってしまい申し訳なく思いましたが、
前回のレスでは『百番観音』
そして今回のレスでは『百観音』と、それぞれ異なる表記がなされているのです。
これはおっちょこちょいでガサツな私の写し間違いではなく、書いた先、この案内板を設置したところがそれぞれ異なっている事に由来したものであるのです。
前レスのものは『西場町文化財保存会』さまが、
今回ご紹介しているものは『足利市教育委員会』が設置したもの。
当然書き手が異なって、そこに込められたものに違いがあってのこの違いになっているのだなと私はある種の感動をすら覚えました。
前者は自分たちの住まう地域の先人が、…おそらくその中にはご自分の祖先に当たる方が奉納されたという方が多くおられる、そんな方々の中のお一人が書かれたもので、後者は市の文化財課の方が学術的なご意見と地元の方々のお話を元に、あるいはその専門の方が書かれたもの、という事です。
かつてご住職さまが発案された観音さまの造立に深く感銘された、ご先祖さまが、もしかしたら苦しい生活の中にあっても、どうしてもここに観音さまを奉納したいと思われた方々がここを誇りに思って書かれたものと、貴重な歴史的資料、文化財と思って書かれたものはこうした違いを生じるものなのだなぁ…この一字の違いが私にはそう思えました。
(続き)
おおっ✨
御手。
御手ひとつを見てもなんとしなやかで美しい御指✨
合掌なさるために自然に曲げた手首の美しさ。
まったく力みのない御仏の肩のラインの美しいことといったら。
衣から見える素の御御足。
なんと尊くて、そしてお美しいことでしょう。
(何回美しいと…笑)
彫られた石工の方が何人かいるよう思われます。
お顔にその違いがみられます。
同じ大きさに切り出された石があって、
同じ形、大きさの舟形光背という取り決めをした上で、
百ヶ寺観音霊場のそれぞれの観音さまを石工たちが彫ったのであろうと思います。
…おそらくは石工同士がそれぞれ自らの腕の限りを注ぎ、その上で腕を競うといったこともあったのではないかと私は思います。
どの観音さまも、すべて美しいお姿をされておられます。
彩色の跡が残るものもありました。
この観音さまが建立され一同に並んださまはさぞ神々しいものであったことでありましょう。
奉納された方々の思いが伝わってまいります。
また…、何度でも行きたいと思う、百番観音さまでありました。
ここに載せる一枚をどれだけ時間をかけて選んだことか…
【庚申】
昨日は今年最後の庚申の日でありました。
この庚申の日の過ごし方で、道教と日本の仏教、さらには地域の言い伝え等と結びついたものから前日からご近所の方々と集って眠らずに過ごすという慣習があり、それを庚申講と呼んだようです。
庚申の日は六十日に一度。
江戸時代には全国各地でかなり盛んにこの庚申講が開かれていたようです。
この庚申講を三年間続けた証として【庚申塔】を建てるという慣習もあり、庚申講がいかに盛んであったかを物語るように【庚申】と書かれた塔や石造物を見かけます。
ただこの庚申という考えもまた、あの明治政府によって否定されたものであり、この頃多くの庚申塔が撤去・処分されてしまったようです。
💢
また庚申の年、というものもあります。
これは六十年に一度巡りくるものとなります。
この庚申の年にもまた、庚申講とは関わりなく庚申塔を建てたようで、庚申塔を建てられた年をみるとなるほど庚申の年であるものが多く見受けられます。
今年、栃木県にある有名な庚申塔を訪ねました。
お寺の中、庚申堂を建てて祀った大変に立派なものでありました。
これが庚申の年に建てられたものでありました。
昨日の庚申の日に、そのことを夫に話していたら、
「は?ちなみに何年に建てられた?」
どういうことか少し不機嫌そうに…。
「寛政十二、…年だったかな」
と私が申しますと
「ああ、それなら正しいな」
はっ?
疑った?
夫は庚申の年にも庚申塔が建てられることは知っていたようで、しかもこの寛政年間に多くの庚申塔が建てられていることも知っていたようです。
が、この栃木県の庚申塔が庚申の年に建てられたということはどうやら知らなかったよう。
二人で行ったので、おそらく彼は建立年を見落としたのでしょう。
はあぁ。
歴オタのプライドを傷つけました?
まぁ、そうした自分を許せない気持ちもあるのでしょうが、それにしてももう少し言い方があろうと思うのですが、ね。
なんで素直に情報を共有できないのでしょう。
モヤモヤするなぁ。
と怒る私もまた未熟者。
…未熟者同士なのだから素直に補い合って生きたら良いのになぁ。
栃木県足利市【正善寺】さん
神社を参拝させていただきますときは、基本的には、神さまに失礼のないよう事前に御祭神を知って伺わせていただくようにしてはおります。
とはいえ、たとえば天満宮とあれば御祭神は天神さま、管原道眞公とわかりますので、出先でふと見かけて
(あ、〇〇さまだ)
とお詣りさせていただくことも多々ございますが。
お寺さんに関してはなんらそういった下調べなく、それこそ門前で(ああ、こちらは〇〇宗のお寺さんなのか)と、はじめて宗派を知って、参拝させていただくことも多くあります。
こちらも足利市の企画で今回文化財公開をされるお寺さんということで、御由緒も宗派も存じあげないまま、文化財公開にあたって紹介されている情報だけで参拝させていただいたのでありました。
こちらの文化財は御仏像の
【木造阿弥陀如来坐像】。
それともう一つ、その名も
【正善寺古墳】。
こちらはどうやら古墳に関係するお寺さんであるようです。
御本堂の前、向かって左側に伝教大師さまの御像がございました。
こちらは天台宗のお寺さんのようです。
…そうなんですよね、必ずしも宗派をうたった標柱や表札があるとは限らないので、こういったヒントを得られればまだしも、実のところ宗派がわからないまま参拝を終えることもあるにはあるのです。
まぁ、それはあまり気にしてはいないのです。
お坊さんにすれば中には心外に思われる方もおられましょうが、もとを辿ればお釈迦さまのお教えですから。
山門の真ん前、御本堂の戸は大きく開かれ、その入り口を一目見ただけでお寺さんが、そして御本尊さまが心から歓迎してくださっておられるのが伝わってくる、…そんな思いのするお寺さんでありました。
たとえるなら、金色の、あたたかなオーラ…そんな雰囲気を感じたお寺さんの御本堂前であります。
その戸口に立った瞬間、やわらかな、それでいて凛とした雰囲気の作務衣をお召しの女の方から、
「どうぞお入りください」
とお声がけいただきました。
身体をこちらに向けて、大きく手を御本堂の中へと招き入れるようなしぐさをされて、まさにこれ以上ないフレンドリーなお招きです。
靴を脱ぎしずしずと一歩。
…次の瞬間、目の前におられます御本尊さまに目を奪われ、思わず小さく声が出てしまったくらいの衝撃を受けました。
(続き)
そこには暖かくおだやかな光に包まれた阿弥陀如来さまがおられたのです。
お姿を前にしてすぐに、もう自然に身体がそうすることが当たり前とばかりにそこに正座し、手をついて頭を深く下げる私がおりました。
そして。
頭を上げた私の目の前には香炉がありました。
「お線香をあげさせていただいてよろしいでしょうか」
先ほどの作務衣の女性に声をかけさせていただきました。
すぐに女性は快くそこにあるろうそくに火を灯してくださいました。
大変良い香りのお線香でありました。
あらためて阿弥陀如来さまのお姿を拝します。
なんとおだやかなお姿でありましょう。
なんとおだやかな癒しの空間でありましょう。
それにしても大きい。
大きな御像です。
入った瞬間には丈六?と思ったくらいです。
ですがよくよくみるとそれほど大きくはありません。
のちに見た資料によると像高九十七センチ、とあります。
ただ、それはおそらくは阿弥陀如来さまのお座りになられた御姿の像のみの高さでありましょう。
光背も大きく、その高さはあきらかに坐像の像高を超えています。
台座は…どうかしら。
私の感覚では台座すらも含まない、まさに阿弥陀如来さまだけで九十七センチあるように思えます。
ただ、いつも申し上げております通り、私、こうした目測の能力が皆無な人間で。
まぁ、そのあたりは置いておいていただいて、かなり大きな坐像なのだなぁと思ってやっていただければ間違いありません。
あれ?、お顔に何か?
表面の剥落、剥離でありましょうか、まるで瘡蓋のように見えます。
…それが痛々しく思えたのは私一人でありますでしょうか。
左右には向かって右に千手観音さま。
左には馬頭観音さま。
…あれ?
この三尊って…。
天台宗のお寺さんですし、もしかしたら?
「日光の輪王寺さんと同じ御本尊さまですね」
と私が申し上げますと、先ほどの女性の方が
「あら、お気づきになられたのですね。それはそれは」
とそれは嬉しそうにおっしゃいました。
あの大きくて金色に光り輝く輪王寺さんの三仏堂の仏さまと同じでありますから。
あのインパクトは一度拝すれば忘れません、…って私、もう何度参拝させていただいたことか。 笑。
配置もまさに日光の三仏堂と同じであります。
(続き)
大きく金色に光り輝く輪王寺さんの三仏堂の仏さまと同じ配列、実はこれは特殊な配列形式で、この三仏、三尊を共に祀ることはあまり無い…はず、なのです。
何故ならばこの三尊は日光の山々であるとされているからこその配列だから。
三仏堂と異なるとすれば、千手観音さまと馬頭観音さまは阿弥陀さまとだいぶ大きさが異なりますこと。
なによりおそらくは制作された年代もだいぶ後年になるのではないかと思われるいかにも新しい仏さまです。
と、まさに絶妙なタイミングで静かに、作務衣の女性が語り始めました。
「実はあの廃仏毀釈で仏さまが集められることとなり、あちこちからかなりの数の仏像が集められたようなのです。
そしていざその仏像を戻しても良いとなったとき、戻せなくなってしまった仏像が結構な数あったのです。
この阿弥陀如来さまは日光の輪王寺さんのものであったのですが、やはり戻せなくなったとのことで、行き場を無くしておられるというのです。
そんな話がこの寺に持ち込まれたのは父の代のことなのですが、その時「これはぜひ我が寺にお迎えせねば」と、
ありったけのお金をかき集めてお迎え申し上げたのですよ」
と笑いながらおっしゃったのです。
なんてチャーミングな語り口でありましょう♡
そんなお話をひとしきりお聞きして。
(続き)
御朱印をお願いいたしましたところ、そのまま女性は御朱印帳を手に御本堂の脇間にあった文机に向かわれ、墨書を始められました。
…もしかしてもしかすると、この女性こそがご住職さま?
私、失礼は無かったかしら。
あ。
夫はこちらで思いっきり失礼をしたんです。
御内陣まで入ることまでお許しくださり、
失礼が無いよう失礼の無きよう、御簾に頭をぶつけたりしないように、気をつけて、気をつけて…。
上にばかり気をつけて、御内陣のほんの少し高くなっている段差に気づかず(本当は昇っているので、正しくは忘れて)、
すっ転んだんです。
ええ、御本堂の中で。
隣で大きな異音がすると同時に、真横に並べられていた椅子が倒れて、そこに夫の足があるびっくりといったら!
一瞬何が起きたものかまるでわかりませんでした。
理解するまでちょっと時間を要したくらい。
でもお寺の調度や椅子を傷付けることなく、本人も(痛みはあったでしょうが)無事で、これぞまさに阿弥陀如来さまのお力のおかげ、千手観音さまの御手の救い、馬頭観音さまの功徳でありましょう。
(続き)
足利市の正善寺さん。
正しくは
【明星山 神楽院 正善寺】。
延享二(1745)年
尊影権大僧都により御本堂建立。
このとき御本尊は釈迦如来さまであり、釈迦如来立像が祀られていた。
昭和五十一(1976)年
日光輪王寺より定朝様式の【阿弥陀如来坐像】を譲り受け、新しく御本尊として安置。
正善寺の阿弥陀如来は、昭和51年に日光山輪王寺より勧請(かんじょう)された仏様です。身の丈約1メートル、当時奈良博物館の館長をされていた石田茂作氏に鑑定していただいた書簡によると、製作は鎌倉中期とされ、日本で最初の仏師とされる定朝様式(じょうちょうようしき)の阿弥陀如来とされています。
一番の特徴はその「肉髷(にくけい)」で、通常如来像の肉髷は頭上のやや前にみえるかたちであるのがほとんどです。正善寺のご本尊の肉髷は頭頂に置かれていて、その相は国内でも珍しいとされています。また光背も放射状に描かれており、弥陀来迎図にあるそのままの姿を表しています。
昭和五十三(1978)年
鐘楼堂落慶。
鋳匠は人間国宝香取正彦氏の弟子で、足利の鴇田力氏。
銅は『戦艦陸奥』に使われていたもの。
昭和五十六(1981)年
日光山より『弁財天』を勧請。
正善寺古墳の石室に奉安。
お寺が前方後円墳の上に建てられてあり、石室から観音像が出土されています。
(正善寺さんのHPより)
えっ?
戦艦陸奥の鐘?
…知りませんでした。
気づきませんでしたぁ(;ω;)
亡き父といい、夫といい、息子といい、実はわが家は戦艦好きが多く。
血筋というには父と夫は血の繋がりは全くないので、…日本男児の血、とでもいうのでしょうかね。(鐘、だけに。…なんでもありません)
過去にはその鐘を拝するべく何寺ほど訪ね歩いた人たちなのです。
そんな浪漫を一ミリも理解しない妻であり母である私は、鐘になんの違いがあろうかとどこか冷ややかにそんな父と息子を見ていたのもたしか、…なのですが。
でもお寺の御由緒をしっかりと学んでこの地を訪れたならば、夫だけでもそうした目でこの梵鐘を見ることができたものを…、そう思うと何やら夫に申し訳ないような気すらしてまいります。
(続き)
お寺さんのことはあまり調べることなく参拝し
神社さんは最低でも御祭神、ことに主祭神さまは調べられる限り調べてから参詣する
それはこの珍道中を歩きながら、いつしか作ったマイルール。
お寺さんをないがしろにしているわけなど毛頭ありません。
神さまに失礼なきようと思ってのことからではあります。
それはひとえにビビりだから、でもありました。
御仏は救いと諌めと、何より見守ってくださる存在であるとの、またまた私の勝手な思い込みもあり、そうした存在のもとへ訪れ、日ごろの悪しき行いや考えをお詫び申し上げ、都度身を正す機会を与えていただき、
そして日頃の感謝を申し上げる存在としてとらえているので、どの御仏にもそうした考えのもと訪れるので良いかと思うようなりました。
…なにより。
ときめきも欲しい 笑。
あまりにも詳細に書かれたものを読んでしまうと、出逢いの煌めきが少しくすんでしまう気がして、
神社さんは最低でも主祭神さま、
お寺さんは宗派すら知らぬままに
参詣させていただいております。
まぁ、行ってから今回のように
(ああ、もう少し調べてから来れば…)
と思うことも多々ありますが、その愚かさも私らしいことで。
そうして来年もまた変わらぬ珍道中を続けるのであります。
閑話休題。
話を正善寺さんへと戻しましょう。
なるほど。
こちらは一目でわかるくらいに古墳の上に墓地があります。
その墓地の麓を、円墳の周りを、不動明王さまと童子さんたちが護っておられます。
十二支の守り童子さんでもあるようです。
私の守り童子さんは…
秘密です 笑。
この墓地のそばに鳥居がありました。
弁天宮、とあります。
下っています。
…下り宮?
(続き)
正善寺さんの弁財天さまのお宮は鳥居をくぐってゆるやかな下り坂。
その先は岩屋のようになっていました。
と、夫が意味ありげに
「俺一人でお詣りさせていただいてくるよ、…無理なんでしょう?」
えっ?
お詣りさせていただきますけど?
くだっていった先は狭いです。
暗いです。
本当はろうそくをあげてお詣りさせていただくよう書いてありましたが、ろうそくがありませんでした。
お参りして、戻ります。
ん?
んんっ?!
この感じ…。
…せ、石室じゃないですかぁぁ。
そ、そうかぁ。
あの夫の意味ありげな物言いは、暗にここが石室であることを伝えていたということでありましたかぁ。
私、古墳も一個人のお墓と考え(いや、事実そうですが)、石室は神聖な場所。
ありていに言えば…怖いんです、私。
歴史好きで考古学研究会とかに所属していた夫とたまに古墳を訪ねても石室には近づこうとすらしなかったのです。…怖いから。
は、はっきり言ってよ、もう(;ω;)
というか位置関係から気づきましょうよ、私。
…お寺さんも墓地には極力近寄らない私。
神さまへの失礼も畏れますが、
死者への冒涜も怖れます。
でも畏れという考え方、感じ方は
人として生きる上でとても大切な感覚だと私は思っております。
ま、ただ私の場合、ビビりであることをも大きいのですが、ね 笑。
みなさまにおかれましては
良いお年をお迎えのことと存じます。
喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただいております。
それでも
全ての生きとし生けるものの上、
平等に陽は昇ります。
そんなことにもあらためての感謝をし、過ごした一日でありました。
風の強い夜が一転、年が変わるくらいに風がなぎ、
あたたかで穏やかな日となった奇跡に神仏のお力を感じ。
昨年一生涯忘れることのできない
元旦となったことに
あらためて自然の脅威を思い
追悼し
復興を祈りました。
そんな
いつもの年とは違う新年を迎える
前の晩に、息子が大切そうに一つの箱を手に帰省してまいりました。
お重でありました。
心遣いに感謝し、
そうした心遣いのできる生き方をしてくれ今に至る彼の生き方に心から感謝した一日でありました。
栃木県足利市【徳蔵寺】さん
栃木県足利市の徳蔵寺さんはピンポン寺を名乗られるお寺さん。
なんのピンポンかといえばあの卓球のピンポンのこと。境内にはなんと卓球場があるといいます。
お寺さんを紹介する記事などをみると、なんと御朱印帳も卓球、もといピンポンをする動物が描かれているものが紹介されています。
…にぎやかな雰囲気のお寺さんなのかしら…?
どちらかといえば、神社仏閣には、日頃の喧騒から逃れるべく静かな、癒しの空間を求める私。
正直なかなか足が向かずにおりました。
そんな徳蔵寺さんが昨年秋の栃木県足利市の文化財公開の対象となっておりました。
これは良い機会なのかもしれません。
ナビの案内で到着した徳蔵寺さんは、駐車場に車が入れられないほどの混雑ぶりです。
それでも、なんだかおもしろいように、出る車と入る車が、まるで相談でもしたかのようにうまいことまわります。
山門をくぐろうとすると…何やら聞こえていますが…?
センサーで人が通ると女の方が歌う仏教の歌?が流れるように設定してあるようです。
いきなり低く小さな歌声が聴こえてくるのは正直かなり怖かったです。
(やっぱり合わないお寺さんかしら…?)
内心そう思ったのは隠しようない事実です。
そして山門をくぐると、
異国風の御本堂。
白い玉砂利の敷かれた境内には橋があったり、
等身大よりやや小さめくらいの羅漢さまたちの石像が、まるで陽だまりで談笑でもしているかのように配置されていたり。
檀家さんだけでない、来る人すべての目を楽しませたいと考えておられるであろう、こちらのお寺さんの姿勢が門をくぐっただけで伝わってきます。
その境内、今回の文化財公開に合わせていく人もの案内人の方がおられました。
マンツーマンでの案内をと考えてくださっておられるようで、すぐにスッと私たち夫婦一人一人に案内の方が近づいてきてくださいました。
「あ、一緒なので」
とお一方にはお断りして。
まずは五百の羅漢さまがおられることで有名な『五百羅漢堂』へとまいりました。
…本来ならばいつものようにまずは御本堂からお詣りしたいのですが、この日はいたしかたありません。
(続き)
石造りの羅漢さまたちが語らう玉砂利の敷かれた場。
その奥に建てられているのが五百羅漢さまのお堂です。
普段は閉ざされているという扉は開け放たれておりました。
もっとも申し出れば普段のときでも扉を開けてくださるとのことでした。
近づくにつれて少しづつその様子がわかってまいります。
おおっ!
こ、これは!!
これは凄い!
思わず息をのみました。
ピラミッド型の大きなひな壇が、狭い御堂の中央に設置されています。
というかほぼその段でいっぱいです。
壇の最上段には阿弥陀如来さま、でしょうか。
脇侍の菩薩さまがその前に立たれます。
こういったときの百であるとか五百というのは、『とても多くの』といった意味合いでありますので、百とあっても必ず百はおられないこともありますくらいです。
長い年月の間に失われてしまうこともありましょう。
ですがこの五百羅漢さまの像は五百を超えるといいます。
ただただ圧倒されます。
しかしながら羅漢さま好きの私。
ハッと我に戻って、出来うる限りその一体一体の羅漢さまを拝見したいとあらためて見上げました。
木造の、まさに大きい雛人形くらいの羅漢さまが、それぞれの異なった表情、異なった思い思いの姿勢で刻まれ並べられています。
うーん♡
ん?
他の羅漢さまのお像ではいかにも人間臭く、怒っておられたり、居眠りしておられたりするのですが、こちらの五百羅漢さまの像は、そのほとんどが祈っておられたり、黙想されたりされるお姿が多いような…。
よくよく拝見いたしますと、やはり抱き合っておられたり、まどろんでおられたり、にこぉ〜っと笑っておられたりする羅漢さまもおられるのですが、大多数の像が静かに椅子に座っておられるのです。
いかにも人間臭く、…まぁ羅漢さまたちはあくまでも人間なので、人間臭いどころではないのですが、ね、…怒ったり、泣いたり、居眠りしたりという羅漢さまに親近感を抱く私といたしましては、ちょっと残念だったりも…。
とはいえ本来の羅漢さま、正確には阿羅漢さまというのは、『もはやなんら修行のいらない存在』
なのだそうですから、そうした泣いたり怒ったりする羅漢さまの方が本来は特殊なのだとは思うのです、がね。
この感情を一言で言い表わすならば、…寂しい?
(続き)
足利市の徳蔵寺さんの五百羅漢さま。
いろいろなお顔、いろいろな表情、いろいろなポーズの羅漢さんがおられます。
ユーモラスで可愛らしい、と撮らせていただいた羅漢さま、あらためてよく見たらお手が欠損されていました。
保存状態が良いとはいえ、やはり年数の経つ木彫の御像、淋しいけれどそんなこともありましょうか。
ピラミッド状の段に五百体。
お雛様とは異なりずっと数百年このまま祀られているのでしょうね。
煤払いくらいはするにしても、一体一体をおろしてお掃除とかしようものなら…戻す場所かわからなくなりそうです。
えっ?
そんなのは私だけ?
お堂に対してほぼいっぱいの台、羅漢さまをおろそうにも堂内にはスペースはありませんし、ね。
上の方の羅漢さまをおろそうにも、上の方は当然奥まっておりますから、脚立をかけてもお降ろしするのは難しそうです。
続いて。
お隣にあります千庚申の塔が収められている覆屋へと向かいました。
(続き)
千庚申堂。
千庚申塔の覆屋です。
とはいえ千基庚申塔、もしくは青面金剛さまが祀られているわけではありません。
初めての参拝、初めて拝観させていただいておりますがこれが実に凄い!
庚申塔を彫るにあたって必要な要素全てを彫り込み刻んだかのような立派な塔が一基、祀られているのです。
彫りの見事なこと、見事なこと!
そしてさらには保存状態が大変良い。
大きく
『千庚申』
と彫られた文字のほかに、文字が彫られているのですが
庚申 庚申 庚申…
と
ひたすら〝庚申〟とのみ彫られているのです。
〝竿石〟というので良いのですかね、この石の部分全てに
〝庚申〟とただひたすらに彫られており、これがなんと千字あるのだといいます。
千字〝庚申〟と彫られているので〝千庚申〟。
一字一字が丁寧に丁寧に彫られています。
気が遠くなるような気がいたします。
そんな中、一部朱が入れられています。
これにはどんな意味かがあるのでしょう。
墓石の裏面の建立者の名が赤いのはその方が生きておられる証であるといいますが、この千庚申には当てはまらない。
…もしかして。
…あくまでも私のひらめきに似た推測でしかありませんが、こうして置くことで験を担いだとか?
この、一部に朱を入れることで、この千庚申の石塔はまだ未完成であると。
完成したあとは崩壊していくという世の常を憂いての…。
そう、あの日光東照宮にみられる逆さ柱のような。
まぁ、私、こうした石造物とかにも全く造詣がございませんので、あくまでもそうした考えに至っただけで、なんの根拠もありません。
あくまでもど素人のひらめきに過ぎません。
(続き)
青面金剛さまの彫られた石柱は笠を逆さにしたような台座(…と呼ぶのでよいのでしょうかね?)に乗るように祀られています。
この部分にも何やら模様が彫られていますが、雲を表現したもの…なのかもしれません。
その下には梵字が、やはり四面ともに彫られています。
青面金剛さまの彫られたメインの面には、青面金剛さまの両脇に立つ人物も描かれています。
青面金剛さまに仕える童子さんでありましょうか?
また、青面金剛さまのおられる竿石(この呼び方が正しいかもよくわかりませんが)の両側面には二体ずつ計四体の鬼神が彫られています。
スペースの関係もありましょうし、技術ある石工への支払い金額も嵩むといった現実的な問題もありましょう、そこまで彫られている青面金剛像を今まで拝したことがありません。
塔の正面一番下には三猿と二羽の鶏か彫られています。
この三猿の可愛らしいことといったら♡
しかも鳥の羽、お猿さんの毛の流れまでリアルに丁寧に彫られています。
この、正面以外の面には何が彫られていたかというと、この塔のいわれ。
細かな文字がぎっしりと彫られ、中には人名と思しきものも含まれておりました。
徳蔵寺さんのHPを拝見いたしますと、銘文を写されたものが載っていました。
高さ262cm.
銘 寛政12年庚申12月
記述文:浅草寺別当代法印権大僧都淵海。
銘の概要
塔の建立者 長 真勝という人である。
(徳蔵寺さんのHPより)
なんでもこの長真勝さんという方は、足利市の廻船問屋さんであったようです。
足利市というのは川の多い街。
かつては廻船問屋さんがあって、この町の繁栄を大きく担っていたのですね。
…ちなみに。
〝かいせんどんや〟と入力しましたら『海鮮丼屋』となりました 笑。
そして銘文に出てくるようにこの塔は『庚申の年』に造立されたもので、庚申塔、ことに青面金剛さまの彫られたものは〝庚申〟の年に当たっているものが大変多いです。
それにしても、262センチ!
この細かな彫りといい、千字の庚申の文字といい他に例を見ないと思われます。
それは言い換えると足利という街の繁栄ぶりと、この廻船問屋さんの繁栄ぶりがよくわかるものであるということに他ならない、です。
私信。
昨夜 九州四国で津波を伴う地震が発生いたしましたこと、被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
お邪魔させていただいておりました方のスレッドにも九州の方がおられるため、お見舞いを申し上げにうかがったところ、ほぼクローズ状態となっており、レスすることが出来ず、このようなおばさんの独り言のスレをお読みではないかとは存じてはおりますが、せめてこちらからご無事でありますようお祈りし、お見舞い申し上げます。
またお若いスレ主さんにおかれましても、何かあったのか大変心配しておりますが、こんな時、何事かがあっても連絡の取りようがないのがネット上でのお付き合いであるのだないと、歯痒く、そして寂しく思うのでありました。
スレ主さまのご無事をお祈りしております。
本来私のような年配の者がお邪魔させていただいているのもおかしいくらいのスレでありましたので、再開されても今後はお話させていただくのも控えたいと思います。
長いことお世話になり本当にありがとうございました。
昨日は暦のうえでは、〝大寒〟、一年で一番寒いころといわれる日でありましたが、群馬県は大変暖かい春を思わせる一日でありました。
そんな暖かさに、桐生市の菱町まで出かけてみました。
あ あじさいの山寺 普門寺
だるま市
菱町カルタの看板のある【普門寺】さんです。
あじさいのお寺さん、なのですかね。
時期が異なるのもあって特に紫陽花の木と思しきものは見当たりませんでした。
山寺とあるだけあって石段の先に仁王門が見えます。
仁王門をくぐると石仏さまがお出迎えくださいます。
仁王門の裏側には、大きく傷付いた石仏さまたちがひっそりと並んで祀られていました。
気づかない方は気づかない、そんなお祀りの仕方は、そのあまりにも傷付いたお姿に驚かれる方に配慮したものと私には思われました。
傷付いた石仏さまも大切にお祀りくださるお寺さんにいたく感動し心より感謝いたしました。
さらに進んでいくと…。
やはり明らかに台座と石碑が異なるものがありました。
台座の三猿さんのお姿から、かつてはもしかしたら青面金剛さまがおられたものとも考えられます。
もしそうならば、この三猿の見事さといい、保存状態の良さといいとても立派な青面金剛さまであったかもしれません。
あくまでも私の妄想にすぎませんが、これもまた諸行無常ということでありましょう。
石段の長さから、でありましょうか、結構な人数が休める休憩所がありました。
休まず進みます。
みぎてに六地蔵さまがお祀りされておりました。
文政四年、とあります。
驚くほど状態の良い石仏さまでありました。
傷付いた石仏さまも大切にされるお寺さん、御仏のご加護があるのでしょうか。
さて先へ。
…!!
な、なんと!
道が二手に分かれています!
はて、いったいどちらへ?
道標はありません。
困って石段二つを眺めてみますと、少しカーブした石段の先にある建物が御本堂を思わせる屋根であります。
こちら、で行ってみましょう。
間違っていたらごめんなさい、と内心。
まあ、そんなことでお怒りになられる御仏はおられないでしょう。
(続き)
普門寺さんの参道のまさかの参道の道別れ。
でも選んだ石段を登っていった先には御本堂、道選び、正解!
しかもちょうどたどり着いたとき、ほんの少しだけ御本堂の戸が開いており、きざはしの下からご本尊さまのお姿を拝することができました。
ありがたい。
御本堂前には大きくてそれはそれは立派な香炉がありました。
どれだけの龍が彫られているのかわからないくらい細やかな彫りの施された石の香炉でありました。
ひだりてに目をやると道元禅師さまが道を示されています。
その横にゆるやかな石段があり、な、なんと!
石段の左脇には石造の十八羅漢様がおられるではないですか♡
しかもこの石像撫でていいそうです。
…さわりたい。
でも石も手にある油分で変質することを知って、むやみには触らないことにしております。
それにもう一宇の御堂が気になります。
『保輪華』という扁額が掲げられています。
どういった意味でしょう?
そもそもどなたがお祀りされておられるのでしょう。
うーん。
ちょうどそこへバイクに乗った方が。
郵便屋さん?
いやいやそうではありません。
作務衣をお召しのようです。
お声がけさせていただき、お話を伺ったところ、な、なんと!
衝撃の事実が発覚いたします。
実は昨日がこちらのダルマ市で、なんとこちらのお堂の扉も開けられたというのです。
ダルマ市に合わせて年一回のご開帳が行われた、というのです。
そ、そ、そんなあ
(続き)
『保輪華』
輪華とは仏教で万物を生成する要素のこととありました。
それを保つ、ということ…?
うーん、もしかしたらどなたか仏さまの別称だったりするのでしょうか?
検索をかけてもなかなかhitしません。
輪華についても、なんと命名のためのサイトでようやく得た情報であります。
桐生仏教会が発行された、
平成の合併以前の桐生市内のお寺さんの紹介された小冊子があり(いま、こちらはネットでも見ることができます)、
それを見てみますと、
御本堂のご本尊さまは聖観音さま、
あともう一体、
観音堂に祀られる十一面観音さまがおられる、とのことであります。
こちらのお堂にお祀りされている御仏が十一面観音さまであることはわかりました。
では十一面観音さまの別称?
…しかしながらそれもまた、素人の検索では調べることができませんでした。
昨日の参拝がちょうどお昼どきに当たってしまい、お聞きするのは失礼なタイミングとなってしまい、そのまま帰宅してしまいました。
ところで。
もう一つこちらのお堂にかかる木札に、なんとも興味深いものを見つけました。
それは
『坂東 足利 第八番札所 無畏山 普門寺』となっているもの。
こちら桐生市の菱町はかつては栃木県でありました。
その頃からの札所であったということなのでありましょう。
足利坂東三十三観音霊場を調べてみたところ、七番札所は毎月のお護摩に参列させていただいている鶏足寺さんでありました。
他の札所はそのほとんどが足利市にあるお寺さんで他の二ヶ寺が佐野市。
令和三年に足利仏教会が発足した足利三十三観音霊場とはまた別の観音霊場があったのですね。
坂東足利観音霊場の第一番札所はいまは無住となってしまった『浄因寺』さんがあたっておりました。
次に鶏足寺さんへ伺った時にお聞きしてみたいと思います。
昭和となって県を跨いでの合併は、以前調べたところ、全国でも大変珍しいケースで十件ほどであったと記憶しております。
そのうちの二件が群馬県桐生市への合併であったと知って大変驚いたものです。
生活圏としての利便性からの合併であったようですが、いままでの長い歴史もあること、
いろいろ複雑な思いもあったかと思います。
そんな名残りをみた気がした、足利の札所である事実でありました。
脚下照顧。
脚下は足もと。
照顧は反省して一つ一つを確かめる。振り返ってよく考える。
もとは禅の言葉である。
ああ言っても、こう言っても、決して自分の脱いだ靴を揃えておくことができない夫。
毎日毎日、明日仕事に向かう夫のために靴を揃えながら思いだす人がいる。
>嫌なことがあったら笑い飛ばせ。
>「なんだ、こんなこと」と。
>笑えないって?
>それなら俺の顔を思い出せ。
かつてそう言っていたミクルで出会った方だ。
いつも整った部屋に住み、靴はいつも揃えてあった。
〝わすれていいから〟は絵本のタイトルでしかないので、忘れたりしません。
忘れることはありません。
忘れるとしたら…それは私が認知症になったときでしょう。
もうじき誕生日ですね。
良い年にするんだよ。
貴方自身の手で。
まるっきりステージの異なる仕事は大変。
それは痛いほど知っている。
けれど貴方の肩にかかる愛しい存在がその大変さを乗り越える原動力。
がんばれ。
【もう一つの】
群馬県桐生市のお寺さんで…今は御朱印で有名なお寺さんに、大々的に【日限地蔵】をうたう観音院さんというお寺さんがあります。
もともと桐生市近辺では日限地蔵と言わないと伝わらないほどであったようですが、今はさらにお地蔵さまをキャラクター化したり。
…決してそれがイメージアップとはなってはいないよう思うのは私だけ?
そんな群馬県桐生市の広沢町というところにも『日限地蔵尊』さまがおられると、親しくしていただいている元同僚さんから聞き、そうと知るとムズムズしてしまう私。
ヒントは広沢町にある『大雄院』という寺院のそば、ということ、なのでまずは大雄院さんをめざします。
国道50号線を少し入っていくようです。
車が絶えず走る片道二車線の道路からほんの少し入っただけなのに、のどかな人々の暮らす住宅地と変わります。
その一画に、『はらぺこあおむし』の遊具のある広場がありました。
どうやら保育園の遊び場のよう。
反対側に園舎があり、園舎に続いた園庭もあります。
なんだかワクワクするような保育園です。
えっ?
なんと園庭に立派な、屋根の付いた土俵があるではないですか!
こう書くと和の園庭?と思われるかもしれませんが、カラフルな大きなお花のモニュメントや遊具もあって、それらが見事にマッチしています。
保育園にみとれていると、目の前に一見してお寺さんの建物がまるでそびえ立つように見えてきていたではないですか。
結構な高さまである石垣の上です。
石垣の高さにビビり、さらにはそこにそびえるかのように立つお寺さんに畏敬の念を抱きました。
(続き)
まず大雄院さんをお詣りさせていただきます。
見上げてみた以上に高く積まれた石垣に少しまたビビりながら横にも長いコンクリートの階段を登ります。
楼門をくぐろうとするとそれはそれは色鮮やかな龍が睨みをきかせておられます。
「お参りをさせていただきたくどうかお通しください」
そして。
門をお護りになられておられます方々にもご挨拶を…。
!
仁王さまではなく、天部の神さまがお護りです。
それも四天王さまが揃ってお護りになられておられる!
同じ桐生市のお寺さん、梅田町にある『鳳仙寺』さんも天部がお護りで、宗派も同じ曹洞宗です。
(鳳仙寺さんは二天でありましたが)
これは総本山永平寺さんに倣ってのことでしょうか。
大好き、…などと申し上げるのは不敬でしょうが、思わぬところでお会いできた四天王さまにわくわくドキドキしつつ門をくぐりました。
ただ。
鳥や野生動物、何よりも悪しき心を抱く人間から守るため、でしょう、四天王さまは網越し。
少し寂しくもある私でありました。
門のひだりてに手水舎があります。
イケメンの龍さまからお水をお授けいただき、手を清めました。
門のみぎてには一瞬足が止まりそのままかたまるほど大きな鐘楼に大きな梵鐘が!
どうやら撞いて良いようです。
鐘楼の数段の段をのぼります。
遠くから見ても大きかった鐘は近くに寄るとさらに大きいっ!
大きな鐘は低くて重い音でありました。
梵鐘には般若心経、そして道元禅師さま瑩山禅師さまのお言葉と、この梵鐘は供養のために奉納された旨、
奉納された方の先祖代々、そしてお二方の戒名とが刻まれておりました。
…と、淡々と書いてはおりますが、何度も書いておりますがこの梵鐘、かなり大きなものです。
どうやらこの鐘、そして鐘楼、お一方の御寄進のようなのです。
お金の話はあまりにも下賎ではありますが、この大きさって…。
普通サイズ、というものがあるかどうかは置いておき、倍はあるのではないかと思われる大きさです。
第二次世界大戦の供出により失われたお寺の鐘は、今なお再建できないお寺さんも多いというのに、これは凄いことかと…。
(続き)
御本堂へと向かいます。
やはり大きな御本堂です。
中を覗くと、ひ、広い!
横にも広く奥行きもあります。
御本堂前に座って手を合わせて。
ご本尊さまの輝くお姿はかろうじて見えますが、距離があるためどなたがおまつりされるのがどなたであるかはまるでわかりませんでした。
御本堂の前に正座して、ふと左側を目をやると。
多重塔がある!
はやる気持ちを抑えて抑えて。
今登った階段を気をつけて降ります。
青い空にそびえ立つ三重塔。
さらにはその姿が池に美しさといったらありません。
なんと癒される光景でしょう。
こんなに癒しの空間が車で三十分走るか走らないくらいのところにあるなんて…✨
大変良いお導きをいただきました。
池のほとりに何故か作家山本有三氏の『路傍の石』の一節の刻まれた碑が?
はて?
何かご縁があったのでしょうか?
ちなみに栃木県出身である山本有三氏のお墓は栃木県にあります。
こちらではありません。
宗派も異なっていたような…。
たった一人しかいない自分を
たった一度しかない一生を
本当に生かさなかったら
人間
うまれてきたかいがないじゃないか
〜『路傍の石』 山本有三
ま、まあいいですかね。
年が明けたと思ったら、もう月も変わりはや如月の時をむかえています。
お釈迦さまの亡くなられたという二月十五日ももう少しでやってきます。
ご存知の方もおられましょうが私はその日に生まれております。
かなり前の話になるのですが、あるお寺のご住職さまの息子さんも同じ二月十五日生まれなのだというお話を聞きました。
同じ誕生日という話を聞くと、なにやら親近感のような思いを抱くのは私だけでしょうか。
ところが。
ご住職さまはさらに続けて
「よりにもよってこんな日にと、悲しかったし悔しかったよ」と話されたのです。
えっ?
そんな日なの?
そこまで忌み嫌われる日?
…衝撃でした。
「あのぉ、わたしもその日に生まれているのですけれど…」
「あんたはいいんだよ。ウチは寺だよ?その跡継ぎがよりにもよって…」
なんだか頭にきました。
そして私は反論したのです。
そう、なんとお坊さまに説教をしたのです。
「命をかけて貴方の子遠産んで下さった奥さまにこれ以上ない失礼だし、尊い子の誕生を祝えない日などあるはずがないでしょう。
お釈迦さまに縁を持つ尊いお子と思えませんか?」
…お釈迦さまに縁を持つ、とは考えられないかもしれない。
そういうものではないでありましょう。
お寺さんの決まり事の、しがらみにも似た決まり事のわからない人間だから言えるのかもしれません。
ましてやその方はすでに七十歳、
そのお子さまが生まれた頃の時代における状況は今とは異なっていたでしょうし、
何よりもその方の生まれ育った年代、そして環境からくるものも多分にありますことは、それはそれで私のような者にも想像くらいはできるつもりです。
でもその日が自分の誕生日でもある私だからこそ言えるんだとばかりに力説いたしました。
「あんたにはわからないよ」
…きっとこれはずっとわからないことだと思う。
わかりたくないからだ。
(続き)
こんなに医学が進歩した今であっても、お産が命がけであることは全く変わっていないのです。
かく言う私も医療側の目でみればまさに命がけの妊娠経過をたどり、病室の廊下にすら出られない程の安静度を三か月以上過ごしましたし、
輸血騒ぎをするお産を二度も経験しております。
意識が遠のく中、
「輸血準備しろ!」
「すぐオペだ!」
というドクターの緊迫した声を聞きながら、
(へえ〜、自分の人生でこんな場面に直面しようとは思ってなかったなぁ、まして自分がその対象だなんて夢にも思ったことなかったなぁ)
とのんきにも思っておりましたが、ね。
産まれたばかりのわが子を抱きもせず死ぬわけが無い、というよりも〝死〟であることとか死ぬことなど、微塵も思わない。
当然ですよね。
前の日までピンピンとして日常生活を送っていて、ほんの少し前に赤ちゃんが産まれたばかりの二十代の若き身です。
ただ…。
その思いはしごく当然、なのにも関わらず、そのまま助からない方がおられるのも、…かなしいかな事実なのです。
これはもっともっと男性に知って欲しい。
知っていて欲しいです。
…まぁ、その頃自宅で祝杯をあげ、ぐっすり寝込んでいた夫は、
いまだにお産が命がけであること、ましてや自分の妻がそんなギリギリのところにいたことをすらわかってはいないのですがね。
貴方の奥さまは命がけで貴方との子を産んでいるのです。
貴方のお母さまは命がけで貴方を産んでいるのです。
二月十五日。
〜いつまでも悲しんでいてはいけない
〜教えを守って生きるように
そう説かれて亡くなられたお釈迦さまの教えを一番ストレートに受け止められる日だと私は思っております。
死の床でお釈迦さまが語られ説かれた最期の教えだといわれる【遺教経】にふれるとことさら、です。
だから涅槃会、お釈迦さまの亡くなられた日に生まれたのだって決して悪いことはないと、胸を張って言えます。
…まぁたしかに。
あの春の日、多くの花咲く日に、すべてのものから祝福されお生まれになられたというお釈迦さまのお誕生日と同じ方が素敵だとは思わなくはないけれど 笑。
もう少しで同じ日に産まれた方、
少し早めにはなりますが
おめでとうございます✨
群馬県みどり市の【南光寺】さん
今日はこちらの涅槃図を拝観させていただきました。
お時間の指定を受け、早過ぎず遅過ぎずをめざします。
が。
時間通りにをめざしたいのはやまやまです、というか当然です。
当然なのは百も承知なのです。
それでも。
何が困るか、というとこちらのお寺さんはあまりにも久しぶりの参拝なため、正直辿り着けるかどうかすらが不確定なのです。
ええ、ひとえにいまだにナビの無い車に乗っているからであります。
もちろん地図は見ております。
家を出る前にざっと目を通して…
(これならば行けるぞ)
と思えたのです。
信号を二つ行って右折して…。
ここまでは間違いなく来たはず、な・の・に…。
目印としたお店が、無い!
嘘でしょ?
まぁ夫にはよく言われるのです。
「お店を目印にしてそこが無くなったらどうするの。やめた方がいい」
…だって、じゃあ何を?
Googleマップに出てるんだから、そのお店は潰れたりしていない、はず。
なのに、無い。
…スマホ?
おんなじGoogleマップしか出てこないし。
…いいや、ダメ元で、適当な方角、お寺さんのありそうな樹木の多いところを適当に目指そ。
早速間違えます。
なんか工場の敷地に入りそうな…
その先は大きな通り。
大きな通りに出てはお寺さんには着かない。
少し奥まったところにあるお寺さんです。
おっ?
その大きな通りから一台車が。
その車のおかげで私からしたら死角となるほどヘヤピンカーブし、しかも細い道があることが判明しました。
よっこらしょ、とヘヤピンカーブを何度か切り返して、その細い道へと入ります。
ま、謎が解けたわけではないんですがね。
細い道を行って、行き止まりとかになったらどうするのか。
不思議とあんまり焦ってはいない自分に自分でも軽く驚きつつ、止まらずに道なりに走ります。
どう走ったのかなぁ。
…なんとなく。
あっ!
目印としていたお店に戻れました。
ここを入って行く!
…って細いんですけど。
ま、いいや、行こう。
全く不思議なことに相変わらずドキドキもしていません。
時間も気になりません。
不思議と指定された時刻に着く、おぼろげではあるのですがそんな気がするのです。
本当に道に迷いまくっているくせに。
現在地すら言えやしないくらいに。
(続き)
こちらのお寺さんは北関東不動尊三十六札所となっております。
不動明王さまの祀られるお寺さん。
不動明王さまは川や、登山口などに立ち(祀られ)、そこに潜む危険から人々をお護りくださる仏でもあり、道を外れて歩いて危険に遭わぬよう道を示す方であるとお聞きしたことがあります。
きっとお不動さまが御導きくださっておられたのだと私は信じております。
細い、対向車が来たらドキドキするような道で、現在地すらわからない状態で、ナビも無く道に迷っている状況で落ち着いていられるって、…普通ならありえませんもの。
たしかに細かろうと道は必ずつながっており、どこかへは出られましょう。
でもそれが突き当たりで、ずっとバックして戻るようなこととなったかも知れなかったわけで、地図に疎く、道覚えが致命的に出来ず、方向音痴で、しかもなによりビビりな私が、そんな状況にありながらありえないくらいに落ち着いていられるなど、そうとしか思えない。
しかもこの日は約束してうかがうので、約束の時刻もさまっていたというのに。
今思えば思うほど、間違えたと思うと必ずヒントがそこに散りばめられて、最後などはまさに!
不思議に左側に意識が集中していて、そのあまりの不思議さに、ちょこちょこ左側を見るように走り、そしてふと見たところに細い道があって、見上げるとそこには馬頭観音さまの小さな御像がぽつんと立っていたのです。
細い道は登り斜面。
間違いない!ここだ!!
迷って、迷って、いざとなったら今来た道を戻ってまるで異なるルートで仕切り直せばいい、そこまで思ったというのに、約束の時刻よりも十分も早く着くことができたのです。
それもお寺さんの表札とも言っていい寺標すらない裏からの、知る人ぞ知るといった細道を入ってのことでありました。
これに奇跡を感じないわけが無いのです。
(続き)
左右の寺標が山門の代わり。
そこに立つと大きな御本堂が目の前に見えます。
記録的な風となったこの日、結構大きな枯れ枝までが落ちたようで、途方にくれるほどの落ち葉や枯れ枝を黙々とひたすら掃いておられる方の姿か見えました。
…御本堂へのお参りが先?
この方への参詣の目的をお話するのが先?
まあ本来なら何よりも先に御本堂へのお参り、な気もいたしますが、
なにぶんも御本堂の真ん前でのこと。
まずはこの方へのご挨拶と、本日ここへまいりました理由をお話しさせていただきました。
「ああ、今日お電話下さった方」
いえ私は昨日でありました。
…他にも涅槃図を拝観したいと申し出る方がおられるのかと、ちょっとホッとしたり。
その方をお待ちするようかなぁとぼんやり考えていると、
「ここを少しだけキリをつけちゃってもいいですか?」
もちろんでございます。
なんならお手伝いさせていただきますが。
「いやそれには及びません。ほんの少しだけお待ちくださればキリがつくから大丈夫です」
…まぁ、ここで
「そう?じゃお願い♡」
という人はなかなかの少数派でしょうが。
私があらためて御本堂にお参りをさせていただく間にとりあえずの〝キリ〟をおつけくださって、御本堂の鍵をお開けくださいました。
その戸は御本堂正面より右寄りのものでありました。
!
真正面にお不動さまが!
こちらのお寺さんへ来るのにありえない道に迷い込んだ私が、奇跡のようにこちらに来られたのはお不動さまのお導きに違いないと密かに思っておりましたそのまさにお不動さまが!
初めてお目にかかったこちらのお不動さまは、丈六の全身が金色に輝くお姿をされておられました。
金色のお不動さまに驚いているかに見えたでありましょう、お坊さまが、涅槃図を…あのバスガイドさんが案内するときに掲げる手のような手で示されました。
ま、まぁ、金色、しかも坐位とは言え丈六とあれば初めて拝すると誰も驚きましょう。
かくいう私もそういった驚きがありましたのも事実です。
(あ、涅槃図)
目的すらが一瞬ですっ飛んだ私でありました。
(続き)
涅槃図を前にすると自然座る私。
畏れ多くてついつい気持ちと身体がそう反応してしまうのです。
すると涅槃図の前にはお焼香の準備をしてくださっておられました。
お燈明も、きちんとろうそくに火を灯されておりました。
お焼香の準備とひとことで言うと、あの葬儀や法要の際に置かれた抹香と灰のセットになった〝容器〟を置いただけに思われるやもしれません。
それだけでは焼香はできない。
あの灰のうえに炭を起こして置いてはじめて焼香ができるのです。
商品の出来や保管状況によって異なるようではありますが、この炭起こし、なかなか火がつかないこともありますし、たった一回、一人のために炭を起こすのを不経済だと考えれば、まさに不経済ですし、何より火を起こすのですからその炭が消えるまでは厳密に言うならば火災を起こす可能性もゼロではありません。
それだけ、涅槃図に対しての敬意があり、そして一限の参拝者に対してもおもてなしの心をもって迎えてくださった証、ほかならないのです。
そこに大きな感動をいたしました。
美しい真っ白な菊が左右に供えられています。
今、涅槃会はだいぶ過ぎてしまっておりますが、このときはまだ涅槃会の何日か前のこと。
その日にならないとお花を供えない、という考え方もできなくはありません。
檀家さんの法事等の法要でもなければ、お寺さんの方しかこちらへは来られません。
誰が見ようと見まいと、お釈迦さまの描かれたこの画を、尊いものと心から思っておられるということのあらわれにほかありません。
…当たり前が当たり前で無くなってきているのが、悲しいかな、今のお寺さん事情です。
「こんなの」と涅槃図を表現され、指差す僧侶もありますし、
「あるけどうちは飾らないんだよ、法事がいっぱいあって、本堂に飾ってあるとなにかと邪魔になるからね」とクソみその扱いをするお寺さんもあります。
ご住職が入院され、副住職がそれをいいことに「今年は飾らない」と言うお寺さんもありました。手がないから、ではなく面倒くさいからと平然とおっしゃるのです。
お坊さんも一人の人、人間に過ぎない。
そう考えるとただの個性でしか無いと思われます。
たしかに室町の時代の涅槃図だとおっしゃるお寺さんもあり、もはや広げると取り返しがつかないほど傷んでしまっているケースもなくは無いでしょう。
数日前この続きを八百数十字打ちこんで消えたためたいそう落ち込んでいる私。
パソコンにすれば良いのだけれどそうすると画像の移動がパソコン音痴過ぎてできないというジレンマ。
かなりいろいろ調べ、自分ではなかなかの文章だったからことさらで。
落ち込んで逃避してひたすら仏像を彫り、新しくしたコタツの上掛けを編んだりしているので、別の意味では実りある日々を過ごしております。
ただ…体調的には以前の何十分の一くらいの運動量でもすぐに気管支炎や肺炎を起こす。
かなり広いお寺さんを参拝しただけでその晩たちどころにその症状か発症する。
なんだかな…。
仕事で身体を壊しての今ではあるのだけれど。
頑張っていた自分は認めるけれど、それもただ過去にしか過ぎない。
この身体でできること。
よく、仏師であるお師匠さまがおっしゃいます。
『まず自分が幸せでないとね』
私の自分探しはまた方向性を模索することとなるかもしれない。
ステロイドの吸入、そして内服をして、頓服の吸入薬を使ってなおすぐには収まらない喘息。
夕方になると咳が始まり止まらない毎日。
気持ちは落ち込むばかり。
あるとき息子がスマホの画面で、もうすでに一目でなんのものかわかるくらいに観ている画像を見せてきた。
「行こう!」
「ごめん、これで出先で大きな発作を起こすとすごい迷惑をかけちゃうから…」
仕事でみてきた患者さんの心理パターンの典型的な一例、自分で寂しくなる。
前の晩にも咳が止まらなかった。
また声をかけてくれる息子。
彼は今貯まった有給休暇を取っているため平日休みの連休中だ。
「うんありがと」
それは…。
長野県上田市立美術館において開催中の特別展
【ハッケン!上田の仏像】
の期間が今月九日(日)までであることをたまたまネットで息子が知ってのこと。
そして、昨日息子の運転で上田市へと向かいました。
ポスターにない御仏のご尊像も素晴らしいものが多く、江戸時代に仏師によって定朝作と鑑定されたという【阿弥陀如来坐像】などはことに私の胸を打つものでありました。
一時間半以上かけて仏像を観て回る母につかず離れず見守る息子。
感謝してもしきれない。
それにしても。
地方のそれもただの一つの市に過ぎない上田市はなんと壮大な企画をされたことでしょう。
驚きしかありません。
このように数多くの御仏の尊像をお借りするにはどれだけのご苦労があったことでしょう。
お借りして、それこそ一片の破損もさせることの無きよう運搬にも細心の注意を図り(運搬のプロに依頼してのことでありましょうが)、美術館内においてはより良い形での展示を考え、このような見事な展覧に至っております。
並々ならぬご苦労があってのこの特別展でありましょう。
展示は年代を追って展示されており、上田市の仏教のあゆみを垣間みることができました。
本当に本当に素晴らしい特別展でありました。
そんな帰宅途中、ラジオを長野放送からNHK第1放送に切り替えたところ、
長野県上田市の大きな火災を報じていて息子と二人大変驚きました。
長野県の、それも同じ上田市にいて、消防車のサイレンも聞かなければ、
長野放送を聴いている間一度としてそのような情報が流れてくることがなかったのです。
NHKの放送でも一度きり。
これは…事実?
(続き)
これは、…もしかしたらどこかの火災と混乱しての誤報かと思いつつ帰宅いたしました。
テレビニュースにも(たまたま)なく、なんだったのだろうと思いながらも自分たちの上田で体感した感覚を信じて、岩手県の山林火災が一日も早く鎮火することを祈って眠りにつきました。
が。
悲しいかなそれは誤報などではなかった。
自衛隊に消化活動を依頼するレベルの大きな火災であるようでした。
そして今まだ鎮火されたという情報は無いようです。
お近くにお住まいの皆さんや、消火活動にあたる専門部隊の皆さんのお命を最優先に。
これ以上被害が広がらない事を切に祈るばかりです。
また初期消火を試みた男性がかなりの火傷をおわれているようです。
1日も早い回復をお祈りいたします。
いま、NHKの朝ドラでちょうどコロナ禍をテーマに話が展開されている。
胸が苦しくなって、バクバクする。
そんな自分に、ああ、あのときの私はこんなにも長いこと引きずるような辛さを抱えて生きていたんだなあと、あらためて痛感した。
未知の病はそれまでもあった。
SARSだって距離的には近かった。
しかし怖さはあまり感じなかった。
国内での感染は少なかったし、ルートが整っての受け入れであったし、この感染対策で大丈夫であろうという安心感をもてた。
ただコロナはもっともっと近く、その致死率は恐ろしくて、そしていきなり懐まで近づくような距離にある病だった。
その症状を一切隠して医療機関を訪れる初期の罹患患者。
体温計すらずらして測る狡猾さだった。
まだその場での検査すらできない状況下でのことだった。
上司は自分の罹患を恐れて部下に接触させ、自分はデスクワークに徹した。
人間不信になっていく。
家に帰るにも着替えにも、車に乗るにも、家の門扉に触れるにも思いつく限りの感染対策をして。
速攻シャワーに向かい、着ていた衣類を単独で洗って、洗濯機を消毒して。
毎日毎日緊張して。
生まれたばかりの孫と娘が心配でも、会いに行くことこそが一番危険だという自分。
そんな中体調を崩す。
自律神経を整えるなど不可能に近い。
心拍は百二十を超え、当然動悸はする、眩暈はする、息はくるしい。
意識の底にしまい込んだつらかった過去が、まるで枯渇した川の川底が見えるかのように露呈された。
コロナは過去ではない。
このドラマは封印する。
【箱根神社】さん
かねてから、いつか行きたいと思っていた箱根神社さんへお詣りすることが叶いました。
駐車場から入る、傍の小さな鳥居をくぐるとまもなくひっそりと建つ石碑に気づきました。
【金剛王院東福寺の跡】
と大きく刻まれており、その下に小さく刻まれた文字。
かつてこの地には【東福寺】さんというお寺があったようです。
【金剛王院東福寺の跡】
奈良朝の末、当地に建立された箱根権現の別当寺、【金剛王院東福寺】は古義真言宗御室派に属し、開創の萬巻上人いらい千年の歴史をもつ関東屈指の名刹であった。
鎌倉期には、源頼朝や幕府の崇敬篤く、近世に至るまで歴代の武将も信仰し、箱根修験の名を高めた山伏等の根拠地としても栄えた。
金堂や鐘楼、僧坊等が軒を連ね、また親鸞上人自作の像をまつる親鸞堂もあったが、明治維新の神仏分離により、明治元年三月、『権現号』が廃止されるまで累代の別当が居を構えていた。
当時の七十一世住僧等は復飾し神職となったが、東福寺は廃止され、寺宝等は悉く消滅した。
とありました。
ことごとくの消滅。
…こんな短く書かれた文章。
短い文章にはそこから読み手が想像する余地が含まれています。
ただ単に寺としての役割、機能を失ったと捉えて、(ああ、神社一本として歩み出したということか)ととらえられることもありましょう。
…あえて、なのだろうな。
〝消滅〟。
少し調べると、それはまさに消滅であったことがわかりました。
御仏像から仏具、寺宝、仏塔、御堂が全てことごとく、
…破壊され、火をつけられて〝消滅〟されたようでした。
…学ぶと、明治政府はそこまでの指示を出していたわけではなかったようではないようでで…。
ただ、その行間の隙間に、人々は自らの解釈、曲解を含め、
ここ、箱根神社においては〝消滅〟に至るまで神仏分離を行った人、人々がいた、ということ。
昨日まで畏れ多く、崇め奉っていた御仏を破壊し、火を放つ…。
…人は恐い。
ただそこにはひがみや嫉みを買うような、やはりただびとである寺の姿勢があったことも否めないようではあるのだが、そこを含めて人は恐い。
初めて参拝させていただいた箱根神社さんは、そんな愚かな人間を温かくお迎えくださる気に満ちていました。
神さま、仏さまはどこまでもありがたい存在でありました。
(箱根神社さん 続き)
遠く異国の地から訪れた人々も多くおられました。
…半数以上がそうだったやもしれません。
ほとんどの方が異国の神さまに対して敬意を表し恭しく手を合わせておられました。
その姿もまたありがたいと思い、知らず知らずそっと手を合わせ頭を下げていた私でありました。
とはいえ。
やはり異国のロケーションの素晴らしさで訪れている人たちがいるのもたしかなことで。
境内社の曽我神社さんを占拠して写真撮影に興じる一集団がいたのも事実。
鳥居を塞ぎ、中で小物まで替えて、三十分以上。
鳥居をくぐろうとすることさえ拒否して罵声を浴びさせられました。
三十分が過ぎたところでメンバーチェンジするだけで、そこを占拠する状況は変わらない。
たしかに、高額のお金を使い、日本という地を訪れたかもしれません。
けれど日本人だって、ここを初めて訪れて、これが最初で最後かもしれないと思って訪れた人だっている。
彼らの撮影会のためのセットではない。
ここは日本の祈りの場。
無理に鳥居をくぐろうとすると、大柄の男性が手を出そうとまでしました。
さすがに周りがとめました。
男の人はずっと罵声を浴びさせます。
平常心!
鳥居に戻ろうとすると、まだ鳥居を塞いだまま、私が映らないよう撮影を開始しています。
「ここは祈りの場です」
鳥居をふさぐ人たちにそう宣言しました。
ま、そこは日本語、なところが私なんですがね。
でも英語圏でも無い、アジア系でも無い方々ですから、英語が通じたかどうかもわからない。
神さまの前で争うことは決して良くはないでしょう。
でも私は日本人としての矜持を持ち生きていきたい。
写真を撮ることは決していけないとは言わない。
祈りの場であること、人が来たら譲る、そうした人としての常識を持ってさえいてくれれば良い。
彼らは全くそうではなかった。
ここは曽我兄弟を祀る場。
何一つ知らず、日本らしい建物として写真撮影に興じる異国の人に私は屈しない。
明後日、お釈迦さまご生誕の日に、年に一度の御開帳をされるお寺さんがある。
歴史オタクの夫の心ゆさぶる、由緒ある一族ゆかりの仏像で、以前、その仏さまが祀られていた山の中腹のお堂までお参りにうかがったくらいである。
平日なこともあり、とりあえず情報として伝えたところ、それはそれはうれしそうに
「ありがとう。それは絶対行きたい。有休をとるよ」
とその場でスマホに打ち込んでいた。
それゆえてっきりそのお寺さんは二人でお参りに行くものだと思っていた。
昨日そのお寺さんのHPを見ていた夫が
「なんか明日(つまりは今日)も、御開帳されてるって書いてあるよ。じゃ明日行こう」
という。
私は今日は、半年も前から楽しみにしていた、とある神社さんの大祭があり、内心(ええ〜っ?)と思った。
それは夫に伝えてあったことだし、何を言っているのか正直わからなかった。
なぜ正規の、それも花まつりにあたる日をさけて明日(つまりは今日)行かなくてはならないのかと聞いてみた。
私は神社さんの大祭に行きたいのだ。
「休んでないよ(=休みは取っていない)」
はっ?
あんなに喜んで、休みを絶対取ると宣言していたのに?
まあ、仕事だからそんな事もあろう。
だけど。
ならば私に一言あってもいいのではない?
「ああそうだったね」
…言い方がいちいち鼻につく。
夜になって。
秩父の枝垂れ桜の美しいお寺さんが満開という話を聞いて、私はただ懐かしく思ってそれを彼に伝えた。
すると。
今度は、
「うわぁ、じゃあ明日は秩父へ行こう!俺あのお寺さんにもう一度行きたかったんだ!」
そのあとはそのお寺さんの御由緒にまつわる自分の疑問をペラペラと話して止まらない。
「明日は私、神社さんのお祭りに行くと言っていたのに、御開帳されるお寺さんに行くことになって、今度は秩父って、いい加減にして!」
…さすがにキレた。
「だって満開なんだろ?明日を逃したら来週はもう無理だよ?」
…頭がおかしい。
人語が通じない。
もはや神事にこれだけのケチがついて、あまりにも穢れが大きすぎて行くのはやめておいた。
夫は一人でどこかへ出かけて行った。
無心になりたくて仏像を彫った。
でも悔しい気持ちは消えなかった。
明後日四月八日は、お釈迦さまの誕生日。
【花まつり(灌仏会:かんぶつえ)】と呼ばれ、日本各地で昔からある仏教の伝統行事です。
この日には全国の多くのお寺さんで、
さまざまな草花を飾った【花御堂(はなみどう)】と呼ばれる小さなお堂を飾り、そこに【誕生仏】と呼ばれる、お釈迦さまが生まれたときすぐに歩いて右手で天を左手で地を指したという言い伝えに基づく像を祀り、
甘露の雨が降ったという言い伝えからそのお釈迦さま(誕生仏)の像に
甘茶を注いでお祝いをします。
お釈迦さまは生まれてすぐ東西南北に向かってそれぞれ七歩ずつ歩かれ、
右手は天、左手は地を指さし
「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」とおっしゃったと言われています。
また、お釈迦さまが生まれた際、九頭の龍が天に現れ、お釈迦さまの頭上から『甘露の雨』を注いだという言い伝えがあり、それが甘茶をかけるということへとつながっています。
ちなみに、花まつり(灌仏会)のほかにお釈迦さまに関する【三大法会】として
【成道会(じょうどうえ)】…悟りを開いた日である十二月八日
【涅槃会(ねはんえ)】…ご命日二月十五日
があります。
先だっても書きましたが
本日四月八日は【花まつり】
お釈迦様のお誕生日です。
灌仏会(かんぶつえ)
降誕会(ごうたんえ)
仏生会(ぶっしょうえ)
浴仏会(よくぶつえ)
龍華絵(りゅうげえ)
花会式(はなえしき)と呼ばれることもあります。
ご入学・ご入園のおめでたい日であります方もおられましょう。
平日ですのでお仕事の方が多いかと存じます。
かくいう私も、在職中は、
始業式であり、
あるいはご入学・ご入園のご子息のおられる同僚の休み希望が集中する日、花まつりへの参列は土日でも当たらない限りは無理でした。
行きたいけれど…と思われておられる方に、
花まつりに飾られる花御堂と誕生仏さまをあらためてここに飾ってみました。
今日一日がみなさまにとって良い日でありますように。
きのうの北関東は、風もなく、よく晴れた絶好の花まつり日和でありました。
うかがったのは二寺。
後からうかがったお寺さんは寄る予定ではなかったのですが、ご本尊さまがお釈迦さまであったことを思い出し、急遽寄ることとしたのです。
山門の前には【花まつり】と書かれた立て看板があり、紙を束ねて輪ゴムなどで止めて広げてで作る、あの花が幾色も飾られていていかにも花まつりらしい♡
広々とした駐車場。
しか〜し!
どれだけ広々としていようと、事故は起こるらしい。
…ぶつけられてしまいました。
「…ありえない」
「どうやったらこうぶつかる?」
その状況を見て内心そう思いました。
私自身は車に乗っておらず、御本堂の前でご住職さまとお話させていただいていた時でありました。
「車をぶつけてしまったのですが、車の持ち主の方はおられますか?」
とおっしゃる方がみえたのです。
一台一台の区画の広い駐車場でその話を聞いてもまさか自分のものとは思えなかったのですが、車の色を聞いて、…「ああ、私のなんだ」
私が怒りの感情を抱く前に、加害者の方のご友人が
「私だったらブチ切れてる!」
とおっしゃて、
さらには私に対して
「駐車中ぶつけているので、10対0で直せますし、代車も用意されますからね」と。
…なんだかそのまま怒りの感情を抱くことなく、すべての処理を終えていました。
ただ一つ、お相手が警察を入れることを何度も嫌がっており、それで事故の処理が遅れてしまい、それがこれ以上長引いたら私も〝キレた〟のかもしれません。
それ以外はママ友さんにお子さんを預け、終始平身低頭誠意をもって謝っておられ、そんな方に怒りをぶつけても何も生まれないし、何も無かった過去に戻れるわけでもない。
お子さんのことも気になるだろうにな。
そもそもお子さんは事故のとき同乗していたわけで、その心身は大丈夫なのだろうか。
そんな確認も取りました。
私だって子を持つ親、そして何より同じくらいの孫がいます。
ある方がミクルで言っておられたとあるドラマの台詞が胸にしみました。
「巡る因果は恨みじゃなくて恩がいいよ。
恩が恩を呼んでいく。
そんなめでたい話がいい」
ただ…。
レッカー移動となってしまった車。
タクシーで帰宅。
そんな花まつりとなってしまった私でありました。
栃木県足利市の【恵性院】さんの
【稚児の碑】
歴史オタク…歴男の夫はそれに寄り添うように存在する民話や伝説にも詳しくて、民話の地を訪ねることもあります。
栃木県足利市の笛吹山恵性院さんの境内にはやはり伝説にまつわる碑が残されているとのことで、もう十年ほど前になりますか…その碑を訪ねこちらを参拝させていただいたことがありました。
そのときはこの碑を知る方がたまたま不在で、碑をみることはかないませんでした。
いま、私が毎月八日の鶏足寺さんのお護摩祈願に参列すべく一人車を走らせているまさにその道、
気持ちの良い、少しカーブになった坂道、笛吹坂と呼ばれる坂であります。
この坂道をのぼる、向かって左側にその名も笛吹山恵性院さんがあります。
笛吹山恵性院さんがあるから笛吹坂、と呼ばれているわけではありません。
この恵性院さん、かつてはその名を明月院といったといいます。
そして、そのころはまだ、この坂は笛吹坂と呼ばれていたわけではなかったのです。
名月院は平安末期に真言宗別格本山鶏足寺末寺として吽誉法印により開創されましたお寺さんですあります。
〜稚子と郷土の娘の悲恋物語〜
今を遡ること六百年以上前、京都の公郷の息子で信光という稚児が故あって明月院で僧道修行に励んでいました。
信光は笛の名手で、毎夜明月院の境内から坂を見下ろすよう笛を吹き、静かな村里に美しい音色を響かせていたと言われています。
いつしかそれに合わせるように琴の音がおこり、やがてふたつの音が一つの曲のようになったといいます。
それから毎晩のように琴と笛が美しい曲を奏でるようになりました。
その琴の音の主は寺の西に住む郷士、大川義種の娘で、里人から菊枝姫と呼ばれ慕われていたといいます。
笛の主に会いたい、会ってみたいと、ある夜、菊枝姫は明月院に通じる坂道を登っていったといいます。
そして坂の上で月の光を浴びながら笛を吹く稚児信光を見ます。
信光は笛の名手であると同時にたいそう美しい少年であったといいます。
二人はいつしか恋に落ち、相思相愛の仲となっていきました。
(続きます)
〜稚子と足利郷士の娘の悲恋物語〜
今を遡ること六百年以上前、京都の公郷の息子で信光という稚児が故あって明月院で僧道修行に励んでいました。
信光は笛の名手で、毎夜明月院の境内から坂を見下ろすよう笛を吹き、静かな村里に美しい音色を響かせていたと言われています。
いつしかそれに合わせるように琴の音がおこり、やがてふたつの音が一つの曲のようになったといいます。
それから毎晩のように琴と笛が美しい曲を奏でるようになりました。
その琴の音の主は寺の西に住む郷士、大川義種の娘で、里人から菊枝姫と呼ばれ慕われていたといいます。
笛の主に会いたい、会ってみたいと、ある夜、菊枝姫は明月院に通じる坂道を登っていったといいます。
そして坂の上で月の光を浴びながら笛を吹く稚児信光を見ます。
信光は笛の名手であると同時にたいそう美しい少年であったといいます。
二人はいつしか恋に落ち、相思相愛の仲となっていきました。
しかし、これを知った大川家では
「道ならぬ恋は家名を傷つける」と菊枝に外出を禁じ、邸の奥に監禁してしまいました。
あまりの束縛、そして恋しい人への焦がれる思いで姫は病の床に伏してしまいます。
ある寒い夜、歩けぬほど衰えた身体で邸を抜け庭先まで這い出し、そこで倒れ、…翌朝冷たくなった姿が発見されたのでありました。
そして、そんなこととは知らぬ信光でしたが、
「病気にでもなったのだろうか」
「今夜は顔を見せてくれるだろうか」
「今日は逢えるだろう」
と、夜にやるなるのを待ちかねては、笛を持ち、毎晩毎夜笛を吐きながら坂をのぼっていったといいます。
そしてついには信光も心配のあまり病気になって、亡くなってしまったのでした。
この哀しい恋の物語を伝える石碑と、稚児信光の墓が今も恵性院さんの墓地に残っています。
ちなみに。
明月院が現在の『恵性院』と改称されたのは、宝暦元(1751)年舜岳上人中興の時とされるといいます。
春うららかな頃に、まっさらの新品新車の代車が届いたおかげで、畏れ多くてどっこにも行く気になれない私を哀れに思ったのか、花散らしの雨が…。
私はそんなこと、望んではいないのよ。
花はまた来年も見られるの。
ただ…。
去年花を散らしたあと、また来年美しい花を咲かさるために、
気まぐれにしか降らない雨からの水を、ただただ恵みとして根を育て、幹を育て、来年の花芽を育んで。
時には降り過ぎるほど降る雨。
時には雹が幹や枝を襲うし。
今までにない熱さで降り注ぐ太陽の日差し。
連日続く熱い熱い空気。
折れるかと思うくらいに吹きつける風にも耐え、時には雪も降る。
雪の重みで枝が折れることすらもある。
寒さの冬を耐えて、越えて、ようやく蕾を持って、花開いたのよ。
だから少しでも長く咲かせてあげて。
私が愛でることができなくとも、そこに咲いてくれていることがありがたいの。
毎年毎年
誰かが見上げて勇気をもらい、
誰かが見上げて涙を隠し、
誰かが見上げて癒されている。
…たとえばそれは私の愛おしい人。
雨も恵みと、また来年に向けて、
ただただ立つ木々。
花の時期を終えると見上げる人も激減するだろうが、そんなことは木たちにはまるで関さない。
尊い、学ぶことの多い植物たち。
神社仏閣巡りの関わりでネットで知り合った方が、昨日お母様が亡くなられたことを綴られていました。
ここ二週間ほどは介護施設に泊まり込んで共に過ごされ、最期を看取られた方でした。
その方がお母様が亡くなられた次の日の早朝、暇なのでとよりにもよって
>神社さんにお詣りしたと
綴られていました。
あまりのことで私がオロオロしてしまいました。
神道では死を穢れととらえ、身内で不幸があった場合、服忌(ぶっき)ととらえ神社の参拝はおろか、鳥居をくぐることすら控えるよういわれています。
日本人であり神社さんのお神楽の奉仕もされる方なので、忌中という言葉を、忌中というものを知らないとは到底思われません。
忌中も忌中、まだなんの仏事も神事も執り行われていない、
その神社さんの神職の方にそれなりのお祓いをしていただいたとは思われません状況での神社参拝。
彼女にとっての神社仏閣巡りっていったい…。
興味を持ったこと、でしかなかったのでしょうか。
そう思って振り返ると、たしかに仏像や石仏をわざわざその地の図書館や資料館に出向き、文献を見て調べるほどの方で、宗教としてというより物としての関心が強かったような…。
でも。
うちのように核家族な上、無宗教の家に育った子どもたちだって、忌中、喪中という感覚はもっておりました。
それほど日本という国には浸透しているものだと思っておりました。
(続きます)
(続き)
以前喪が明けて参拝させていただいた神社さんで、「喪は明けているのですね」と繰り返し繰り返し念を押すように聞かれ、
穢れを持ち込まれた神社さんはそれなりのお祓いをなさるようだということを学んだこともある私。
ドキドキはなかなか鎮まらない。
その神社さんにご連絡申し上げた方がいいのかしら…。
それは出過ぎたことだろうな…。
そもそも服忌のことについて何も知らない方が、普通に参拝されていても、神社さんは知る由もありません。
ただ、そんなことって無いわけではない…かなり特殊な例でしょうが。
服忌という習慣を全く知らない方であっても、暇だからと神社さんを散歩のように参拝される方はまずあまりいないはずです。
…なんでよりにもよって神社さん?
ネットだけのおつきあいとはいえ、これからはちょっと…その方との心の距離が生まれてしまった。
…まあ、あちらはもともと、たかだかネット上での知り合いでしか無いので、心のつながりなど感じもしていなかったか。
そういうクールさが無い私はネットには不向きなのかもしれないな。
【磯山弁財天 御開帳】
十二年に一度、巳年の年に御開帳されるという磯山弁財天さまの御開帳日が四月二十日ということを知ったのは一年ほど前。
この日を指折り楽しみにしていよいよ今日参拝させていただきました。
ただこちらは駐車場が大変少なく、稚児行列や法要はあきらめて、それが終わったころを目指して栃木県の出流原へと向かいました。
さすが十二年に一度の御開帳です。
人出が凄い!!
列をなしてのぼる石段は百八十段。
小さなお子さんが並んで、一生懸命石段を一段一段登っているのが愛おしかったです。
鐘を撞いて、手水鉢で手を浄めて。
ようやく御堂が見える石段です。
この日は曇り。
それでも赤いお堂の色は鮮やかです。
それもそのはず、昨年よりクラファンをし、このお堂の修理修復を行われたのです。
鎌倉時代に造られたという、そびえ立つ岩山に寄り添うよう建てられた【懸造り】の御堂は、御開帳で集まった多くの人々が乗ろうとびくともいたしません。
おお、御堂が開いています。
それも両側面の戸まで開け放たれているではないですか!
新しそうな畳の間に、分厚い座布団が置かれ、その前には護摩壇があります。
そして。
なんとも美しい…ほどこされた彫りも、そこに塗られた色の色調もたいそう美しいもので、その内には弁財天さまがおられるのが見てとれます。
さらには小さな御厨子なのですが、十五童子が共にお祀りされているではないですか!
【迦葉山弥勒寺】さん
『天狗のお山』として知られる群馬県沼田市の迦葉山竜華院弥勒寺さん。
今年は十年に一度の御開帳の年であり、現在まさにこの御開帳期間です。
前回参拝させていただいたのが七年前。
そう次の御開帳にはほど遠く、寂しく思えたものでした。
煩悩のかたまりにして、執念深い私は毎年指折りつつ今年の春の御開帳を待ちました。
まあ…ただただ指折り待っていただけなんですけど、ね。
こちらは同じ群馬県とはいえ片道二時間はかかる場所(自宅より片道四十五キロ弱)なうえ、峠を越える!
運転ほにゃららな私は自分でこちらに来るのはちょっと…だいぶ難易度が高いのです。
今年新年を迎えるや否や、
「今年は迦葉山弥勒寺さんの御開帳の年だからね」
と声高らかに夫に告げました。
…人にものを頼むときは?
「連れて行ってください!」
ですよね、はい…。
妻にそんな高らかに宣言された夫はといいますと、けなげにも同日他にも参拝をするお寺さんや神社さんを調べ、同じ沼田市のお寺さんで一年に一度四月二十九日に御開帳されるところがあることまでも調べてくれたのでありました。
そして。
まさにその四月二十九日、迦葉山弥勒寺さんへ連れて行ってくれた…下さったのでありました。
この場を借りて御礼申し上げましょう(えっ?、直接は?)。
(続き)
〝天狗のお山〟といわれる群馬県沼田市の迦葉山竜華院弥勒寺さん。
石段をのぼると、橋があって、その両サイドには石造の天狗さまが二体でお出迎えくださいます。
【中峰尊】と書かれた扁額のかかる御堂か天狗さまのお祀りされた御堂です。
鰐口をたたいて御堂へと入ります。
!!!
何度か目の参拝であるにもかかわらず、やはり驚いてしまいます。
正面むかって左側には壁の上から下までを覆うほどの大きな天狗さまのお面が祀られています。
正面には一体いくつあるのかわからないくらいの、よくある顔に被るくらいの天狗さんのお面。
そして、お借り面といわれる、お借りするお面が、お面屋さんにだってこんなにあるだろうかというくらい平台に置かれています。
前を見ても後ろを向いても大小さまざま、年代もいろいろの天狗さまのお面がお祀りされています。
…御開帳だから、ではありません。
これはいつもと変わらない光景であります。
ただ一ついつもと違っていたのは、正面に紅白の、鉢巻を太くしたくらいの質感の長い長い布がさげられていたこと。
【おさがりの
紅白の綱は
善のつなと申し上げ
中峯尊御真躰の御手より
連なっております。
この綱を握る事は
御尊真体と手を結ぶ事に
なりますから御運が開ける基となります】
と書かれております。
お参りされた方々はみな、この綱をしっかりと両の手で握って祈りを捧げておられました。
…もちろん私も。
十年に一度御開帳される中峰尊さま。
…神さまではないので御真体というのだなぁ。
(続き)
今回は十年に一度の御開帳です。
…この正面の天狗さんたちのから覗くのかしら?
奥に天狗さまの御像が見えますが、よもやこんな大きな、木製のお像ではないであろう。
そんな、
得意技『覗き』をそっと使っている私に、
「なんだかそろそろ何か始まるから急ぐように言われてるから、ここはまた後でにして」
と少し焦ったような口調で言う夫。
は?
何がなんだかわからないんですけど?
とはいえなんとなく夫もよくはわかってはいな口調ですし、とりあえずしたがってついて行きましょう。
御堂を出て。
おや?
先ほど御堂に入る時には気づかなかったのですが、御堂の前にスノコが渡してあるではないですか!
どうやらここで靴を脱いで奥へ歩くようです。
中峰尊さまの御堂をぐるっとめぐつて…。
おや、こんなところに入り口があったのですね。
ここは通常ですと御祈祷を受ける方々がお通しされる間です。
すでに何名かの方々が椅子に座ってお待ちです。
そして。
こちらにも紅白の善の綱が下げられています。
ここでもご縁をいただいて。
御開帳で来た私どもは、天狗さまの御像の手前で拝観料をお納めいたします。
受付をされておられるお坊さまに拝観料をお納めすると、お守をくださいました。
(続きます)
こんなに長いこと、ここに書かずに過ごしていたのか…。
体調は相変わらず良くはないけれど、仕事をしてはいないので焦りはない。
この間大きな検査をしたり。
大きな検査をするにあたっても、自分の内なる声がつぶやいていた。
してもしなくとももはや天命。
この検査の結果を受けても私の選ぶだろう道はノーコード。
それでも呼吸苦は除ける限りは除いて欲しいけど…。
かと言って人工呼吸器は要らない。
医療というのはあくまでも生きることを手助けしてくれるだけ。
生きたいと思う気持ちこそが何よりも強い。
巷では今日何かが起こるかもと、
もう何年も前の一個人の方の見た夢が大きくクローズアップされている。
お、夫は休みの日か。
あまり信じてもいないくせにそんなことが脳裏をよぎった。
ならば何かあっても共にいられるぞ、と思いきや、お泊まりで旧友に会いに行ってしまった 笑。
今日何事もなくともそれはただ単に二分の一の確率に過ぎない。
大切な人と共にいたいと仕事を全てキャンセルしたという芸能人がいる。
大きな病という辛いことを支えてくれた夫と共にいたいと思う彼女が私は好きだし、その旦那さまも私はとても好き。
格闘技をお仕事とされたくらいの方だから、そういう意味ではお強い方だが、
涙もろくて優しくて、何よりも妻を本当に心から大切に思っておられることが伝わってくる方だ。
共にいたいと思っても叶わないことなどそれこそ星の数ほどある。
その、たとえたった一人の人の、夢の話に過ぎないことであっても、
二分の一の確率をこの日信じて生きて良いと思うし、
なんならウチの息子のように知らずに生きている者もいる。
(あえて話題にしないから、もしかしたら流石に知ってはいるかもしれないが)
まぁ、〝ノストラダムスの大予言の日を過ごしてきた世代としてもだけれど、
もういつ天命が訪れてもおかしくはない年頃でもある。
強いていうならば、もっと断捨離しておきたいな。
来年はあちこちのお寺さんで御開帳となる年だしな。
…相変わらず煩悩は掃いて捨てるほどたくさんある。
大好きな神社さんにどうしても行きたくて、レスキュー薬を持ってひとり車を走らせました。
七月七日のこと。
夫は一度行ったところへはあまり関心が無いことが多くて、
ここはもう二度一緒に来ているし、行くといえば一緒に来てはくれるだろうけれど…。
ここ毎年、その神社さんへは夏詣として参拝させていただいており、平日にお参りすれば良い。
そうだ、こちらは笹を飾ってくださるから、ちょうど七夕の日に短冊をかけることができる!
心地よい気の満ちた、優しい気持ちになれる神社さん。
ああ、なんと気持ちが良いのだろう。
短冊は子どもたちと孫の健康と幸福を祈願して吊るした。
帰宅したとき、ここずっと体調が良くなかったのに、ここ近年ないくらいに身体が楽なことに気づく。
あ、そうか。
あの神社さんの御祭神の一柱は少彦名命さまだった。
なんとありがたいこと。
願わずとも見てくださっていてお力を与えてくださったのだ。
近いうちに御礼参りに参りましょう。
その時は熱中症のような症状となってしまったという、あの優しい人の体調が早く良くなって新たなお仕事に一日も早く慣れることができるようお願いしてまいりましょう。
早く良くなりますように、ここから祈ります。
お大事になさってください。
(花手水)
日本という国は、八百万の神がおられ…そこへ御仏がお越しになられた。
神がおられるのにと言った者。
神さまに救われなかった者を救うのが御仏であると説いた者。
その異なるところから
年月をかけて
自然と、
神道と、
仏教とが寄り添うようになっていく。
このなんとも特異な考え方に一つの宗教を信じる国の人たちは驚くようだが…
私はこの先人の柔軟な心に感謝しかない。
神を崇め
自然を崇め
御仏の教えに心のあり方を学ぶ。
そんな教えの中、釈迦は四苦を説く。
〝産まれ落ちたときから
苦しみが始まる〟と。
この世に生を受け、
老い、
病にかかり、
そして死を迎える
生命の流れのなか
必ず経験する苦しみ、だと。
生まれてきたことすらが苦しみ?
…少し切なくなる
たしかに産まれ出づるときの
苦しみは大きかろう。
ただ、
そのときのつらさや痛み、苦しさを
覚えている者はいないであろう。
老いたと思うことは日々の暮らしの中どんどん増えていくし
病の苦しみも味わうようになった。
生老病死
わずか四文字でその苦しみはあらわされるけれど
人は一生をかけて
それを味わい生きていく。
この四苦のほかにも苦しみがあると
お釈迦さまはおっしゃった。
愛別離苦
怨憎会苦
求不得苦
五陰成苦
人が生きていく上で味わう精神的な苦しみ。
うん、…味わった。
味わって生きてきた。
…味わって生きている。
まさに生きている上で避けられない苦しみだ。
不安や孤独…さまざまな苦しみがあった。
それはこれからも生きている限りは付いてまわるであろうことは、
今までの生きてきた道を振り返らずとも想像される。
でもそこには喜びもあった。
だから
能天気な私は
苦しみもあろうが喜びもあろうと
生きてきたし
生きていく。
御仏の教えを伝える仏教は、これらの苦しみを言葉としてあらわし伝えただけではない。
苦しみを受け入れること、
その苦しみから解放されるための智慧と方法を教えてくださっている。
…ただなぁ。
私のような煩悩の塊の愚者には
なかなかむずかしい。
おそらく生きている間には
その〝域〟には
達することは不可能であろう。
だから私は
今日も苦しむ。
埼玉県の安楽寺さんの年一回のご本尊さまの御開帳日であるからと、夫が有休をとってくれ、
「夜中の二時から御開帳されるというから、もし行きたければそのときに間に合うように行ってもいいし。
調べたら一時間半かからずに着くらしいから、夕飯食べて早めに仮眠取って行けばいい」
こちらは吉見観音さまと呼ばれ、その御開帳の日の参拝は早い時間であればあるほどご利益が大きいと言われているといいます。
しかしながら私どもは初めての参拝です。
明るいときと異なり、道の案内板等も見えづらいでしょうし、いくらライトアップされていたとしても石仏さまなどは見逃してしまいましょう。
ゆっくり明るくなってから、と、それでも七時半くらいには家を出たのですが、この日は平日。
この時間帯は通勤通学のラッシュ時にあたっており、なんだかんだ二時間かかってしまいました。
真夜中の二時から御開帳されていたということで、真夜中にはさぞ混んでいたでしょうに、この時間になると駐車場もガラガラに空いています。
そしてその駐車場の脇にはたくさんの石仏さま♡
暗いうちに訪れていたならお会いすることはできなかったことでしょう。
参道に露店のお店は二つのみ。
厄除け団子のお店が立ち並ぶ、と聞いていたのに…。
時間帯のせい?
それとも時代による減少?
参道沿いに店を構えるお茶屋さんでは
『厄除け団子売り切れ』
『本日休業』
との貼り紙が。
私の厄はどう祓えばいいのでしょう (;ω;)
参道沿いにあるおうちから、疲れたお顔をされた男の方が出て来られました。
…そうだよなぁ。
普段なら静かであろう道沿いが、一年に一度のこととはいえ、夕べは夜中中大賑わいでしたでしょうから。この頃は季節を先取り夏日が続いておりましたし、眠れない夜、さぞ疲れもたまりましたことでしょう。
石段の上、山門が見えてまいりました。
坂東観音霊場第十一札所【岩殿山安楽寺】さん。
朱色をされた仁王さまが来るものを見張っておられます。
「初めて参拝させていただきます」とご挨拶を申し上げます。
おや?
山門にいろいろな図柄の蟇股です。
これが真夜中の人出の多い頃であったら、気づきもしなかったことでしょう。
ひとつひとつに物語がありそうです。
明るくなってからでも充分なご利益です。
年一回の吉見観音さまの御開帳は六月十八日のことでありました。
山門の彫刻をゆっくりと堪能して。
(…どうせ帰りにもまたそこをうろつくくせに)
山門をくぐると目に入ってくる情報の大変多いお寺さんであるにも関わらず、まっすぐ前の大香炉と、そこからまっすぐ石段の上の御本堂に、心ごと引きつけられてそわそわワクワクいたします。
なんと慈悲深くお力の強い観音さまでありましょう。
夫もそうなのかわき目もふらず真っ直ぐ大香炉へと向かっています。
…ちがうよ〜。
まずは手水舎だよ。
…私も真っ直ぐ前だけを見てそこを目指していたはずなのに、ある地点でふと足が止まり、左側にごくごく自然に目を向けました。
ああ、手水舎!
見えない力がそこに働いているかのようでした。
すっかり明るくなった境内、まさに龍が守っているとしか思われない手水舎がありました。
手を浄めて。
大香炉を目指します。
こちらはお線香に火を着けるのに昔懐かしい練炭を使うのです。
お線香を買い求めるのも私には妙なこだわりがあって、自分のお財布から自分の分だけお払いすることにしています。
神さまや仏さまに捧げるものは全て自らのお財布から。
…働いていない私の支払うお金の出どころは夫が働いて得たお金なのに、ね。
そんな事を考えながらお金を納めていると、年若いお坊さんがあらたな練炭をお持ちになりました。
「ようこそお参りくださいました。こちらの方が早く(お線香に)火が付くかと思うのでよかったらお使いください」
…なんと心のこもった対応をなさるお寺さんでありましょう!
夜の二時からの御開帳。
それに向けてもう数日前から動いておられ、きっとこの日は前日から寝ておられないでありましょう。
それなのにこの爽やかで、心のこもった対応。
暗い真夜中からたくさんの人が訪れ、その対応にあたられたこの方は、疲れていたり、眠かったりするかもしれない、まさにそんな時間帯にも関わらず、
全身全霊相手の心に寄り添った、対応をなさるこの方に深い感動を覚えました。
神対応という言葉がありましたが、これはまさにそんな対応。
心を浄めてくださる対応を受けて、御本堂への石段を登ります。
真っ青な空が御本堂の上に広がっています。
五色の幕のかかる御本堂へ一歩、また一歩。
(続きます)
(埼玉県吉見観音さまの続き)
だいぶ間があいてしまいました。
御本堂へお参りさせていただきますところから再開させていただきます。
御本堂の中に置かれた御賽銭箱の前に、玉垣のような柵があり、
ここに安産や子育て満足といった祈りを込めた小さな前掛けをかけるようになっています。
手作りしてきた物でも、こちらで購入した前掛けでも良いようです。
ちなみに今回のお参りの際の前掛けをお授けいただいたときのお納めする代金は七百円と大変良心的なお値段設定でありました。
ご許可いただけるようなお寺さんなりがあればお地蔵さまのお首に御奉納という形で前掛けを掛けさせていただきたい、というのは私のかねてからの小さな夢であり望みであります。
ええ、夫さえいなければきっとこちらでこのお掛けを購入したことでしょう。
そうすればこれを元にお掛けを作れます。
…まぁ、あきらめましたけれど。
たいがいのことは大目にみてくれますので、購入したところで、せいぜい「それをどうするの」と聞く程度でありましょうが、ね。
御本堂前、御開帳されておられる聖観世音菩薩さまとは細紐で繋がれており、お参りの際にはその紐を持ち、ご縁を結んでいただけるようになっておりました。
若い男の方が熱心にその紐を握って長いこと祈っておられたのがとても心に残りました。
ご自分のためでしょうか。
それとも奥さまとか、あるいは奥さまとそのお腹にいるまだ見ぬ我が子のためにでしょうか。
それとも親御さんのため?
彼の敬虔な祈りは観音さまにきっと届いたことでしょう。
え?わたし?
わたしは初めて参拝ができましたことを御礼申し上げました。
(続きます)
(続き)
吉見観音さまの御本堂の内にも入らせていただけ、より近い所から拝観させていただくことができました。
ありがたいことでございます。
御本堂内は撮影禁止とありましたが、御開帳されておられる観音さまを含めた境界の内側とのことで、
左甚五郎作といわれる欄間彫刻【野荒らしの虎】の撮影などはご許可がありました。
『野荒らしの虎』は夜ごと御本堂を抜け出しては付近の田畑や家畜を荒らし、村人に右足を槍で突かれて血まみれになって帰って来たという伝説が残ります。
…なるほど、欄間から尻尾がはみ出して、躍動感あふれる虎であります。
御本堂内の天井にはおびただしいという表現がぴったりなくらいに千社札が貼られていました。
…かつてはこのようなことすらもが許されたのですね。
今はたいてい千社札禁止ですし、お寺の御本堂の内にハシゴなどを持ち込んで、ということになりますからね。
お寺の、高い天井です、足場などがなければ到底不可能ですもの。
このあと御本堂では御祈祷が執り行われました。
外陣にいる者に対しても退出するようにおっしゃることなく、ありがたくその読経を拝聴させていただくことができました。
ただ…拝観の方の中に大変失礼な方がおりました。
今回御開帳されておられる観音さまの真正面に陣取って、観音さまに足を向け伸ばして座り、脚を組んだり、
まるでお家のリビングでテレビでも観ているかのような気楽さで参列されている女の方がいたのです。
…もちろん足がお悪くて足を伸ばしてしかお座りになれない方もおられます。
しかしながら彼女たちはさにあらず。
五十代前半から六十代後半といったところの、十中八九日本の方。
そのうち飽きてしまったようで途中退座されました。
たとえ信仰心など無いにしても、その場でのマナーというものがあると思います。
まあ、観音さまの御前でたとえ内心でとはいえ苛立つ私もまた未熟者。
そんな私の苛立ちも九条錫杖経に合わせて振られる錫杖の音できっと祓っていただけました、よね?
観音さまの右側のお不動さまの御前でのお護摩も焚かれておりましたし。
お護摩の炎、お不動さまの炎はそうした穢れを焼き祓い、焼きつくすといわれています。
観音さま、こんな未熟な私の心が少しでも穏やかなものとなりますよう、お導きください。
(続きます)
独身税とかいう税金の導入が進んでいるようだ。
わが家には独身の息子もいる。
今後のことを考えると、不安もある。
不安しかない。
NHKの綾瀬はるかさんのドラマが観られないくらいには不安だったりする。
独身というだけで、何故そんなに国にお金を搾り取られなければいけないというのだ。
独身というのは罪にあたるというのか?
そもそもどこからどこまでが独身なのだ?
ご近所に八十を超えた生涯独身男子がおられるが、その方も独身税を払うのか?
収入のある独身者がターゲットなのか?
一人悶々と怒っていた。
仏教徒ではないが、法句経というお経の偈文に
『人間は、共に行動する仲間に影響を受けやすいもの。
聡明な伴侶が見つからず、智慧を持っていなかったり、志が異なっている人と旅をするのなら、勇気を持って孤独に進むほうが良いものです」
〜愚かな者を道連れにしてはならぬ〜
とあるくらいだ。
まあ某総理はキリスト教徒で洗礼も受けているようだから、お経を持ち出したところで痛くも痒くもないであろうが。
…そもそも彼には痛覚がない気がする。
で。
本日はこの〝独身税〟なるものを調べてみた。
調べてみたらなんのことはない
【子ども・子育て支援金制度】のことをいつしかそう呼ぶようになっていたということらしい。
まあ、結局のところ独身者の納める額はどうしても大きく、そんなところから独身税と呼ばれるに至ったらしいが…。
ゆえに件のご近所さんは当然支払う事はない。
ヘンテコな表現をして注目を集めるのが目的なのか?
全くもって…わからない。
独身者に対して手厚い制度はできるのか?
無いんでしょ?
そうそう、小泉元首相は収入のある独身者だね。
…そんなちっぽけな税金を納めたところで痛くも痒くもないだろうが。
ほんとね。
ちゃんと国民を、あらゆる方面から見てよ!
お金だけ搾り取って、取りこぼすとかすんなよ!
あーヤダヤダ!
地蔵菩薩さまは大地を蔵にしている仏さま。
奈良時代には虚空蔵菩薩と対で祀られていたという。
虚空蔵菩薩は虚空、つまり天を蔵にしており、地蔵菩薩は大地を蔵にしている。
そして平安時代には【抜苦与楽(ばっくよらく)】の仏として信仰されるようになる。
苦を抜き、楽を与えてくれる仏さま。
やがて、地獄に堕ちた衆生=人たちでも救ってくれるという信仰が強くなっていく。
お地蔵さまはどこにいても救ってくださる仏さま。
救いを求めて、
大切な誰かを救って欲しくて、
あるいは救っていただいたお礼として
多くのお地蔵さまの像がつくられた。
明治の時代を経なければもっともっと多くのお地蔵さまの像は存在したであろう。
同じ立像であっても、よく見るとお地蔵さまの片足が一歩前に踏み出された像もある。
お座りになられる像にあっても、片足は下げて、すぐにでも歩けるようにされている像がほとんどだ。
これは救いを求める声を聞いたならすぐに動けるようになさっておられるお姿をあらわしたからだ。
…生きることは苦しいこととお釈迦さまは説いておられる。
生老病死の四苦をはじめ、八苦、…あの四苦八苦といわれる言葉の始まりは仏教から生まれている。
別れたくないと思う者と別れなければならない苦しみ。
出会ってはならない者と出会ってしまう苦しみ。
などなど…。
あなたが苦しくて声を上げたなら、そこに来てくださる御仏、お地蔵さま。
どうかご自分の苦しいときは、他者ではなくご自分をこそ見てあげてください。
それは決して甘えなどではありません。
ご自分をこそ抱きしめてあげてください。
あなたの優しさも苦しみも、みな、
御仏は、
神さまは、
見てくださっておられます。
そして私はここから
風に頼んで
エアハグを送るよ。
戦後八十年
私とて戦争を知らない世代だ。
語り継ぐといっても
それは
体験された方の生の肉声を
お聞きして初めてできることだと
思うのだ。
しかしながら
時は流れる。
今、
世界は
そして日本は
人の手による自然破壊で異常気象が起き、大きな災害も起き、
それにより食べ物という生きていくため欠かせないものにも大きな支障がきたされている。
富める国は自国のために、保身に動き出している。
日本は…
本来国民のために国のためにその職に就いた者が、もはやそう動いてはいない。
歯車が狂い出していると思うのは私だけではないであろう。
忘れてはならない。
忘れてはいけない。
人の命の重み。
かの人は、平和式典にどんな思いを持って臨むのであろう。
いろいろなお寺さんを巡っております私。
季節や仏教行事の折にふれて、同じお寺さんを参拝させていただきますことも多くありました。
お釈迦さまはご自分の亡くなられたあと、仏教、=仏の教えがうまく伝わらず世が乱れることを予想しておられました。
それこそ仏の道を説く僧からがその教えから外れてしまうことすらも。
まさに今はその、お釈迦さまが憂いた時にあたる時代。
悲しいかなそれは的中していると思うしかないことに出会ってしまうことがたいそう多い。
それは私が仏教徒でもなければ、檀那寺も持たないから、なのかもしれません。
でもそれで仏教に不信感を抱いて仏教離れしていったら、言葉はたいへん悪いでしょうが、営業活動になっていませんよねぇ。
…悲しいことにそれすらがわからないらしい。
本堂御内陣のご本尊の前に灯した蠟燭の火を口で吹き消したりはまだ序の口で。
ここを私どものお寺と定めようかとすら思っていた人格者の僧が、人の道を外れてしまったり。
法具を地べたに置いたり、箱に投げ入れたり、人に殴りかかるかの悪ふざけをしたりポスターの顔面に五鈷杵と呼ばれる尖端を突きつけたり…。
法要の合間の時間に「あの会社はもうおしまいだよね」と名指しで話したり。
…別にね。
聖人であることを強いたりはしないです。
生きた人間ですから。
でも仮にも僧侶という職業人であるならちゃんとその格好をして、自らの治める寺で、法要の合間とはいえ、人目ある時くらいは【演技】してよ!
…そういった意味では法を犯した僧侶は少なくとも僧としての仕事中はそんな素ぶりを見せたことのない、檀家以外の者からも慕われ敬愛された人物であったくらいでしたよ。
そんなことを見る機会、聞く機会を与えられてしまって、なんかちょっと…興醒めしているところがあるのが否めない。
檀家ならば見ない?見せないかもしれないし、逆に檀家ならばもうそういう寺、そういう僧だと認識した上で付き合ってきている歴史学あるのかもしれないし。
御仏の教えは決して揺るぐものではない、そう自分に言い聞かせて言い聞かせている、まさにその最中、であるのです。
もちろんそうでないお寺さん、僧侶も多くおられます。
その方のおられるお寺をお訪ねしては、自らの思いを修正中というのが正直な実状です。
…だいぶ間が開いた事もあり、どうしようか迷いもしたのですが、
吉見観音さまはある方とつながりの地。続きを書きたいと思います。
(吉見観音さまの続き)
御朱印を拝受させていただくため納経所へと向かいました。
穏やかな佇まいの庭園を進んでまいります。
ここを歩くだけで癒される、そんな空間でありました。
と、向こうから年若いお坊さま。
やわらかな所作で道をお譲りになりながら、
「ようこそお参りくださいました」
私、この日何度こう言っていただいたのだろう。
人の心に残るのは、人の心ある言葉であり、人の優しさ、思いやり。
そんなことを、身についた普段通りの行いで私にお伝えになるお坊さま。
なんと良いお寺さんでしょう。
納経所に着き、係の方が渡された私の御朱印帳を開いて捺印なさろうとしたまさにその時、
あの、心の臓をつかむかのような緊急警報Jアラートが鳴り響いたのです。
(納経所の建物は新しい。
この建物が倒壊するようならそれはもはや地震の規模の問題。
すぐに外へと出るのも可能な位置にはいるけれど、
どこをどう動けば良いか、初めて訪れた場所ではなかなか判断も難しいから、このあとどうなるかもう少し様子をみよう)
怖さは全くといっていいくらいありません。
いたって冷静にそんなことを考えていると、Jアラートに続いて女の方の声でアナウンスが聞こえてきました。
「緊急地震速報、大地震です」
夫は様子を見に外へ出て行きました。
(ほう、そばには居なくていいんだ…)
冷静にそんなことまでを考えていると、
「震度5弱の地震です」
と再びアナウンス。
?
…おかしい。
私のiPhone鳴ってない。
何故?
さっき御本堂を出たあとマナーモードは解除したはず。
歳で指の力が足りなかった?
いや、そもそもマナーモードであろうとJアラートは鳴るはず。
夫のスマホも鳴ってない。
…これ、なんか変。
なんかおかしい。
そう思ってiPhoneを開いてみたところ、やはり私のものにはJアラートの受信履歴が無い!
「これは訓練放送です。これで訓練放送を終わります。」
は?…訓練でしたか。
ま、一般人には言われませんか
…訓練にならないし。
吉見観音さまのご利益は即効にして絶大でした。
…穏やかでしたでしょ?私
(続き)
【吉見観音】さまは正式には【岩殿山安楽寺】。
今から約1300年ほど前、行基菩薩が岩窟に観音像を安置したのが始まりといわれているといいます。
平治の乱後、源範頼がこの地を領するようになり、本堂と三重塔を建立しました。
範頼の館跡とされます。
…ええ、どこかの歴男子がやたらと解説をしておりました。
しかしながらこの時の伽藍は天文年間(約450年前)の上杉憲政と北条氏康の松山城合戦に際し、すべて焼失してしまいました。
現在の本堂は寛文元年に再建されたものであり、五間堂の平面をもつ密教本堂です。
また、堂内の間には左甚五郎の作といわれる「野荒しの売」も納められています。
三重塔は本堂よりもさらに古い覚永年間の創建といいます。
現在の塔は総高24・3メートルとのこと、
それだけでも十分高い塔ですが、かつての塔はその倍の48メートルあったと伝えられるといいます。
仁王門は元緑十五年に再建された三棟造りの八脚門という建築様式をもち、内部に仁王像二体が安置されます。
三重塔は修復や保全にお手を加えておられるのでしょうが、全く古さを感じないどころか、新しいものにさえ見えます。
御本堂よりも古いものには到底見えません。
この塔の説明板に穏健な雰囲気の塔とありますが、まさにその表現がぴったりする塔であります。
中には誕生釈迦尊像が安置されているといいます。
そのお姿を見ることはできませんが、つい見えないそのお姿を想像しては重ねて見上げている私でありました。
(続きます)
【平和への誓い】
いつかはおとずれる、被爆者のいない世界。
同じ過ちを繰り返さないために、多くの人が事実を知る必要があります。
原子爆弾が投下されたあの日のことを、思い浮かべたことはありますか。
昭和20年(1945年)8月6日 午前8時15分。
この広島に人類初の原子爆弾が投下され、一瞬にして当たり前の日常が消えました。
誰なのか分からないくらい皮膚がただれた人々。
涙とともに止まらない、絶望の声。
一発の原子爆弾は、多くの命を奪い、人々の人生を変えたのです。
被爆から80年が経つ今、本当は辛くて、思い出したくない記憶を伝えてくださる被爆者の方々から、直接話を聞く機会は少なくなっています。
どんなに時が流れても、あの悲劇を風化させず、記録として被爆者の声を次の世代へ語り継いでいく使命が、私たちにはあります。
世界では、今もどこかで戦争が起きています。
大切な人を失い、生きることに絶望している人々がたくさんいます。
その事実を自分のこととして考え、平和について関心をもつこと。
多様性を認め、相手のことを理解しようとすること。
一人一人が相手の考えに寄り添い、思いやりの心で話し合うことができれば、傷つき、悲しい思いをする人がいなくなるはずです。
周りの人たちのために、ほんの少し行動することが、いずれ世界の平和につながるのではないでしょうか。
One voice.
たとえ一つの声でも、学んだ事実に思いを込めて伝えれば、変化をもたらすことができるはずです。
大人だけでなく、こどもである私たちも平和のために行動することができます。
あの日の出来事を、ヒロシマの歴史を、二度と繰り返さないために、私たちが、被爆者の方々の思いを語り継ぎ、一人一人の声を紡ぎながら、平和を創り上げていきます。
今年の広島の平和式典でのこども代表のことばです。
もう私の文章なんて、ここに書くのをすらやめたくなるくらい立派だし、その立ち居振る舞いの立派なことといったら。
この子たちの素晴らしさもなのだけれど、今の子供たちって、堂々としていて、テレビのインタビューなどでも立派な受け応えをするし、恥ずかしがったりしないで普通に会話するかのようにカメラに向かうんだよなぁ…。
この素晴らしい子供達の未来を守ろうよ。
心からそう思う。
(吉見観音さまの続き)
三重塔を拝し、御本堂裏手へとまわります。
御本堂の裏手には石垣が組まれ、その一角、ちょうど御本堂の中央の真裏にあたる位置に洞が造られています。
輪違の御紋の石碑がまるで表札のように置かれています。
この輪違の御紋はこちらのお寺さんが属する真言宗智山派の宗紋です。
そして。
この洞の内には石造りの大日如来さま館お祀りされておられました。
お詣りさせていただき、さらに進むと石段の上へとのぼる石段があります。
のぼっていくと鐘撞き堂があります。
はて何故このような奥に?
高台にある方がより遠くまで音が響くから、なのでありましょうか。
先の大戦で供出され新たに造られた梵鐘のようです。
どれだけ無駄な労力を使って全国からこのような大きな梵鐘をかき集めたのでしょう。
そして無駄な労力を使って、このように立派に造られた歴史ある梵鐘を溶かし。
あるいはそれすらも追いつかず、集められただけで放置され、帰る先がわからなくなった梵鐘が雨ざらしになって錆びていったことでしょう。
帰る場所がわかったところで、その運搬にかかる費用や労力はもはや国の手からは離れており。
あるいは溶かされ、あるいは行方知れずのままとなって、
鐘楼だけとなったお寺さんをどれだけみてきたことか…。
再建にあたっては莫大な金額のお金が必要で、さらには鐘を造る専門職も激減した中でのこと。
鐘一つとってもいかに戦争で失われたものが多かったかが伝わります。
美しい音色の鐘。
素晴らしい技術をもって造られた梵鐘。
鐘を造る技術をもった技術者。
そして…人類はそれでもまた戦争を起こしています。
そんな思いをもって梵鐘を拝みます。
鐘撞き堂をぐるっとまわると八起き地蔵尊のお堂が眼下に見えます。
八起(やおき)地蔵尊とは
七難を克服し、七福を授かり幸せを築くことができるようにと建立されたといいます。
私たち衆生の願いを叶え、悩み、苦労を代わって受け、救済してくださるといわれるといいます。
やはり手には輪違の御紋をお持ちです。
七難くらいではまだまだ私の悪いところは到底とり去ることはかないませんがありがたく拝ませていただきました。
七福は…子どもたちにお授けくださいと、お願いしました。
(続きます)
(続き)
八起き地蔵さまの参拝をし、三たびのご本堂前。
参拝のご縁をいただきました事を御礼申し上げ、石段をくだります。
青銅製の半跏坐のお地蔵さま。
錫杖を手に、何か事あればすぐに立とうとされておられる、なんともありがたく尊い地蔵菩薩さま。
大きな、同じく青銅製の阿弥陀如来さま。
『吉見の大仏』さまと呼ばれるようです。
新しいものに見えますが寛政二(1790)年に鋳造されたものといいます。
この阿弥陀如来さま、山門をくぐるとその大きく威厳あるお姿に目がいき、ついお参りに参じたくなるのですが
自らの心を律して、まずは御本堂へと向かいましたもの。
お詣りのマイルールは『まず御本堂、まずご本尊さまへ』なのであります。
大きな宝篋印塔。
境内参道を左右に対で置かれております。
お堂の内にある六地蔵さま。
…お地蔵さまが多く祀られるお寺さんであります。
うーん。
今までで見た中で一番紙が貼られておられます。
中にはもう衣のように御札を貼られたお地蔵さまもおられました。
どこかでお授けいただいた御札?
いや全文手書きのものから、印刷して名前と日付だけ手書きされた物までいろいろあります。
決まった文言があって、それを個々に用意してこうして石仏さまに貼らせていただく風習がこの地にあるのだと思いました。
私はこうした深い信仰のある地がとても好き。
もはや道端の石仏さまを見かける機会すらを失ってしまった自らの住む町にあると、こうした風習は憧れでもあります。
いつかこの御札を携えて再びこの地を訪れたいとすら思うくらい。
参道を超え。
御本堂と三重塔を見護るかに立つ弘法大師さま。
十数段の石段を登ると御堂がふたつ。
石段真正面は薬師堂。
覗きみますと、中央にはたいそう立派な御厨子があり、左右を十二神将さまが護っておられました。
…御開帳があるのかしら?
そうしたらその日にもまた参拝させていただきたいです。
薬師堂むかってみぎてには百観音さまの安置された観音堂。
お参りさせていただきありがとうございました。
一番心に残ったのはやはりお寺の方々みなさんが、参拝に訪れた人々に道を譲りながら、
「ようこそお越しくださいました、ごゆっくりお参りください」
とおっしゃっておられたこと。
また参拝できますように。
お地蔵さまは菩薩ですので、本来は観音さまや弥勒菩薩さまと同じ菩薩の格好をしておられますが、
我々衆生を救いたいというお気持ちから頭を丸め衣と袈裟を着ておられるといいます。
お地蔵さまといえばば子供を守ってくれる「ほとけ様」としてよく知られますがでありますが、大人にとっても大変ありがたい存在です。
地蔵菩薩の信仰には「十益十福」がある言われているといいます。
地蔵菩薩を信仰すれば
1、女人泰産(良縁で安産になる)
2、身根具足(健康で健全な体になる)
3、除衆病疾(病気や怪我から逃れ回復する)
4、寿命長遠(健康で長生きする)
5、聡明智恵(知恵が発達し学問に優れる)
6、財宝盈溢(商売が繁盛し財に恵まれる)
7、衆人愛敬(人に好かれ仲良くなる)
8、穀米成熟(作物が実り豊かになる)
9、神明加護(神仏の護りがあり家内安全でいられる)
10、證大菩提(大きく豊かな心が日々の幸福を招く)
という「十種の福徳」の功徳があるということ。
仏教徒でもない私には正直、信仰する、という根本的なことすらが理解できていない、そういった自覚があります。
心が八方塞がりで苦しく過ごしていても、その心をすら救ってくださるというその信仰というもの自体がよく理解できず、その縁がいただけないということはきっとその資格がないのだろうと思ったりもします。
それでもお地蔵さまのお優しいお顔に癒されます。
そしてそんな時間を持てるということはお地蔵さまのお力の強さなのでありましょう。
今は、そのお力に気づかせていただいたことに感謝し心に描くお地蔵さまに手を合わせます。
十もの福徳は希望いたしません。
仏教で密教と呼ばれる教えのなかに御真言というものがあります。
私は檀那寺をもたないので、ごくごく一部の、上っ面な知識しか無い者でありますので、ここでお経についても御真言についても詳しく書くつもりはないのでありますが…。
お地蔵さまなどの御真言はWikipediaにも挙げられるくらいなので、もし中途半端にここに綴ったものがお気になりましたなら、どうかWikipediaをご覧いただければと思います。
そのお地蔵さまの御真言の一部に
『カカカ』
とお唱えするところがあります。
それははお地蔵さまの種子、梵字のha(ハ)であるといいます。
それを、明るい笑い声、だとおっしゃったお坊さまがおられました。
そのときは私のような仏教徒でない者に親しみを持たせようとおっしゃった言葉遊び的なものであろうと思っていたのですが、実はそれは本当なのだと別のお坊さまに教えていただきました。
お地蔵さまのこの〝かかか〟が明るい笑い声であるとするのは、お地蔵さまの希有なる忍耐力を表わしているのだといいます。
踏まれても耐え、笑顔で救おうとする対象を支えることのできる大地のようなお徳だと。
地の蔵
それがお地蔵さまであります。
虚空蔵菩薩さまは
虚空に蔵を持つ菩薩さまだといいます。
そこからお智慧をお授けくださるという…。
前回、御真言について密教でお唱えされるものと書いた。
これについては宗派もあり、さらには僧一人一人の考え方でだいぶ扱いが異なるようで。
御真言は師から弟子へと授けられて初めてお唱えできるものであるとすることもあり。
あるいは僧から教えていただいたり、
御真言の書いてあるものが壁などに貼ってあったりするものがあれば、なんの修行も積んでいない、
なんなら私のように仏教徒でもない者がお唱えしても良いという、ありがたい説もある。
私は根っからのビビりなので、長い歴史ある宗教の、御真言とされる言葉に込められたものを簡単にここに書くことができないくらい、この御真言というものの持つちからを、パワーを信じているところがある。
もちろんむやみやたらにお唱えもしないのだが。
宗派によってはお念仏をお唱えする。
もちろんこの文言を知らないわけではないが、お寺さんでお唱えするよう言われた時にしか唱えない。
これはその宗派の教えを檀家として授けていただいた方ならばいざ知らず、私はそうではない。
そもそも極楽浄土へそうは簡単に行かせてもらえるような人物ではない。
そう世の中は甘くはないということだけは理解しているのだ。
…あれ?
極楽浄土はあの世のことか。
うーむ。
と、とにかく、このお念仏をお唱えする宗派は浄土宗・浄土真宗、あるいはここから派生した宗派である。
私はこのお念仏をお唱えする宗派の法事・法要に参列したこともなく、いわんや法話をお聞きしたこともない(…と記憶している)
だからその真意もわからない。
どうして勝手に〝お念仏〟をお唱えできようか
そもそもお念仏をお唱えするだけで極楽浄土へ行くって…どうよ。
(続き)
そんな法然、親鸞の教えは浄土教といわれる。
人は、阿弥陀仏の、生きとし生けるもの(衆生)を救うという願い(本願)により救われるというものである。
具体的には、来世に阿弥陀仏の極楽浄土に生まれ(往生)、悟りを開くというものである。
拠り所となるお経は『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経」で、『浄土三部経』といわれるが、
一般にはまずお念仏をお唱えする。
平安時代に現れた風獄の著した『往生要集』によって、浄土教の信仰
は盛んになり始める。
そこには厭い離れる穢土(汚れたこの世)と、よろこんで求める浄土が説かれている。
しかしながら
『往生要集』により、地獄の恐ろしさが強調され、浄土を求める心が起こったとしても、
そこに生まれるには阿弥陀仏やその浄土を観想するという難しい行法が必要とされたため、多くの人々にとっては阿弥陀仏の救いは、まだ手の届かないものであった。
日本は平安末期から鎌倉時代にかけ、時代はまさに地獄のような様相となる。
仏教ではお釈迦さまの在世から離れるにしたがい、正法、像法、未法と
仏法が衰退していくとが他ならぬお釈迦さま本人が言い残している。
正法とは教説(教)とその実践(行)とその結果(証)の三つが備わる時代で、釈尊の教えが広く行われている時代である。
像法とは教と行だけが備わる時代で、釈尊の教えに像たものが行われる時代である。
未法は行も証も失われ、ただ教のみのこる時代で、仏法の衰退した時代である。その内容はしばしば五濁悪世と表現される。
五濁とは
劫濁(時代、社会の汚れ)、
見濁(誤った見方、思想の汚れ)、煩悩濁(頻悩が盛んになること)、衆生濁(衆生の心身の資質がおちること)、
命濁(寿命が短くなること)、
であるという。
まさに未法到来を示すかのようにな地獄のような凄まじい時代であったといい、それはその後も歴史の中で繰り返し繰り返されることとなる。
お釈迦さまが亡くなり、弥勒菩薩が世に現れるまでの長い長い間が末法の世である。
その間実に五十六億七千万年。
その間衆生を救うべく世に遣わされておられるのがお地蔵さま、地蔵菩薩である。
(続き)
法然の生まれ生きた時代、人々は現世の地獄を生きていた。
そして法然もまたその一人であった。
法然が九歳の時、父親は日頃から対立関係にあった者の夜襲を受け非業の死をとげている。
法然は目の前で父親が殺されるという地獄を見たのである。
臨終に際し、父は法然に、
「もしもお前が恨みを抱き、仇を討ったら、その子供もまたお前に恨みを抱き、仇を討つだろう。
だから恨みを捨て、出家し私の菩提をとむらい、悟りを求めなさい」
といったという。
これが法然の出発点である。
法然は十三歳で比叡山に登り、学び、修行に励んだ。
そして修行をしつつ考えたのであった。
『仏像や塔を造ることを本願とするなら、貧窮困乏の者は往生する望みを全く絶たれる。しかも現実には、富貴の者は少なく、貧賤の者が非常に多い。
もし智慧や才能のすぐれていることを本願とするなら、愚かな、智慧のない者は往生の望みを全く絶たれることになる。しかも現実には、智慧ある者は少なく、痴愚の者が非常に多い。もしよく見聞し、学問をすることを本願とするなら、見聞できず学問のない者は往生の望みを全く絶たれる。
しかも現実に多聞の者は少なく、少聞の者が非常に多い。も戒律を守ることを本願とするなら、破戒無戒の人は往生の望みを全く絶たれる。しかも現実には持戒の者は少なく、破戒の者は非常に多い』
法然の生きた時代は、貧しい人、智慧のない人、学問のない人、破戒の人がほとんどであった。
富んでいる人、智慧ある人、学問のある人、戒律を守る人だけが救われるとしたら、ほとんどの人は救われないということになる。
法然は考えた。
仏の慈悲とはすべての人が救われるはずなのに、これはおかしいと。
ここから法然の長い求道が始まるのである。
(続き)
法然は十八歳で比叡山を下り、
その何年か後、唐の善導(中国浄土教の大成者)の影響のあった永観、珍海の浄土教にふれる。
善導の「観経疏」の
『一心に専ら弥陀の名号を念じ、行住坐臥、時節の久近を問わず、念々に捨てざるを、是れ正定業と名づく、彼の仏の本願に順ずるが故に」
(一心にもっぱら阿弥陀仏の名号を称え、行住坐臥に、時間の長い短いを問わず、常に忘れない。これを正しい行法という。これはこの阿弥陀仏の願にかなっているからである)
という一文に遭遇して、
『口に南無阿弥陀仏と称えれば必ず極楽浄土に往生できるのだ』
という確信に至る。
この教えは専ら念仏を修するところから、修念仏の教えと称される。
法然四十三歳の時のこと、浄土宗の開宗の年ともされている。
口に南無阿弥陀仏を称えれば誰もが往生できるという法然の説いた教えは当時、破竹の勢いで人々の中に広がっていった。
救われたいと願う人々が、ひたすら南無阿弥陀仏と称えていたともいわれ、しかも、その数は、推測の域をでないが、当時の人々の半数以上であったように考えられているという。
それほど、念仏は生き生きとして、人々の心をとらえたのである。
方丈記の時代である。
羅生門の時代であった。
人々の救いを求める思いは藁をもすがったであろう。
そこにしか光を見出せない。
見出せなくとももはやそこにしか光がない時代であったのだ。
南無阿弥陀仏という念仏に秘められた過去を紐解き、
地獄のような現実を生きる人々は、極楽往生も夢見たろうが、少なくともいまよりはマシな未来を、来世を望んだであろうし、
その人々をなんとか救いたいと一心に経を読み、学んだ一人の僧をそこに見たのであった。
浄土宗。
なるほど法然上人の詠む歌はだからこんなにも優しく心に染み入るものであったのか。
こうした学びを経ても、私がこの南無阿弥陀仏をお唱えしたところで極楽に行けるなどという甘い考えには至らない。
けれど人々を救わんとした一人の僧を心からありがたいと思い、それに救われた多くの人々の心をも心から良かったと思うのであった。
学ぶということはいくつになっても大切だということもまた学んだ今回であった。
ありがたいことである。
なん年前だったでしょう、『トイレの神様』という歌が大ヒットしました
…あまりその内容はよくは覚えていないのですが 笑。
私の場合、おなかに子どもがいるとき、母親に
「トイレ掃除をするとキレイな子が産まれるんだよ」
と言われました
…母は掃除が苦手、特にトイレ掃除が嫌いな人でありました。
…なるほど…。
顔も、だけれど、心根のきれいな子になるよう祈りを込めて〝実家の〟トイレを掃除いたしました。
トイレの神様ならぬ、仏さまがおられます。
この仏さまがクローズアップされ有名になったのは、やはりあの歌のおかげなのかもしれない。
このお方のお姿を写した仏像を見ると、トイレを汚したままにすると何やら叱られてしまいそうな気がする。
その御仏は烏枢沙摩明王(うすさ(し)まみょうおう)さま。
明王さまと呼ばれる御仏はとても恐いお顔をされておられます。
たとえば不動明王さま。
お不動さま、と呼ばれ親しまれています。
恐いお顔をされておられますが、悪いものは許さないという強い御意志の表れであって、その実とても優しく寄り添ってくださるお方でございます。
烏枢沙摩明王さまもそのお姿は恐いです。
ですが、不浄なものをきれいにしてくださる仏さまであられます。
それを誓願とされた御仏でございます。
私は神社仏閣とはほど遠く、神仏を崇めることなく生きてきた期間の長い人間ですので、烏枢沙摩明王さまの存在を知ったのも早くはありません。
なので烏枢沙摩明王さまに叱られるからきれいにしよう、しておこうといった感覚を持つ以前から、仕事に向かう前、どんなに忙しくとも必ず欠かさなかったのがトイレ掃除でありました。
この狭い空間くらいなら、短時間でも掃除できる、そういった思いもありました。
もう長いことこれが私のルーティンとなっています。
(続きます)
(トイレをお護りくださる御仏のお話の続き)
そうした毎日を送っていると、自然、外出先でお手洗いをお借りしても、きれいにお掃除されていると感謝の思いでいっぱいになります。
汚すのは掃除をしている本人ではありません。
どこの誰とも知らない人間です。
それをピカピカに磨き上げ、埃もないようにしておられるトイレ。
それだけではなく、使用される方の目を、心を少しでも楽しませるよう、季節の花を置いてくださったり、飾りを置いてくださるトイレまであります。
これに感謝せずして、何に感謝する?
私のかつての勤務先では清掃の方が入っておられました。
その方のお掃除もまたとても丁寧で、道端の花を手折ってきては、とてもセンスのある生け方をしてくださっていました。
そんなことは会社のマニュアルになどもちろんありません。
その方の御心からのもの。
職種も、なんなら勤める事業所も異なりましたが、時々ご一緒にお食事をさせていただくくらい親しくしていただきました。
そう生きてこられたから、トイレ掃除一つにしても生き方があらわれるのだなぁと、思います。
ただ、…この烏枢沙摩明王さまは、ご自身のご誓願である、汚れたところをきれいにするということを心がける、あるいはご職業、ボランティアでなさる方に自然寄り添ってくださるといいます。
ありがたいことです。
今はもう連絡もとっておりませぬ彼女が健康で幸せに暮らしておられますように、烏枢沙摩明王さまに祈ります。
【烏枢沙摩明王】さま
烏枢沙摩明王さまは、
インドの火の神【アグニ】が元になっているとされ、
不浄を燃やし清浄にするため【火頭金剛(かずこんごう)】さまとも称されるといいます。
【不動明王】さまを中心とした【五大明王】と称せられる明王さま方がおられます。
その北方には金剛夜叉明王さまが配されますが、
天台宗では烏枢沙摩明王を配することがあるようです。
金剛夜叉明王さまと烏枢沙摩明王さまは、誓願に共通点があり、同一視されたのではという説もあります。
烏枢沙摩明王さまは古くから、不浄な場所を清浄にする力が強いので、トイレなどに祀られること多い明王さまです。
初めてそのお姿をトイレで拝見した時、
(なんとバチ当たりな!)と畏れおののいたものであります。
不浄除け以外の御利益としては、
子宝安産、
病魔除けや魔除けなど、
祟りを鎮める霊験があると伝わります。
また、枯れかけた樹木や野山に花を咲かせたり、枯れ井戸や泉に水を戻したりなど、生命や水にまつわるご利益があるようです。
憑き物除けのお力も強いと伝えられます。
怨みや妬み、怨念などの不浄な心や魂をも清浄に変えてしまうとされ、人間関係の悩みも消し去ってくださるそうです。
うーん。
烏枢沙摩明王さまにおかれましては、トイレに御鎮座いただくよりも人の世での大きな悩みであります、人間関係のこと、
そして人の心の中にある恨みや妬み、邪念などをお収めいただきたいと切に切に思うのですが…。
そういったことを願うこと自体が穢れた心、ということでありましょうか。
…ですよね。
【吉見百穴】という史跡をご存知でしょうか?
埼玉県吉見町というところにある、『古墳時代の横穴墓群』であります。
こちらは国の史跡に指定されておりますが、…群馬という地は埼玉県とはお隣という位置関係、情報が入りやすい土地柄でありますので、それゆえまったく興味のないような私でも知っているものとはなりますが、なにぶんにも日本は広い。
世界的にみれば狭い島国となりましょうが、いくら情報の豊かな時代を迎えたといっても、人間、興味のないもの、ましてや遠くに存在する遺跡などはあまり知らないもの、…えっ?そんなことはない?
私などはその名を子供の時分から存じてはいるものの、どんなに古くとも〝お墓〟というだけで行きたいとは思えないビビりですし。
実際何度か吉見百穴が見えるところまで行きながら、行っていないという…。
じゃあ何故?
何故ここで吉見百穴の話を?
…当然そう思われますよね。
まあ、長くこちらをお飲みくださりおつきあいくださっている方は、
(ああ、またか)と、お笑いになっておられるやもしれませんが。
実は今年、その吉見百穴のすぐそばに【岩室観音堂】と呼ばれるお堂があると夫が連れて行ってくれたのです。
吉見百穴から南へ150メートルに位置し、町中心部に通じる幹線道路の近くにありました。
…ええ、わずか150メートルほどですから、当然吉見百穴はそこから見えておりました。
おりはしましたが、またまた今回も遠巻きに見ておしまい。
百穴、といいながら実は二百以上の墓穴が存在するというだけあって、遠くからでも草も生えない砂岩の岩山にぼこぼこと穴の開いた様子は見えるもの。
お墓だから怖いというビビりおばさんでなくとも、一見ちょっと異様な光景に見える、…はず。
…本当はね、どうせこの世に生まれたからには
『なんにでも好奇心をもってとりあえず見る』方が良いのはわかるんです。
ですが、短い人生だから、『見たいものを見る』、でも良いじゃない?
そんな吉見百穴のすぐそばの【岩室観音堂】は、私の好きな懸造りの建物でありました。
(岩室観音堂 続き)
こちらの縁起は、嗟峨天皇の御宇・弘法大師が諸国を遊歴しこの地に至り、岩窟を選び三味に入り、観世音の尊像を彫刻し岩により殿をかまえ【岩室山】と号したのがはじまりといわれています。
その開山は弘仁年間といわれますが、たしかな記録は残っていません。
この岩室観音堂はかつてあった松山城にほど近く、松山城主が代々信仰し護持しておりましたが、
天正十八年松山城の攻防戦の際に兵火にあって当時の堂宇はことごとく焼失してしまいます。
しかしながら党宇は残らず消失したにもかかわらず、聖観音さまの尊像だけは不思議にも岩窟内に無事おわしたといいます。
現在のお堂は、江戸時代の寛文年間に龍性院第三世堯音が近郷近在の信者の助力を得て再建したもので、
お堂の懸造りは江戸時代ののとしては、めずらしいものだといいます。
また、こちらには四国八十八ヶ所弘法大師巡錫の霊地に建てられた寺々の本尊を模した石仏が八十八体祀られています。
今も龍性院さんの境外仏堂であります。
(続きます)
(続き)
近づいて行くにつれ、岩室観音堂は他の懸造りのお堂とはだいぶ異なるものであることに気づきました。
今までに私がお参りさせていただいた懸造りのお堂は、上にそびえるお堂のそり出した部分の下側を見ながら、脇に設けられた坂なり、きざはしを登って上がっていき、お堂の前に向かうものてありました。
しかしながら、この岩室観音堂さんは懸造りの建物の真下に入り口が設けられ、さらには簡素ではありますが囲いがあり、それは四方を囲むものではありませんが形として一階部分になっておりました。
さらに変わっていたのは、一階部分とはいえ、剥き出しの岩場、さらには自然が作り出した洞があって、一階部分の真正面は明らかに山の麓といった景色が広がっていたのです。
むしろ異質にさえ見える、二階へのきざはしでありました。
ちょっと怖い…それが正直な私の気持ちでありました。
お堂の建つ場所にあって、地面には水たまりがあり、岩肌にはイワカガミが生い茂り、
この建物が何故江戸時代から残って建っていられるのかが不思議でなりません。
そしてこの懸造りの建物の一階部分に入り込んだ左右に洞があって、そこには数多くの石仏さまがお祀りされておられるのです。
いつもなら石仏さまを拝見させていただくと心ときめくような私が、その洞に足を踏み入れることすらためらうような…。
本来、ここは四国八十八霊場にあたるお寺さんのそれぞれのご本尊さまのお姿を写しとった石仏さまがお祀りされておられるので、この洞に入ってお参りすることこそが正しいお参りであるのにも関わらず、です。
実はこちらの地域、どういった信仰なのか、その石仏さまにお札を貼り付け供養する習慣があるようなのですが…。
石仏さまの胸元に貼られたおびただしい供養のためのお札が、その光景を見慣れていない私にはどうにも怖く感じさせるものであったのでありました。
お札をよく拝見すれば、その意図は理解できるもの。
ですが、その光景に尻込みした私はなかなか近づくことができなかったのです。
…ビビり、ですから、ね 笑。
(続きます)
今日の深夜一時頃、細い月が明るい木星を伴つ て東の空に昇ってきます。
今日は旧暦七月二十六日。
今夜の月は二十六夜月と呼ばれ三日月を反転させた美しい姿をしています。
かつて『二十六夜待ち』といって、お酒を酌み 交わしながらこの月の出を待つ風習があったといいます。
旧暦の一月と七月、年に二回行われていたのだそうです。
年に二度、夜空を見上げながら月の出を待つ日、…なんとも風情があって素敵な気がします。
夫は飲むのは好きだけれど、月の出の頃まで起きてはいられない人。
私はといえば万が一に備えてお酒を飲まない。
今宵は一人、窓から月を愛でるとしますか。
読みかけの本でも読みながら。
(岩室観音堂 続き)
観音堂の一階部分の左右に洞があって、それぞれの洞に四国八十八霊場それぞれのご本尊さまの石仏さまが祀られているということですが、左側の洞を覗いてみると、
その石仏さまの胸元に、縦長の紙が貼られているのが見えます。
それも何枚も重ねて貼られて。
こちらに来る前に参拝させていただいた吉見観音さんでも石仏さまの胸元にお札が貼られてはいたのですが、こちらはその比ではないほど重ねられ貼られているのです。
石仏さまの数の多さもあって、この初めて見る風習に私は正直ビビっておりました。
で、その洞に立ち入ることができない。
この石仏さま大好きおばさんが。
ただ、この観音堂、順路が設けられていて、まずは二階にあがるよう矢印で指示されています。
ま、まずは二階へ。
この階段、背の高い方には少し登りづらい。
とはいえ江戸時代に造られたお堂ですので、当時の日本人の身長からすれば少し頭を下げるくらいで登れる造りでありましょう。
夫は百八十センチほど身長がありますので、なにやらブツブツ申しておりましたが、私は当時の日本人男性の身長くらい、トントントンと登ってまいりました。
階段はくるっとまわって二階部分へ。
奉納された大きな絵が飾られているのが目に入りました。
そしてその反対側、お堂の正面からいうと左側に御内陣様の場が設けられ、そこは木の柵で覆われており、その奥におられるであろう観音さまのお姿は垂れ幕の影で見えないのか、それともその垂れ幕に隠れた御厨子でもあるのか、まったく拝することはできません。
古い境外堂ということもあり、あまり手をかけることがないのか少し荒れているようにもみえます。
ちなみにこの日、観音さまの御縁日ということで、毎月法要を営むこととなっているよう書かれておりましたが、そうした様子は感じられませんでしたし、ひと月に一度でも手入れをし、法要をしているお堂には、正直見えませんでした。
あのお札を見ても、こちらを信心されておられる方は多いようなので、年に一度とかでも法要が営まれているといいのだけれど…。
(続きます)
飛び飛びになってごめんなさい。
本日二十二日は【如意輪観音】さまの御縁日です。
新月も重なりますので、より願いが届きやすいともいわれます。
如意輪観音さまは、
『意の如く願いを叶える【如意宝珠(にょいほうじゅ)】と、
煩悩や災いを滅し、仏法が広がる【法輪(ほうりん)】の御力が強い仏さま。
六道の衆生を救済するため、六本の腕がある観音さまです。
六道にあてられた六観音では、天道(天界)を司る観音さまにあたられます。
天道を司る如意輪観音さまは、古くは
月待ちの女人講・十九夜念仏講の御本尊で、そのことから女性を守る観音さま、女性の願いをよく聞いてくださる観音さまとされています。
ただご本尊さまとしてお祀りされておられることはほとんどなく、どちらかというと月待ちの女人講、念仏講の石仏さまとしてお祀りされていることがほとんどです。
その信仰を裏付けるかのように、もしかしたらお地蔵さまに次いで石仏さまとして彫られ祀られておられるかもしれません。
右の手の一本を頬に当てるかかの仕草と、輪王座という胡座に立て膝のような独特な座り方と、右側に顔を傾けた物憂げなその表情は、なんともアンニュイなお姿であり、一度覚えたら二度と忘れない観音さまでありましょう。
とはいえ。
新暦のため、月待の御縁日が新月となっていると、なんだか不思議に思えてしまうのですが、新月はより願いが届きやすいといわれているという説を信じますか。
いろいろと生きづらい世でありますが、
すべての人が自分なりに心穏やかに過ごせますよう、
心身のどこかを病む方のお痛みが少しでも早く癒えますように、
祈ります。
(岩室観音堂 続き)
こちらのお堂の二階にある御内陣のひだりてに小さな折り紙が置かれていました。
なんだろう…。
読むとその一枚一枚に般若心経の一文字が書かれていて、その折り紙で折り鶴を折ると書かれています。
願いを込めて。
昨年秋に広島で泊まったホテルで折り紙が置かれていたことを思い出しました。
広島での折り鶴に込める願いは祈りでもあり、その願いはひとつ、あるいはふたつ。
戦争のない世、原爆の無い世界をと強く願い、
亡くなられた方の冥福を祈ること。
ここでも同じ思いで折れば良いのだろうけれど、ここではいろいろな方のいろいろな願いに紛れてしまいそうで。
折り紙を手にすることなく、お姿の見えない観音さまに手を合わせて、…下へと向かう階段を降りました。
そういえば、あの広島の地で平和を願い、冥福を祈る千羽鶴が燃やされた事件がありました。
人の心を失ってはいけない。
でもそうした、人の心を持つ人間の所業とは思えない、思いたくもない事件はここ数年多発しております。
人の心を失った人間には、神仏など怖くはありません。
神仏を信じる心など持ち合わせてはおりません。
人の心を持つことはない、動物にすら劣る行為、劣る心根。
それも恥ではないので、何もこたえない。
人という文字は支え合う姿から、というのはまったくの後付けなようですが、
支え合って生きるということは大きな大きな力となる。
そういった歴史も振り返ってみるといいと、
戦で落城した城跡のふもとに建つ観音堂で思うのもまたおかしななこと、なのかしら。
…話が逸れ過ぎましたね。
(続き)
階段を降りると正面を入っての右側に出ます。
少し高いところにお祀りされた石仏、左側と同じような…趣きはかなり違うけれど…洞があって、その入り口からお顔を失った石仏さまが一体おられるのが見えます。
でもまずはそこではなく奥に広がる急な斜面を見上げます。
そこは自然のおりなしたものをかつて人的に手を加え、城への侵入をふせぎ、かつ登り口の一つであったろう路。
ひとしきりそこを見上げ(登る人もいるようだが、かなり難易度は高い)
やはり自然がおりなした岩くぐりを見上げる。
鉄製の鎖を使って登るものです。
一瞬躊躇ったのは前日の雨でかなりぬかるんでいること、岩場も湿っていかにも滑ること。
でも〝ハート型〟と言われると登りたくなるのが一欠片だけは残っていたらしい乙女心。
えっちらおっちら、よっこいしょ。
……ハ、ハート?
ま、見様によっては?
客寄せだなぁ。
『願い事をしながらくぐると願いが叶います』
え。
あのぉ〜…。
「滑らないように、滑らないように」と心で唱え続けていた私です。
速攻で願いは叶いましたぞ。
……。
さすが四国八十八ヶ所霊場のご本尊さまが勢揃いなさっているだけあります。
…もっと違うことを願いたかったなぁ。
気を取り直して。
右側の洞へと入ります。
(続きます)
↓ハート型に見えますか?
(続き)
右側の洞は若干斜め、そして天井も低い。
そこへ四十体ほどの石仏さまが安置されておりますので、なかなかお詣りしづらいです。
しかしながらこちらの洞は横に長いので、足を踏み入れないことには奥におられる石仏さまの尊顔を拝することができないのです。
ここでようやく石仏さまに貼られたお札を読むこととなるのですが、
【奉拝 百地蔵尊二世安樂之為也】
とあります。
いやいや、こちらには四国八十八ヶ所霊場の〝それぞれの〟ご本尊さまのお姿を写した石仏さまが祀られている…。
それはたとえばお不動さまであったり、十一面観音さまだったり、お釈迦さまであったり。
阿弥陀さまであったり、千手観音さまであったり、お薬師さまであったりと、実にさまざまな御仏の尊像となります。
百地蔵と書かれたお札であるならば、せめてお地蔵さまに貼り付けないといけないのでは?
いつから、であったろう。
私が厄除けであるとか、方位除けであるとかを知ったのは。
さらにはそれが気になるようになったのは。
私の育った家は、厄除けであるとか方位除けであるとかを全く気にしない家であった。
さもあらん、のちに知ったことだが、私の両親は教会で、ウエディングドレスを着て結婚式を挙げていたのであった。
だからといって日曜日に教会に行きミサに参列するような事も一切なかった。
私が物心がついた頃にはもはやその信仰心は失っていたのか、
とにかく、家には仏壇も神棚もないが、かといってクロスや聖書があったわけでもないのだった。
そんな家庭でもあったこともあり、お寺さんに行くのはもっぱら父方の祖母と。
それも、お盆であるとかお彼岸であるとか、まあ大抵の日本人がお寺さんに行くようなタイミングでのみであった。
神社に至っては、年に一度の県内外から人が集まるような大きなお祭りの時と、七五三のときだけ。
あとはもっぱら友人との遊び場でしかなかった。
今思うと冷や汗モノ。
さすがに厄除けという言葉くらいは聞いたことはあったが、この世に御祈祷であるとか、御祈願であるとかがあることすら知らずに、結構な歳になったのが私である。
今年、結構私の子どもたちは前厄であったり、方位除けの年にあたっておりました。
なんなら孫に至るまで。
でも今までずうっと、そんなことを気にしたこともなく、お祓いも受けたことなどない私。
まあ、方位除けや厄除けの御守りをお授けいただいて、各々に渡せば良いであろう。
毎年初詣に伺う神社さんには割札のようになっている絵馬のようなお札があり、片方を神社の絵馬掛けに掛け、片方を自宅にお祀りするといったお札?絵馬?をお授けいただき、御守りと一緒に渡したのでありました。
そんな令和七年も十月をむかえました。
…いやぁ、方位除けの人たち、実にいろいろありました。
怖っ。
なんでだよぉ〜。
凄い的中率。
私、たいそうビビって、早々に来年の厄年、方位除けの年廻りをチェックしました。
…またいるよ。
厄年が二人、
方位除けが一人。
ひえぇ〜っ。
私の寝る部屋の窓から、今の時期、今の時刻は月がよく見える。
今宵の月はなんと優しい月だろう。
上弦の月から少しふくらんだ、
やわらかな優しい黄色い月だ。
こんなお菓子があったよな。
来週には十五夜を迎える、…ん?だとしたら今日は十日ん夜かしら。
昔の人は月をよく愛で、そしてそこに信仰を結びつけ、ご近所さんと講をもったようだ。
今そんなお付き合いはどうなのだろう。
人付き合いのよい人、
人付き合いの盛んな地域では月と結びつけることはなくとも、夜集まっては話したり、お酒を酌み交わし、持ち寄った食べ物を食べたりしているのかもしれない。
私は人付き合いは苦手だし、それほどのお付き合いをさせていただいている方もいない。
それでも月の光はすべての人の上に平等に注ぐ。
寂しい人の心にも。
嬉しい思いを抱いた人の心にも。
…つらい思いを抱えて、月を見上げることすら出来ない人の上にも。
今日は達磨大師の亡くなられた日、逹磨忌とされます。
達磨さまは南天竺において国王の第三王子として生まれ、中国で活躍した仏教の僧侶であります。
幼名は菩提多羅といいました。
若い頃に父である国王が亡くなり、菩提多羅王子は国政を二人の兄に頼み、お釈迦さまから二十七代目にあたる般若多羅尊者のもとに出家し、『菩提達磨』の僧名を頂きました。
師に就いて四十年修行、般若多羅尊者から釈尊正伝の第二十八代目を継承しました。
しかし師より「六十七年間はインドを布教し、その後に中国に正法(しょうぼう)を伝えなさい」と遺言され、それに従って老年になってから、海路を三年かかって中国・広州へと渡ります。
梁(りょう)の武帝と問答し、縁かなわず揚子江を渡って洛陽の都のはずれ、嵩山(すうざん)少林寺の裏山の洞窟に住み、『面壁九年』壁に向かって九年間の坐禅をされました。
その結果、その手足は壊死し失われてしまいます。
そんな達磨のもとに求道者・神光(しんこう)が現れ、その熱意に感じ中国で初めて弟子をとり、慧可(えか)と名付けました。
達磨さまはこの慧可にすべてを伝え、中国に禅宗の基礎を築かれます。
しかしながらその教えを理解できない者たちによって毒殺され、熊耳山(ぎゅうじざん)定林寺(じょうりんじ)に葬られました。
それが今日、十月五日と伝わります。
達磨大師を知らないとおっしゃる方も、あの赤い張子のダルマさんはご存知でしょう。
群馬県の高崎市には【少林山達磨寺】というお寺があります。
このお寺さんこそが一説によるとあの赤いダルマさんの発祥の地と伝えられているのであります。
全国的には何種類かのダルマがあるといいますが、高崎ダルマは眉が鶴、口元の髭が亀という縁起をかついだ画風が特徴です。
高崎市はこのダルマを誇りとし、道路沿いや駅にもダルマさんが飾られ、高崎駅ではプラスティック製のダルマさんの容器に入った『だるま弁当』という駅弁が売られています。
このだるま弁当、私の子どもの頃からのロングセラー商品。
お弁当の空き容器はコイン大の穴を開けて貯金箱になるとか言われていますが、そうした使い方をされている方を見たことはありません。
お砂遊びや雪遊びで型として使うのは時折見かけましたが、ね。
(群馬県高崎市の少林山達磨寺の続き)
室町時代、群馬県高崎市の碓氷川の南側、鼻高村の高台に
【行基菩薩】が彫られたとされる四尺ほどの厄除・子授け・縁結びにご利益のある観音さまを祀る小さな観音堂がありました。
延宝年間(1673~1681)のある年、大雨が降り碓氷川が氾濫はんらんしたことがあったといいます。
水が引けたころ、川の中に黒光りした大きなかたまりがあるのを見つけ、引き上げてみると香りのする大きな古木でありました。
村人たちは霊木としてその木を観音堂に納めたといいます。
観音さまの尊像の前に安置すると、不思議にも紫の霞がたなびいたといい、村人はみな、よいことのある前兆であると大変喜びました。
ちょうどその洪水があった頃、全国を行脚する『一了居士』という行者の夢枕に達磨大師が立たれ
「この私の像を彫りなさい、その木は鼻高にある」
とおっしゃったといいます。
延宝八(1680)年、一了居士は鼻高の地を探しあて、村人に夢枕の話をしました。
それは観音堂に納められた霊木のことであろうと村人が案内しました。
一了居士はまさにそれこそが達磨大師のお告げの木であると涙を流して喜びました。
一了居士は、沐浴斎戒(身を清めて、肉・魚・酒や臭いのきつい野菜などを絶つこと)をし、
一刀三礼(一彫りごとに五体投地の礼拝をすること)、心を込めて見事な達磨大師の坐禅像を彫りあげました。
達磨大師の像は村人たちの評判となり、この観音堂のあたりはいつともなしに“達磨出現の霊地”として【少林山】と呼ばれる用になり近隣に広まりました。
その頃の領主『酒井雅楽頭忠挙』公は厩橋城(前橋城)の裏鬼門を護る寺として、
『水戸光圀』公の帰依された中国僧・『東皐心越禅師』を開山と仰ぎ、弟子の天湫和尚を水戸から請じて、元禄十(1697)年【少林山達磨寺】を開創しました。
享保十一(1726)年、水戸徳川家から三葉葵の紋と丸に水の徽章を賜い、永世の祈願所とされました。
天明三(1783)年は浅間山の大噴火などの天変地異が多く起こり、かの有名な大飢饉となります。
この惨状を見かね、付近の農民救済のため九代住職東嶽和尚が、開山心越禅師の画いた【一筆達磨坐禅像】をもとに木型を彫り、張り子のだるまの作り方を豊岡村の山縣友五郎に伝授します。
これが縁起だるまの始まりといいます。
今日は旧暦の八月十五日、
【中秋の名月】です。
旧暦の暦に当てはめてのものなので、十五夜が必ず満月とは限らず、今年は明日が満月🌕にあたります。
『月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月』
うーん。
この素晴らしい読みようにただただうなるばかりでありますが、この歌、実は読み人知らずであるといいます。
お月見は平安時代に中国から伝わり、貴族たちは池の水やお酒に映した月を眺めて楽しんだそうです。
江戸時代になると庶民にも広がり、豊作を願って里芋などのいも類をお供えしたことから〝芋名月〟と呼ばれることもあるのだとか。
アメリカでもこの十月の満月は〝ハーベスト・ムーン〟と呼ばれます。
ちなみに満月のピークは七日の12時48分。
真昼の月、ですか。
はて。
離れ住む子供たちに
『月がきれいですね』
とメッセージを送るタイミングは、いつになるだろう。
今日はさらに一粒の種が万倍にも実るという【一粒万倍日】
天が赦しを与える吉日【天赦日】だといいます。
うーん、吉日♡
ちなみに仏滅ではありますが、十五夜は暦の上では必ず仏滅が当たります。
それゆえ『仏滅名月』というあまりありがたくない呼び方もあるようです。
月が明るくきれいな夜であることから【良夜】とも呼ばれる今日。
みなさんに良き日となりますように。
「月がきれいですね🌕」
どこにその木があるのかわからなくともその香りでその花が咲きはじめたこと、その存在を知ることができる、金木犀の季節がやってきました。
すっかり秋の空です。
色づき始めたもみじ。
毎月八日のお護摩供に足利まで車を走らせて
八月に入院した家人の病の平癒をご祈願していただきました。
秋の日を浴びて気持ち良さそうに破顔される布袋さま。
稚児大師さまもひなたぼっこ。
実りの秋。
お寺さんにも実りが♡
今日のお護摩には
跡取りとなられるお坊さまが参加されました。
うれしそうで誇らしげな奥さまと娘さん。
カメラでその勇姿おさめようと早々とお堂の前でスタンバイされていました。
…すこぉしだけ居心地悪そうなご住職さま。
お寺さんに幸あれ。
そして…。
離れ暮らす家人が寛解いたしますよう、家人一家が幸せに暮らせますように。
群馬県に【赤城山】という山があります。
なんとこの山、群馬県のかなりの市町村から見ることのできるというお山。
多くの群馬県民に愛される山であります。
ただ、【赤城山】と呼ぶ単体の峰はなく、ひとつの火山帯ではあるのですが複数の山頂を持つ連山の総称ではあります。
標高1800mから1200mの峰々が取り囲んで円頂を構成し、裾野の大きさは、約35kmの富士山に次ぐ日本で2番目の規模であるといわれます。
山岳信仰の対象ともされ、関東一円に約三百社の赤城神社が分布しています。
そのうちの一社がこの赤城山の大沼にある【大洞赤城神社】さま。
こちらにお祀りされる神さまは
【赤城大明神】さま。
女神さまにございます。
この山を訪れると私は、どうにもすぐれなかった体調が良くなるという〝不思議〟が起こることが多く、とはいえ運転がたいそうほにゃららな私、そうそうはこちらのお山に来ることも叶わない。
それゆえ、赤城山の見えるところでは必ず赤城山の神さまを遥拝するのでありました。
きのう夫が赤城山へと連れて行ってくれました。
赤城山は赤城おろしと呼ばれる強い風が吹いてくるお山とされますが、きのうはたいそう優しい、風ともいえぬくらいのやわらかな空気が包んでくれました。
優しくて、人の心配ばかりしている、可愛らしいあの方に、あのきのうの赤城のやわらかな空気が届きますように。
私が何年も書き連ねてきたこの『神社仏閣珍道中』録。
神社仏閣といいながら、その実態はお寺さんに偏っている自覚はありました。
石仏さまや御仏の尊像が好きなこともありましたし、何よりお寺さんに行くと心が落ち着いたのです。
それは今も変わらない。
…変わらないのだけれど…。
お寺に関われば関わるほど、本来なら僧侶としてはありえない行為を目にすることが多くなり、心が疲れてしまった気がするのです。
ご本尊さまの御前の蝋燭の灯を口を尖らして息で吹き消したり、…そんなことは序の口で。
法具を段ボール箱に投げ入れたり、まるで投げ捨てるかのような勢いで地べたに投げ置いたり。
果ては弘法大師の坐像が必ず手に持つほどの法具でポスターの人の顔、それも目をめがけて突きつけたり。
無住寺であることからお山から住職を言い遣ったお寺が、新住職を迎えるにあたり御本堂を建て替えてまで歓待しようとしていたというのに、
あろうことか、その旧本堂にあった欄間飾りを全て外して、実家の寺の本堂にはめ込んでしまい、しかも、その新しくなったお寺には不在で、実家であるお寺に常在していたり。
檀家でもない私の、目を見て、話が途切れるまで優しく耳を傾け話を聴き、そして心に寄り添うお言葉をおかけくださった僧侶が、思いもよらない形で失脚されたのも、少なからず影響しているかもしれません。
末法思想の、まさに末法。
お釈迦さまの危惧しておられた末法の世にあたるいまだから、いたしかたないことなのかもしれないけど、心は疲弊する。
もちろんそんなことは一切なく、御仏に仕え、仏法に帰依する僧は大勢おられます。
そして。
御仏は変わらない。
いつもそんな世を、見捨てることなく見護ってくださっておられる。
でも今はわたしの心が正直ついていけないのです。
少なくともお寺さんに出向くことが激減している。
毎月、私事で何事もなければ、きまって伺うお寺さんへは今もお参りをしております。
しかしながら、とあるお寺さんで六十年に一度の御開帳が行われる今、行けない状況におかれても、遥拝で全く平気、心が揺らがない。
ある意味ではより仏教に近づいた?
…日本仏教ではないかもしれない?
里の道ばたにおられる石仏さまをお訪ねしました。
道の傍におられる石仏さまは
お地蔵さまや馬頭観音さま、
如意輪観音さま、
そして青面金剛さま
がほとんどなのだけれど…。
時代の流れに合わせて、区画整理をし、道を新たにつくったり、家を建てるべく宅地造成されたりとして、石仏さまは元おられた場を移動されることもしばしばです。
道の傍に小さなお堂があることもあり、今回は薬師如来さまの御像にお会いすることが多かった。
季節の変わり目、そして夏日からいきなり冬のような寒さ。
体調を崩される方も多いかもしれません。
そして、かつては冬だけ、あるいはオリンピックの年にだけ何故か流行った流行病が、もうずっと蔓延状態が続いています。
コロナは型を変え続け一向に収まる気配をみせません。
どうかみなさんが心身の不調無く過ごせますように。
どうぞくれぐれもご自愛ください。
前スレ・次スレ
小説・エッセイ掲示板のスレ一覧
ウェブ小説家デビューをしてみませんか? 私小説やエッセイから、本格派の小説など、自分の作品をミクルで公開してみよう。※時に未完で終わってしまうことはありますが、読者のためにも、できる限り完結させるようにしましょう。
- レス新
- 人気
- スレ新
- レス少
- 閲覧専用のスレを見る
-
-
![]()
![]() 国会ウォッチング③~政治を語る~ 9レス 142HIT コラムニストさん
国会ウォッチング③~政治を語る~ 9レス 142HIT コラムニストさん -
![]()
![]() すしお 〈スパ〉 0レス 48HIT コック
すしお 〈スパ〉 0レス 48HIT コック -
![]()
![]() 狂気!!コックのデス・クッキング〈キャラ紹介〉 0レス 45HIT コック
狂気!!コックのデス・クッキング〈キャラ紹介〉 0レス 45HIT コック -
![]()
![]() ユアマイエブリシング 25レス 204HIT 流行作家さん
ユアマイエブリシング 25レス 204HIT 流行作家さん -
![]()
![]() 狂気!!コックのデス・クッキング しばらく休載 0レス 88HIT コック
狂気!!コックのデス・クッキング しばらく休載 0レス 88HIT コック
-
![]()
![]() ユアマイエブリシング
ユアマイエブリシング やはり実際の出来事をエッセイとして書いて行こうか リアルの方も今…(流行作家さん0)
25レス 204HIT 流行作家さん -
![]()
![]() 国会ウォッチング③~政治を語る~
国会ウォッチング③~政治を語る~ ↑ 信じられないわな…… 一方で、今のテレビのトランプ・サナエフ…(コラムニストさん0)
9レス 142HIT コラムニストさん -
![]() 20世紀少年
20世紀少年 太陽にほえろ 確か始まったのは72年。僕は小6の時だ。マカロニ、…(コラムニストさん0)
175レス 3437HIT コラムニストさん -
![]() 猫温泉
猫温泉 大勢の動物さんたちはたのしそうに温泉入りました。(たかさき)
4レス 117HIT たかさき (60代 ♂) -
![]()
![]() 神社仏閣珍道中・改
神社仏閣珍道中・改 里の道ばたにおられる石仏さまをお訪ねしました。 道の傍におられる…(旅人さん0)
205レス 11968HIT 旅人さん
-
-
-
閲覧専用
![]() 生きていたいと願うのは 1レス 52HIT 小説家さん
生きていたいと願うのは 1レス 52HIT 小説家さん -
閲覧専用
![]()
![]() ドアーズを聞いた日々 500レス 1077HIT 流行作家さん
ドアーズを聞いた日々 500レス 1077HIT 流行作家さん -
閲覧専用
![]()
![]() 真夏の海のアバンチュール〜ひと夏の経験 500レス 1931HIT 流行作家さん
真夏の海のアバンチュール〜ひと夏の経験 500レス 1931HIT 流行作家さん -
閲覧専用
![]()
![]() where did our summer go? 500レス 1772HIT 作家さん
where did our summer go? 500レス 1772HIT 作家さん -
閲覧専用
![]() 20世紀少年 2レス 226HIT コラムニストさん
20世紀少年 2レス 226HIT コラムニストさん
-
閲覧専用
![]()
![]() ドアーズを聞いた日々
ドアーズを聞いた日々 私がピアノを弾く番になりロングドレスのママさんがピアノを弾いてと言った…(流行作家さん0)
500レス 1077HIT 流行作家さん -
閲覧専用
![]() 生きていたいと願うのは
生きていたいと願うのは 私は自分が嫌いだ。 なぜかと聞かれたらいくらでも答えられる。 …(小説家さん0)
1レス 52HIT 小説家さん -
閲覧専用
![]()
![]() 真夏の海のアバンチュール〜ひと夏の経験
真夏の海のアバンチュール〜ひと夏の経験 オクマビーチに到着してみんなで夕焼けをながめた 1年後も沖縄で楽…(流行作家さん0)
500レス 1931HIT 流行作家さん -
閲覧専用
![]()
![]() where did our summer go?
where did our summer go? そして、例様がケニーロジャーズのLady を歌う 聖子とミスター…(作家さん0)
500レス 1772HIT 作家さん -
閲覧専用
![]()
![]() モーニングアフター モーリンマクガバン
モーニングアフター モーリンマクガバン お昼ご飯のお刺身を食べ終わり私はレンタカーで例様を社員寮へと送る …(作家さん0)
500レス 3558HIT 作家さん
-
閲覧専用
新着のミクルラジオ一覧
サブ掲示板
注目の話題
-
相続放棄したいが
父名義の持ち家があります。 両親とも存命ですが、2人とも施設にいてもう家に帰って来れないです。 …
13レス 225HIT 相談したいさん -
毎週凸してくる義母への対応
結婚して3年。 娘が産まれてから2年…毎週義母が凸してきます。 別に仲は悪くはありません。 …
19レス 206HIT 結婚の話題好きさん (30代 女性 ) -
普通に生きてれば
普通に生きてればイケメンやかっこいいは複数人(学校、バイト先、会社など)に言われるものでしょうか? …
13レス 195HIT おしゃべり好きさん (30代 男性 ) -
思い出してしまいます
凄く好きだった元彼と別れ1年半になりますが思い出して時々胸が物凄く苦しくなります。 彼の浮気が原因…
7レス 198HIT 恋愛好きさん (20代 女性 ) -
Xお金配りについて
Xであるお金配りますみたいなやつあれって詐欺ですよね?やりとりするとLINEが送られてきます 奴ら…
6レス 118HIT 匿名さん -
洗濯洗剤とバスマジックリン 間違えた。
部屋干し用洗濯洗剤のアタックのボトルが空になったので詰め替えようと思い、 間違えてバスマジックリン…
10レス 143HIT ちょっと教えて!さん - もっと見る